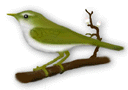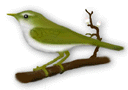
 セイヨウオトギリソウは、ヨーロッパ、アジア、北アフリカに分布し、日本にも帰化して野生化している多年草です。草丈は約1mになり、直立して分枝が多いく、茎に2本の縦の隆起線を有するのが特徴です。楕円形で無柄の葉には透明な腺点と縁に黒い腺点があります。7~8月頃、枝の先に集散花序を出してレモンの香りのする黄色の5弁花をつけます。花や葉を押しつぶすと、蛍光色素を放出するため赤色に変わり、芳香性の香りを発します。
全草を乾燥したものが「カンヨウレンギョウ」で、収れん、抗菌、止血、利尿作用などがあり、喀血、吐血、リウマチによる骨痛、胃・腸カタル、黄疸などに用いられます。外用として火傷や口腔炎にも用いられます。
セイヨウオトギリソウは、ヨーロッパ、アジア、北アフリカに分布し、日本にも帰化して野生化している多年草です。草丈は約1mになり、直立して分枝が多いく、茎に2本の縦の隆起線を有するのが特徴です。楕円形で無柄の葉には透明な腺点と縁に黒い腺点があります。7~8月頃、枝の先に集散花序を出してレモンの香りのする黄色の5弁花をつけます。花や葉を押しつぶすと、蛍光色素を放出するため赤色に変わり、芳香性の香りを発します。
全草を乾燥したものが「カンヨウレンギョウ」で、収れん、抗菌、止血、利尿作用などがあり、喀血、吐血、リウマチによる骨痛、胃・腸カタル、黄疸などに用いられます。外用として火傷や口腔炎にも用いられます。
 セイヨウナツユキソウ は一般的に世話が簡単だと考えられ、湿った、酸性から中性の土壌で繁栄し、部分的な日陰から直射日光に向いています。重要な特別なケアポイントは、一貫して湿っている土壌を必要とし、定期的な水やりと乾燥を避ける必要があることです。さらに、土壌の水分を保持し、根を保護するためにマルチ層を施すことが有益です。また、日陰の部分で繁栄し、光と日陰のバランスの取れた優しい光を受ける場所が最適です。この最適な光環境は健全な成長を可能にし、健康と花付け能力に寄与します。全日光にかなりの耐性を示すことがありますが、過度の曝露はストレスを引き起こし、その勢いに悪影響を与え、葉が焼ける可能性があります。屋外の環境では、日中の強い日差しのある地域では、明るさがかすかまたはフィルターされた場所に植えるべきです。
セイヨウナツユキソウ は一般的に世話が簡単だと考えられ、湿った、酸性から中性の土壌で繁栄し、部分的な日陰から直射日光に向いています。重要な特別なケアポイントは、一貫して湿っている土壌を必要とし、定期的な水やりと乾燥を避ける必要があることです。さらに、土壌の水分を保持し、根を保護するためにマルチ層を施すことが有益です。また、日陰の部分で繁栄し、光と日陰のバランスの取れた優しい光を受ける場所が最適です。この最適な光環境は健全な成長を可能にし、健康と花付け能力に寄与します。全日光にかなりの耐性を示すことがありますが、過度の曝露はストレスを引き起こし、その勢いに悪影響を与え、葉が焼ける可能性があります。屋外の環境では、日中の強い日差しのある地域では、明るさがかすかまたはフィルターされた場所に植えるべきです。
 セイヨウノダイコンは地中海からヨーロッパ、中央アジアまでが原産地ですが、世界中に広く導入され、チョーク質や砂質の地域で育ちます。アメリカを含むいくつかの国では侵入性のある雑草としてリストされています。セイヨウノダイコンは帰化種で、詳細は不明ですが昭和初期に非意図的に渡来し、現在では北海道から九州にかけて分布しています。「ダイコン」という名前がついてますが、私たちが普段食べているダイコンとは異なり、セイヨウノダイコンは根が肥大しません。アメリカ合衆国の多くの州では侵略的な種または農業雑草として定義されています。食用目的や受粉者を引き寄せるために栽培されてきましたが、農業害虫の代替宿主としても機能します。大量の種子生産を通じて急速に広がり、撹乱された生息地に容易に定着します。効果的な制御には除草剤やその他の方法(耕作や土壌の極性化など)の統合が一般的に必要です。
セイヨウノダイコンは地中海からヨーロッパ、中央アジアまでが原産地ですが、世界中に広く導入され、チョーク質や砂質の地域で育ちます。アメリカを含むいくつかの国では侵入性のある雑草としてリストされています。セイヨウノダイコンは帰化種で、詳細は不明ですが昭和初期に非意図的に渡来し、現在では北海道から九州にかけて分布しています。「ダイコン」という名前がついてますが、私たちが普段食べているダイコンとは異なり、セイヨウノダイコンは根が肥大しません。アメリカ合衆国の多くの州では侵略的な種または農業雑草として定義されています。食用目的や受粉者を引き寄せるために栽培されてきましたが、農業害虫の代替宿主としても機能します。大量の種子生産を通じて急速に広がり、撹乱された生息地に容易に定着します。効果的な制御には除草剤やその他の方法(耕作や土壌の極性化など)の統合が一般的に必要です。
 マンテマは、ナデシコ科マンテマ属に属する草本の一種です。ヨーロッパ原産の一年草で、日本では江戸時代に観賞用に持ちこまれ後に逸出し野生化し、本州中部以南の河川敷、市街地、海岸などに見られる外来種となっています。マンテマは、およそ150年ほど前、観賞用にと日本にはいってきたとされるかなり古い帰化植物です。いまどきのガーデニングでカラフルな園芸植物とちがって、ずいぶんと控えめです。しかし、花びらの紅色の紋のまわりが白くふちどられ、小さい花ながら人の目をひきます。シロバナマンテマのロゼット葉は,歩道の低い木の植え込みのふちで、冬の日を浴びて春にそなえています。地ぎわから広げている根生葉(ロゼット葉)はしゃもじ形をしています。道路ぞいの街園の草地に群がって生えているところです。花は白色からうすいピンク色で、だいたい同じ向きに突き出しています。マンテマとのちがいは、ヒトにたとえますと人種のちがいのようなもの。どちらも花の大きさは1cmぐらいですがシロバナのほうは花びらも細くてマンテマより見劣りがします。
マンテマは、ナデシコ科マンテマ属に属する草本の一種です。ヨーロッパ原産の一年草で、日本では江戸時代に観賞用に持ちこまれ後に逸出し野生化し、本州中部以南の河川敷、市街地、海岸などに見られる外来種となっています。マンテマは、およそ150年ほど前、観賞用にと日本にはいってきたとされるかなり古い帰化植物です。いまどきのガーデニングでカラフルな園芸植物とちがって、ずいぶんと控えめです。しかし、花びらの紅色の紋のまわりが白くふちどられ、小さい花ながら人の目をひきます。シロバナマンテマのロゼット葉は,歩道の低い木の植え込みのふちで、冬の日を浴びて春にそなえています。地ぎわから広げている根生葉(ロゼット葉)はしゃもじ形をしています。道路ぞいの街園の草地に群がって生えているところです。花は白色からうすいピンク色で、だいたい同じ向きに突き出しています。マンテマとのちがいは、ヒトにたとえますと人種のちがいのようなもの。どちらも花の大きさは1cmぐらいですがシロバナのほうは花びらも細くてマンテマより見劣りがします。
 「きくらげ」という名前や茶色くプリッとした見た目から、「きくらげは海藻なのか?それとも山菜なのか?」と考える人も多いのではないでしょうか。実は、きくらげは「菌類」としてジャンル分けされています。干したクラゲに味が似ていることから、樹木に生えるクラゲという意味で「きくらげ」と名付けられました。しかし、きくらげ自体は海藻や山菜ではなく、キクラゲ科キクラゲ属のキノコの一種です。自然界のきくらげは、ケヤキやニワトコ、クワ、グミ、ニレなど、広葉樹の枯れ木や倒木に群生し、その存在は世界中で確認されています。しかし、古くから食用としてきくらげを利用してきた日本や中国、韓国などのアジア圏とは違い、欧米などでは最近まで食用としての利用はされていませんでした。欧米できくらげは、薬草学者によって目の炎症を治療するための湿布剤や、喉の問題の緩和剤といった薬用菌として利用されてきた歴史があります。
「きくらげ」という名前や茶色くプリッとした見た目から、「きくらげは海藻なのか?それとも山菜なのか?」と考える人も多いのではないでしょうか。実は、きくらげは「菌類」としてジャンル分けされています。干したクラゲに味が似ていることから、樹木に生えるクラゲという意味で「きくらげ」と名付けられました。しかし、きくらげ自体は海藻や山菜ではなく、キクラゲ科キクラゲ属のキノコの一種です。自然界のきくらげは、ケヤキやニワトコ、クワ、グミ、ニレなど、広葉樹の枯れ木や倒木に群生し、その存在は世界中で確認されています。しかし、古くから食用としてきくらげを利用してきた日本や中国、韓国などのアジア圏とは違い、欧米などでは最近まで食用としての利用はされていませんでした。欧米できくらげは、薬草学者によって目の炎症を治療するための湿布剤や、喉の問題の緩和剤といった薬用菌として利用されてきた歴史があります。
 ヨーロッパキイチゴは、ヨーロッパおよび北米を原産とし、16世紀にはじめてイギリスで栽培、18世紀末にはヨーロッパから米国へ導入され、19世紀後半から栽培が盛んになった経緯があり、その果実は腐敗しやすいため主にその香りと色を活かしたジャム、リキュール、ジュース、菓子類などの加工品に利用されています。日本においては明治初期に栽培種が導入され、農林水産省北海道農業試験場で適応品種の選択も行われたましたが、同時期に導入されたリンゴ、ブドウ、モモなどに比べて経済性が乏しく、加工品としての需要が伸びなかったことから、経済果樹としての産地の形成には至らず、現在は適応品種が北海道、宮城県、長野県、福岡県などで小規模に栽培され、主にジャムに加工されています。ただし、果実にはビタミンCが豊富であり、近年ではポリフェノールの含有量が多いことも明らかにされてきたことから、機能性食品として注目される機会が増えており、家庭用苗木の流通が盛んな品種もあることから、きっかけ次第で栽培量・流通量が増える可能性を秘めていると推測されます。
ヨーロッパキイチゴは、ヨーロッパおよび北米を原産とし、16世紀にはじめてイギリスで栽培、18世紀末にはヨーロッパから米国へ導入され、19世紀後半から栽培が盛んになった経緯があり、その果実は腐敗しやすいため主にその香りと色を活かしたジャム、リキュール、ジュース、菓子類などの加工品に利用されています。日本においては明治初期に栽培種が導入され、農林水産省北海道農業試験場で適応品種の選択も行われたましたが、同時期に導入されたリンゴ、ブドウ、モモなどに比べて経済性が乏しく、加工品としての需要が伸びなかったことから、経済果樹としての産地の形成には至らず、現在は適応品種が北海道、宮城県、長野県、福岡県などで小規模に栽培され、主にジャムに加工されています。ただし、果実にはビタミンCが豊富であり、近年ではポリフェノールの含有量が多いことも明らかにされてきたことから、機能性食品として注目される機会が増えており、家庭用苗木の流通が盛んな品種もあることから、きっかけ次第で栽培量・流通量が増える可能性を秘めていると推測されます。
 スイランは中部地方以西の本州から九州に分布する多年草ですが、近年温暖化の影響で東北地方でも確認されています。低地の湿原やその周辺、貧栄養な溜池の湖岸などに生育します。地下茎があり、長さ15~40cmほどの細長い根出葉を出します。葉の縁には不明瞭な鋸歯がまばらにあり、柔らかいがやや厚く、裏面は粉白色であり、両面無毛で切ると白い乳液がでます。9月から10月にかけ、高さ50~80cmほどの花茎を出し、分枝してその先端に頭花をつけます。頭花は直径3~3.5cmで、ニガナの仲間とよく似た黄色い花を咲かせます。9月頃はまだ根出葉は残っていますが、10月の終わり頃になると葉は枯れてしまい、茎の上に花だけが咲いている状態になります。スイランの和名を漢字で書くと水蘭です。花を見るとキクの花であり、とても蘭とはいい難いです。
スイランは中部地方以西の本州から九州に分布する多年草ですが、近年温暖化の影響で東北地方でも確認されています。低地の湿原やその周辺、貧栄養な溜池の湖岸などに生育します。地下茎があり、長さ15~40cmほどの細長い根出葉を出します。葉の縁には不明瞭な鋸歯がまばらにあり、柔らかいがやや厚く、裏面は粉白色であり、両面無毛で切ると白い乳液がでます。9月から10月にかけ、高さ50~80cmほどの花茎を出し、分枝してその先端に頭花をつけます。頭花は直径3~3.5cmで、ニガナの仲間とよく似た黄色い花を咲かせます。9月頃はまだ根出葉は残っていますが、10月の終わり頃になると葉は枯れてしまい、茎の上に花だけが咲いている状態になります。スイランの和名を漢字で書くと水蘭です。花を見るとキクの花であり、とても蘭とはいい難いです。
 スイセンノウはヨーロッパ南東部の原産で、二年草あるいは短命な多年草です。スイセンノウは、ビロードのような白い毛の生えた株と、小さいけれど目立つ整った花が魅力的です。花は花茎を分枝させその頂部に咲かせます。一重で花つきもよいです。葉色や茎が銀色で細かい毛が生えています。株はロゼット状ですが開花時は長い花茎を伸ばします。タネから育てる場合、開花には低温に合わせる必要があるので秋まきにします。高温多湿には弱いものの、こぼれダネでも増える丈夫な花です。5月から7月の中頃にかけ、派手な赤色のナデシコの仲間が花壇などで目立っています。栽培植物なので気にしていなかったのだが、注意して見ると荒地に勝手に生育しているものが結構あります。園芸植物の逸出です。スイセンノウは白い毛が全草に多いことからフランネルソウとも呼ばれています。
スイセンノウはヨーロッパ南東部の原産で、二年草あるいは短命な多年草です。スイセンノウは、ビロードのような白い毛の生えた株と、小さいけれど目立つ整った花が魅力的です。花は花茎を分枝させその頂部に咲かせます。一重で花つきもよいです。葉色や茎が銀色で細かい毛が生えています。株はロゼット状ですが開花時は長い花茎を伸ばします。タネから育てる場合、開花には低温に合わせる必要があるので秋まきにします。高温多湿には弱いものの、こぼれダネでも増える丈夫な花です。5月から7月の中頃にかけ、派手な赤色のナデシコの仲間が花壇などで目立っています。栽培植物なので気にしていなかったのだが、注意して見ると荒地に勝手に生育しているものが結構あります。園芸植物の逸出です。スイセンノウは白い毛が全草に多いことからフランネルソウとも呼ばれています。
 スズメノヤリは、単子葉植物イグサ科に属する植物です。見かけはイグサには似ず、小柄なイネ科植物に見えます。茎は短くて地中にあり、地表には根出葉だけを伸ばします。葉はイネ科植物のような線形の細長い形で、ゆるやかに曲がって、断面は浅いU字になっています。葉は緑色でややつやがあり、縁に沿って長くて白い毛がまばらに生えています。また、葉の先端がすらりと細くなるのではなく、先端の部分が細いながらも厚い棒状の形になって終わっています。日本産の同属のものは、ほとんどがこの特徴をもつので、ここに気をつければ花がなくても見分けがつきます。3月ころに穂を伸ばします。10cm位の細長い花茎が伸びて、その先端に花が頭状に集まっています。見かけ上は個々の花ははっきりせず、赤褐色のくす玉のような固まりが着いているように見えます。固まりは一つ、あるいは二つくらいに分かれており、時には短い柄を伸ばしてその先により小さな固まりをつけます。なお、花茎の途中には一枚の苞葉がついています。
スズメノヤリは、単子葉植物イグサ科に属する植物です。見かけはイグサには似ず、小柄なイネ科植物に見えます。茎は短くて地中にあり、地表には根出葉だけを伸ばします。葉はイネ科植物のような線形の細長い形で、ゆるやかに曲がって、断面は浅いU字になっています。葉は緑色でややつやがあり、縁に沿って長くて白い毛がまばらに生えています。また、葉の先端がすらりと細くなるのではなく、先端の部分が細いながらも厚い棒状の形になって終わっています。日本産の同属のものは、ほとんどがこの特徴をもつので、ここに気をつければ花がなくても見分けがつきます。3月ころに穂を伸ばします。10cm位の細長い花茎が伸びて、その先端に花が頭状に集まっています。見かけ上は個々の花ははっきりせず、赤褐色のくす玉のような固まりが着いているように見えます。固まりは一つ、あるいは二つくらいに分かれており、時には短い柄を伸ばしてその先により小さな固まりをつけます。なお、花茎の途中には一枚の苞葉がついています。
 ユウゲショウは、アカバナ科の多年草の帰化植物。日本には観賞用植物として入ってきたものが野生化し、関東以西に広く分布しています。夕方に咲くことが名前の由来とされていますが、実際には昼間から咲く一日花です。夏から秋にかけて、明るいピンク色の花が次々と開花し、めしべの先が十字状になる特徴があり、白花もあります。多年草ですが種でも繁殖し、日当たりの良い道端、河原、野原、空き地などいたるところで見かけます。ユウゲショウはアカバナユウゲショウとも呼ばれ、アメリカ大陸(熱帯地域)原産の外来(帰化)植物で、日本国内では、主に関東以西の市街地や荒れ地、耕作地周辺など日当たりが良く、乾燥気味の場所で見られる多年草です。世界の暖温帯地域に広く帰化しており、日本には明治時代に観賞用の園芸植物として持ち込まれたものが逸出(逃げ出し)、野生化したとされます。
ユウゲショウは、アカバナ科の多年草の帰化植物。日本には観賞用植物として入ってきたものが野生化し、関東以西に広く分布しています。夕方に咲くことが名前の由来とされていますが、実際には昼間から咲く一日花です。夏から秋にかけて、明るいピンク色の花が次々と開花し、めしべの先が十字状になる特徴があり、白花もあります。多年草ですが種でも繁殖し、日当たりの良い道端、河原、野原、空き地などいたるところで見かけます。ユウゲショウはアカバナユウゲショウとも呼ばれ、アメリカ大陸(熱帯地域)原産の外来(帰化)植物で、日本国内では、主に関東以西の市街地や荒れ地、耕作地周辺など日当たりが良く、乾燥気味の場所で見られる多年草です。世界の暖温帯地域に広く帰化しており、日本には明治時代に観賞用の園芸植物として持ち込まれたものが逸出(逃げ出し)、野生化したとされます。
 ムラサキウマゴヤシは、地中海沿岸原産で、日本には明治初期に入り、北海道などで栽培されているほか、各地に帰化しています。日本で見られるウマゴヤシ属のなかで、紫色の花が咲くのはムラサキウマゴヤシだけなので、見分けやすいですが、茎が直立し、小葉が細長いのも特徴です。高さは30〜90cm。小葉は長さ2〜3cm、幅0.5〜1cmで、豆果はらせん状に巻きますが、ウマゴヤシのような刺はありません。花期は5〜9月です。ムラサキウマゴヤシ(紫馬肥やし)は、マメ科ウマゴヤシ属の多年草で、別名アルファルファとも呼ばれます。牧草として導入されましたが、現在では野生化しているものも見られます。また、種子を発芽させた「アルファルファもやし」は、食用としても利用されています。
ムラサキウマゴヤシは、地中海沿岸原産で、日本には明治初期に入り、北海道などで栽培されているほか、各地に帰化しています。日本で見られるウマゴヤシ属のなかで、紫色の花が咲くのはムラサキウマゴヤシだけなので、見分けやすいですが、茎が直立し、小葉が細長いのも特徴です。高さは30〜90cm。小葉は長さ2〜3cm、幅0.5〜1cmで、豆果はらせん状に巻きますが、ウマゴヤシのような刺はありません。花期は5〜9月です。ムラサキウマゴヤシ(紫馬肥やし)は、マメ科ウマゴヤシ属の多年草で、別名アルファルファとも呼ばれます。牧草として導入されましたが、現在では野生化しているものも見られます。また、種子を発芽させた「アルファルファもやし」は、食用としても利用されています。
 サルトリイバラは、日本全国の日当たりの良い山野に生育するつる性の落葉低木です。国外では、中国、朝鮮半島、台湾から東南アジアにまで分布します。つる性と言っても、茎は硬く、フジなどのように樹木にぐるぐると巻き付くようなことはなく、葉柄部分から出る2本の巻きひげで他の植物にしがみつくようにして成長します。葉は直径3~12cmほどになる円形で、質は厚く、全縁(縁にギザギザがない)、両面無毛です。茎にはまばらに鋭いトゲがあり(トゲの数には個体差があり、ほとんどない個体もある)、葉が着いた部分ごとに折れ曲がってジグザグになっています。花は4~5月頃、葉の付け根の部分から散形花序を出し、淡黄緑色の花を多数咲かせます。果実は液果で、晩秋に鮮やかな赤色に熟します。熟したばかりの時には食べることもできますが(甘くはないが、少し酸っぱい味)、時期が遅くなると、乾燥してしまって中は種子ばかりになります。鳥などに食べられなければ落葉後もつるに残るため、生け花や、クリスマスリースの飾りなどにも使われます。果実の中にはあずき色をした直径1cm弱の種子が5~6個入っています。
サルトリイバラは、日本全国の日当たりの良い山野に生育するつる性の落葉低木です。国外では、中国、朝鮮半島、台湾から東南アジアにまで分布します。つる性と言っても、茎は硬く、フジなどのように樹木にぐるぐると巻き付くようなことはなく、葉柄部分から出る2本の巻きひげで他の植物にしがみつくようにして成長します。葉は直径3~12cmほどになる円形で、質は厚く、全縁(縁にギザギザがない)、両面無毛です。茎にはまばらに鋭いトゲがあり(トゲの数には個体差があり、ほとんどない個体もある)、葉が着いた部分ごとに折れ曲がってジグザグになっています。花は4~5月頃、葉の付け根の部分から散形花序を出し、淡黄緑色の花を多数咲かせます。果実は液果で、晩秋に鮮やかな赤色に熟します。熟したばかりの時には食べることもできますが(甘くはないが、少し酸っぱい味)、時期が遅くなると、乾燥してしまって中は種子ばかりになります。鳥などに食べられなければ落葉後もつるに残るため、生け花や、クリスマスリースの飾りなどにも使われます。果実の中にはあずき色をした直径1cm弱の種子が5~6個入っています。
 真夏の強い日ざしの中でも元気に咲くマツバボタン。茎が這うように広がり、枝分かれしながら咲き続けます。花壇やコンテナはもちろん、砂利道のわきや敷石の間などの乾きやすいところでもよく育ちます。日当たりと水はけがよく、多湿にならない場所であれば、ほとんど手入れの必要もなく、栽培は容易です。一日花ですが花数が多く、6月から9月ごろまでほとんど途切れることなく次々と咲きます。園芸品種では花がしぼむのが遅く、夕方ごろまで開くように改良されています。花色が豊富で、一重咲きから八重咲き、さらに万重咲きまであり、場所によってはこぼれダネで毎年自然に育ちます。また、古くから栽培されている品種‘ジュエル’(‘Jewel’)は耐寒性があり、軽い霜程度なら越冬します。
真夏の強い日ざしの中でも元気に咲くマツバボタン。茎が這うように広がり、枝分かれしながら咲き続けます。花壇やコンテナはもちろん、砂利道のわきや敷石の間などの乾きやすいところでもよく育ちます。日当たりと水はけがよく、多湿にならない場所であれば、ほとんど手入れの必要もなく、栽培は容易です。一日花ですが花数が多く、6月から9月ごろまでほとんど途切れることなく次々と咲きます。園芸品種では花がしぼむのが遅く、夕方ごろまで開くように改良されています。花色が豊富で、一重咲きから八重咲き、さらに万重咲きまであり、場所によってはこぼれダネで毎年自然に育ちます。また、古くから栽培されている品種‘ジュエル’(‘Jewel’)は耐寒性があり、軽い霜程度なら越冬します。
 ヤマアジサイは、主に太平洋側の福島県から四国・九州に分布しています。半日陰の湿り気のある林や沢沿いに生育しています。このことから別名のサワアジサイの名前がつきました。周辺の自然によくなじんでいる樹木です。中央から花の外側に向かって咲き、縁に沿って装飾花をつけてガクアジサイと同じようにガク咲きとなります。装飾花(中性花)の萼片は、白色または白青色で少し反り返りますが、紅色を帯びることもあります。ガクアジサイよりも花序が小型なので、コガクと呼ばれることもあります。アジサイに比べて葉は、薄くて細長く小型です。野趣に富んだ樹形で、花色や花形は地域による変異が多く、愛好家の間で人気の高い花木です。
ヤマアジサイは、主に太平洋側の福島県から四国・九州に分布しています。半日陰の湿り気のある林や沢沿いに生育しています。このことから別名のサワアジサイの名前がつきました。周辺の自然によくなじんでいる樹木です。中央から花の外側に向かって咲き、縁に沿って装飾花をつけてガクアジサイと同じようにガク咲きとなります。装飾花(中性花)の萼片は、白色または白青色で少し反り返りますが、紅色を帯びることもあります。ガクアジサイよりも花序が小型なので、コガクと呼ばれることもあります。アジサイに比べて葉は、薄くて細長く小型です。野趣に富んだ樹形で、花色や花形は地域による変異が多く、愛好家の間で人気の高い花木です。
 コミノネズミモチ は一般的にさまざまな環境での強靱さと適応性で認められており、手入れが簡単な植物です。主な手入れポイントは、十分な日光を確保し、定期的な水やり、根腐れを防ぐための良好な排水の土を提供することにあります。コミノネズミモチ
は剪定に耐えられるため、その健康と美的形状にメリットがありますが、いくつかの地域ではその侵食的な性質から成長を管理することが不可欠です。生息地の湿度レベルの変動に適応し、コミノネズミモチ
は中程度の水分を好み、短い乾燥期を耐えることができます。この強靱さは、1〜2週間に1回の水やりスケジュールをお勧めし、その植物の自然な環境を模倣するバランスを保つことを意味します。一般的に屋外で育てられる常緑植物であるコミノネズミモチ
は、葉によって水分を保持し、植物周囲の湿度を維持し、さまざまな気候帯での活力に貢献します。
コミノネズミモチ は一般的にさまざまな環境での強靱さと適応性で認められており、手入れが簡単な植物です。主な手入れポイントは、十分な日光を確保し、定期的な水やり、根腐れを防ぐための良好な排水の土を提供することにあります。コミノネズミモチ
は剪定に耐えられるため、その健康と美的形状にメリットがありますが、いくつかの地域ではその侵食的な性質から成長を管理することが不可欠です。生息地の湿度レベルの変動に適応し、コミノネズミモチ
は中程度の水分を好み、短い乾燥期を耐えることができます。この強靱さは、1〜2週間に1回の水やりスケジュールをお勧めし、その植物の自然な環境を模倣するバランスを保つことを意味します。一般的に屋外で育てられる常緑植物であるコミノネズミモチ
は、葉によって水分を保持し、植物周囲の湿度を維持し、さまざまな気候帯での活力に貢献します。
 キツネノボタン(狐の牡丹)は、キンポウゲ科キンポウゲ属の多年草で、実の形からコンペイトウグサと呼ばれることもあり、秋田県雄勝郡、山形県酒田市、新潟県佐渡市、長野県下水内郡、福岡県山門郡・八女郡・柳川市、大分県南海部郡・佐伯市ではウマゼリとも呼ばれています。山道でキツネノボタンの可愛らしい花が咲いていた。家の近くに生えていたものがキツネノボタンではなくウマノアシガタだと最近気がつきましたが、こちらは種の先端が鉤爪状になっており、葉も完全に3つに分かれた複葉となっているのでキツネノボタンで間違いなさそうです。この葉の形が牡丹に似ていることから名付けられたそうです。日当たりの良い斜面ではウマノアシガタが大きく堂々と生える一方で、日陰の山道ではキツネノボタンが小さくひっそり咲いており、力関係の一端を見た気持ちです。
キツネノボタン(狐の牡丹)は、キンポウゲ科キンポウゲ属の多年草で、実の形からコンペイトウグサと呼ばれることもあり、秋田県雄勝郡、山形県酒田市、新潟県佐渡市、長野県下水内郡、福岡県山門郡・八女郡・柳川市、大分県南海部郡・佐伯市ではウマゼリとも呼ばれています。山道でキツネノボタンの可愛らしい花が咲いていた。家の近くに生えていたものがキツネノボタンではなくウマノアシガタだと最近気がつきましたが、こちらは種の先端が鉤爪状になっており、葉も完全に3つに分かれた複葉となっているのでキツネノボタンで間違いなさそうです。この葉の形が牡丹に似ていることから名付けられたそうです。日当たりの良い斜面ではウマノアシガタが大きく堂々と生える一方で、日陰の山道ではキツネノボタンが小さくひっそり咲いており、力関係の一端を見た気持ちです。
 ツキヨタケは、初夏~秋に、ブナなどの広葉樹の倒木や枯れ木などに多数重なり合って発生します。中型~大型で、傘は半円形~じん臓形(長径 10~25cm)、表面ははじめ黄橙褐色でやや濃色の小鱗片がありますが、成熟すると紫褐色~暗褐色となり、多少ろう状の光沢を帯びます。ひだは垂生(柄に対し、ひだが下向きの弧を描いて付着)し、淡黄色のち白色で幅広く、暗所で青白く発光します。柄は長さ2cm程度で太短く、傘のほとんど側方、まれに中央に付き、隆起した不完全なつばがあります。縦に裂くと、柄の付け根部分にふつう黒紫色、まれに淡褐色のしみがあります。肉は白色でやわらかく、柄に近い部分は厚く、食用のヒラタケ、ムキタケ、シイタケに、外見、色彩、サイズ等が酷似しているため、誤食による中毒がクサウラベニタケに並んで多く発生します。
ツキヨタケは、初夏~秋に、ブナなどの広葉樹の倒木や枯れ木などに多数重なり合って発生します。中型~大型で、傘は半円形~じん臓形(長径 10~25cm)、表面ははじめ黄橙褐色でやや濃色の小鱗片がありますが、成熟すると紫褐色~暗褐色となり、多少ろう状の光沢を帯びます。ひだは垂生(柄に対し、ひだが下向きの弧を描いて付着)し、淡黄色のち白色で幅広く、暗所で青白く発光します。柄は長さ2cm程度で太短く、傘のほとんど側方、まれに中央に付き、隆起した不完全なつばがあります。縦に裂くと、柄の付け根部分にふつう黒紫色、まれに淡褐色のしみがあります。肉は白色でやわらかく、柄に近い部分は厚く、食用のヒラタケ、ムキタケ、シイタケに、外見、色彩、サイズ等が酷似しているため、誤食による中毒がクサウラベニタケに並んで多く発生します。
 桜の実は、桜の花が終わった後にできる小さな実のことです。一般的に食用には適さず、豆粒ほどの大きさで、次第に黒っぽくなります。一部の桜の木には食用になる実がなるものもありますが、それは「さくらんぼ」として知られる別の品種です。桜の花が咲いた後にできる実は、ソメイヨシノなどの観賞用の桜では、食用に適さないものがほとんどです。「さくらんぼ」として知られる果実は、セイヨウミザクラなどの品種の桜から採れるもので、食用に適しています。さくらんぼは、桜の仲間ではありますが、観賞用の桜とは異なる品種であり、果実を食用とすることを目的として栽培されています。桜の実には、渋みや苦み成分が含まれているものや、有害なシアン化合物を含むものもあるため、注意が必要です。桜の実は、食用以外にも、絵を描いたり、種を採取して育てたりするなど、様々な利用方法があります。
桜の実は、桜の花が終わった後にできる小さな実のことです。一般的に食用には適さず、豆粒ほどの大きさで、次第に黒っぽくなります。一部の桜の木には食用になる実がなるものもありますが、それは「さくらんぼ」として知られる別の品種です。桜の花が咲いた後にできる実は、ソメイヨシノなどの観賞用の桜では、食用に適さないものがほとんどです。「さくらんぼ」として知られる果実は、セイヨウミザクラなどの品種の桜から採れるもので、食用に適しています。さくらんぼは、桜の仲間ではありますが、観賞用の桜とは異なる品種であり、果実を食用とすることを目的として栽培されています。桜の実には、渋みや苦み成分が含まれているものや、有害なシアン化合物を含むものもあるため、注意が必要です。桜の実は、食用以外にも、絵を描いたり、種を採取して育てたりするなど、様々な利用方法があります。
 ナガボノシロワレモコウは湿原や湿性の草原に生育する多年草です。北海道・関東地方以北の本州、樺太に分布しますが、中国地方などにも隔離分布しています。湿原に生育する植物は、氷河時代に分布したものが生き残っていることがあり、ナガボノシロワレモコウもその例の1つです。地下に太い根茎があり、8月から10月にかけ、高さ1mほどの茎を出して花を付けます。茎の上部は枝分かれして長さ2~5cm程の花穂を出し、長いものは垂れ下がります。花は先端から咲き始め、花弁はありません。萼片は4枚で白色であり、これが花の色となっています。雄しべは4本で長く、黒い葯が目立ちます。葉は11~15の小葉からなり、小葉の幅は狭いく、三角形の鋸歯があります。ナガボノワレモコウはコバナワレモコウ(白花)とワレモコウとの間にできた自然雑種と考えられ、連続的な変異が見られます。ナガボノワレモコウとコバナノワレモコウは区別が難しく、すべてナガボノワレモコウに含めるという見解もあります。
ナガボノシロワレモコウは湿原や湿性の草原に生育する多年草です。北海道・関東地方以北の本州、樺太に分布しますが、中国地方などにも隔離分布しています。湿原に生育する植物は、氷河時代に分布したものが生き残っていることがあり、ナガボノシロワレモコウもその例の1つです。地下に太い根茎があり、8月から10月にかけ、高さ1mほどの茎を出して花を付けます。茎の上部は枝分かれして長さ2~5cm程の花穂を出し、長いものは垂れ下がります。花は先端から咲き始め、花弁はありません。萼片は4枚で白色であり、これが花の色となっています。雄しべは4本で長く、黒い葯が目立ちます。葉は11~15の小葉からなり、小葉の幅は狭いく、三角形の鋸歯があります。ナガボノワレモコウはコバナワレモコウ(白花)とワレモコウとの間にできた自然雑種と考えられ、連続的な変異が見られます。ナガボノワレモコウとコバナノワレモコウは区別が難しく、すべてナガボノワレモコウに含めるという見解もあります。
 ヒエンソウは、高く伸びた花茎に青や紫、白、ピンクの花をたくさん咲かせるかわいらしい花です。名前の由来は、花の後ろに距 (きょ)と呼ばれるしっぽのような部分があり、
そのつぼみの形がイルカの背中を曲げた格好に似ていることから、ギリシャ語のイルカ (Delphis) からもじられ、つけられました。もともと北半球の温帯地域の比較的に冷涼で乾燥ぎみの場所に生育する多年草で、高温多湿な環境が苦手です。関東以西の暑さの厳しい地域では、暑さ耐えられず枯れてしまうため、日本国内では一年草として扱われることが多かったです。しかし、今では、200種余りの原種をもとに
たくさんの園芸品種が作り出され、暑さに強い品種も誕生しました。この品種改良により、暑さの厳しい地域でも花が楽しめるようになり、日本でも多年草としても利用できるようになりました。花びらのように見える部分は萼(ガク)で
中心の盛り上がっているところが花弁になります。
ヒエンソウは、高く伸びた花茎に青や紫、白、ピンクの花をたくさん咲かせるかわいらしい花です。名前の由来は、花の後ろに距 (きょ)と呼ばれるしっぽのような部分があり、
そのつぼみの形がイルカの背中を曲げた格好に似ていることから、ギリシャ語のイルカ (Delphis) からもじられ、つけられました。もともと北半球の温帯地域の比較的に冷涼で乾燥ぎみの場所に生育する多年草で、高温多湿な環境が苦手です。関東以西の暑さの厳しい地域では、暑さ耐えられず枯れてしまうため、日本国内では一年草として扱われることが多かったです。しかし、今では、200種余りの原種をもとに
たくさんの園芸品種が作り出され、暑さに強い品種も誕生しました。この品種改良により、暑さの厳しい地域でも花が楽しめるようになり、日本でも多年草としても利用できるようになりました。花びらのように見える部分は萼(ガク)で
中心の盛り上がっているところが花弁になります。
 ハカワラタケ(歯瓦茸)は、タマチョレイタケ科シハイタケ属の小型から中型のキノコ(菌類)で、白色腐朽菌です。日本各地のほか、北半球に広く分布するしています。一年を通じて発生し、広葉樹林の枯れ木や朽木の上に重なり合って群生し、極めて普通に見られるキノコで、広葉樹の枯れ木の表面に多数の子実体が屋根瓦状に広がっています。子実体は傘のみで柄がなく、扇形からへら形または半円形で、質は薄く、傘の幅は1.6cm、厚さは1.3mm位です。傘表面は灰白色から淡い灰褐色、あるいは淡い材木色などで、ほぼ無毛か微毛を密生し、同心円状に環紋があります。傘の縁部は薄くて鋭く、乾くと下部へ強く曲がり、幅狭く紫色に色づきます。傘裏は帯紫色から薄紅色、はじめは浅い管孔状で、のちに孔壁が深く裂けて薄い歯牙状になります。若いときの管孔の長さは0.5~1.5mmほどで、成長するに従って、管孔面は色褪せて淡褐色から灰褐色になり、傘裏の歯が目立つことが多く、肉は白色で、強靱な革質になっています。
ハカワラタケ(歯瓦茸)は、タマチョレイタケ科シハイタケ属の小型から中型のキノコ(菌類)で、白色腐朽菌です。日本各地のほか、北半球に広く分布するしています。一年を通じて発生し、広葉樹林の枯れ木や朽木の上に重なり合って群生し、極めて普通に見られるキノコで、広葉樹の枯れ木の表面に多数の子実体が屋根瓦状に広がっています。子実体は傘のみで柄がなく、扇形からへら形または半円形で、質は薄く、傘の幅は1.6cm、厚さは1.3mm位です。傘表面は灰白色から淡い灰褐色、あるいは淡い材木色などで、ほぼ無毛か微毛を密生し、同心円状に環紋があります。傘の縁部は薄くて鋭く、乾くと下部へ強く曲がり、幅狭く紫色に色づきます。傘裏は帯紫色から薄紅色、はじめは浅い管孔状で、のちに孔壁が深く裂けて薄い歯牙状になります。若いときの管孔の長さは0.5~1.5mmほどで、成長するに従って、管孔面は色褪せて淡褐色から灰褐色になり、傘裏の歯が目立つことが多く、肉は白色で、強靱な革質になっています。
 オカトラノオは平地から低い山地の日当たりのよい草地や道端に見られる多年草です。冬は地上部が枯れます。茎はまっすぐに立ち上がり、多数の卵形の葉をつけます。茎の先端に長さ15cm前後の花穂をつけ、多数の花を咲かせます。花穂は途中で横向きに曲がっているのが特徴です。葉や茎に短い毛があります。地下に細長い地下茎が多数あり、これを伸ばしてふえていきます。そのため群生しているのが普通です。草本の花も春に比べ少なくなっては来ましたが、7月にかけて白い花を咲かせるのがサクラソウ科のオカトラノオです。
オカトラノオは北海道から九州の、丘陵の日当たりの良い草地に生える多年草です。 茎や葉には細く短い毛がまばらに生えています。オカトラノオの花言葉は「忠実、貞操、優しい風情、清純な恋、騎士道」などです。また、属名のLysimachiaが、古代ギリシャのリュシマコス王がこの花で猛り狂った牛を鎮めた故事に由来することから、「鎮静」という意味も持つと木のぬくもり・森のぬくもりは伝えています。
オカトラノオは平地から低い山地の日当たりのよい草地や道端に見られる多年草です。冬は地上部が枯れます。茎はまっすぐに立ち上がり、多数の卵形の葉をつけます。茎の先端に長さ15cm前後の花穂をつけ、多数の花を咲かせます。花穂は途中で横向きに曲がっているのが特徴です。葉や茎に短い毛があります。地下に細長い地下茎が多数あり、これを伸ばしてふえていきます。そのため群生しているのが普通です。草本の花も春に比べ少なくなっては来ましたが、7月にかけて白い花を咲かせるのがサクラソウ科のオカトラノオです。
オカトラノオは北海道から九州の、丘陵の日当たりの良い草地に生える多年草です。 茎や葉には細く短い毛がまばらに生えています。オカトラノオの花言葉は「忠実、貞操、優しい風情、清純な恋、騎士道」などです。また、属名のLysimachiaが、古代ギリシャのリュシマコス王がこの花で猛り狂った牛を鎮めた故事に由来することから、「鎮静」という意味も持つと木のぬくもり・森のぬくもりは伝えています。
 キダチルリソウの起源は南アメリカとされ、その名前は太陽を追いかけるという意味の「ヘリオトロープ」に由来します。特にペルーでよく見られるこの花は、古代の人々にとっても重要な存在でした。キダチルリソウは「献身」と「永遠の愛」を象徴しています。このため、結婚式や恋人同士の贈り物に頻繁に使用されます。また、その香りはリラックス効果があるとされ、多くの文化圏で尊重されています。庭園や花壇でもキダチルリソウは非常に人気があります。その強い香りと美しい花は、庭全体を引き立てる効果があります。特に、リラックスしたい場所に植えると、その効果を一層高めることができます。キダチルリソウは結婚式でよく使用されます。その象徴する意味「永遠の愛」が新郎新婦の誓いにぴったりだからです。また、その美しい紫色は式場を華やかに彩ります。
キダチルリソウの起源は南アメリカとされ、その名前は太陽を追いかけるという意味の「ヘリオトロープ」に由来します。特にペルーでよく見られるこの花は、古代の人々にとっても重要な存在でした。キダチルリソウは「献身」と「永遠の愛」を象徴しています。このため、結婚式や恋人同士の贈り物に頻繁に使用されます。また、その香りはリラックス効果があるとされ、多くの文化圏で尊重されています。庭園や花壇でもキダチルリソウは非常に人気があります。その強い香りと美しい花は、庭全体を引き立てる効果があります。特に、リラックスしたい場所に植えると、その効果を一層高めることができます。キダチルリソウは結婚式でよく使用されます。その象徴する意味「永遠の愛」が新郎新婦の誓いにぴったりだからです。また、その美しい紫色は式場を華やかに彩ります。
 セイヨウアカミニワトコはヨーロッパ原産です。ヨーロッパ北部やカザフスタンにも導入されています。この植物は侵入性がなく、湿った岸を好みます。セイヨウアカミニワトコ
は、緩やかな生け垣、低木のボーダー、そして自由に広がることができるエリアでのマッシングに適した選択です。この植物には、森林や自然の庭が非常に良い選択肢です。根茎の広がりに圧倒される可能性のある植物と一緒に植えるべきではなく、コギグリアが一般的なコンパニオンです。セイヨウアカミニワトコの木には伝説や神話が数多く存在します。かつては、エルダーベリーの木に魔女が住んでいると信じられており、あなたの家の近くにセイヨウアカミニワトコを植えると、その魔女があなたの家庭に力を持つことができるとされていました。エルダーベリーを使ってゆりかごを作ることは禁じられていました。なぜなら、それが赤ちゃんに対する魔女の力を解放すると考えられていたからです。
セイヨウアカミニワトコはヨーロッパ原産です。ヨーロッパ北部やカザフスタンにも導入されています。この植物は侵入性がなく、湿った岸を好みます。セイヨウアカミニワトコ
は、緩やかな生け垣、低木のボーダー、そして自由に広がることができるエリアでのマッシングに適した選択です。この植物には、森林や自然の庭が非常に良い選択肢です。根茎の広がりに圧倒される可能性のある植物と一緒に植えるべきではなく、コギグリアが一般的なコンパニオンです。セイヨウアカミニワトコの木には伝説や神話が数多く存在します。かつては、エルダーベリーの木に魔女が住んでいると信じられており、あなたの家の近くにセイヨウアカミニワトコを植えると、その魔女があなたの家庭に力を持つことができるとされていました。エルダーベリーを使ってゆりかごを作ることは禁じられていました。なぜなら、それが赤ちゃんに対する魔女の力を解放すると考えられていたからです。
 ミゾカクシは、北海道~沖縄の各地に分布するキキョウ科の多年草です。水田の畔や溝などの湿った場所に生じ、時には地面が見えないほど群生するため、ミゾカクシ(溝隠し)と名付けられました。植物を編んで作った敷物の筵(むしろ)に例えた別名、アゼムシロも同様の意味合いです。ミゾカクシの開花は夏~秋で、葉の脇から伸びた長めの花茎の先端に、淡い紅紫の花が一輪ずつ上向きに咲きます。花は直径1センチほどの唇形で上唇は二つに、下唇は三つに裂けていますが、サワギキョウのように下半分へ偏るように咲きます。葉は長さ15mm、幅3mmほどの長楕円形で、茎から互い違いに、ややまばらに生じます。茎は細く枝分かれしながら地面を這うように広がり、節から根を出してさらに広がります。草丈は10~20cmほどで全体に無毛です。ミゾカクシは全草にアルカロイド系のロベリンを含んでおり、新芽や茎などを誤って食べると嘔吐、胃腸痙攣、呼吸麻痺などの症状に陥いります。食用するセリと同じような場所に生えるため、混入しないよう留意する必要があります。
ミゾカクシは、北海道~沖縄の各地に分布するキキョウ科の多年草です。水田の畔や溝などの湿った場所に生じ、時には地面が見えないほど群生するため、ミゾカクシ(溝隠し)と名付けられました。植物を編んで作った敷物の筵(むしろ)に例えた別名、アゼムシロも同様の意味合いです。ミゾカクシの開花は夏~秋で、葉の脇から伸びた長めの花茎の先端に、淡い紅紫の花が一輪ずつ上向きに咲きます。花は直径1センチほどの唇形で上唇は二つに、下唇は三つに裂けていますが、サワギキョウのように下半分へ偏るように咲きます。葉は長さ15mm、幅3mmほどの長楕円形で、茎から互い違いに、ややまばらに生じます。茎は細く枝分かれしながら地面を這うように広がり、節から根を出してさらに広がります。草丈は10~20cmほどで全体に無毛です。ミゾカクシは全草にアルカロイド系のロベリンを含んでおり、新芽や茎などを誤って食べると嘔吐、胃腸痙攣、呼吸麻痺などの症状に陥いります。食用するセリと同じような場所に生えるため、混入しないよう留意する必要があります。
 パンパスグラスは、庭植え用の苗として流通するほかに、秋に切り花としてもたくさん出回ります。庭植えのものを切り花として利用する場合、花穂が出る前の棒状のさやをナイフで削って、強制的に若い花穂を露出させると、光沢があってきれいです。ただし、葉の縁がノコギリ状になっているので、手を切らないよう、取り扱いには注意しましょう。パンパスグラスは、南アメリカとニュージーランド、ニューギニアに分布するススキに似た多年草で、約20種が知られています。栽培されるのは、明治中ごろに渡来したセロアナ種です。雌雄異株で、雌株の花穂には長い毛があり、観賞価値が高くなります。耐寒性は強くなく、2~3℃程度です。地中まで凍ると傷むので、若苗は凍らせないように防寒が必要です。寒冷地では大株でも防寒しないと、株が弱ります。
パンパスグラスは、庭植え用の苗として流通するほかに、秋に切り花としてもたくさん出回ります。庭植えのものを切り花として利用する場合、花穂が出る前の棒状のさやをナイフで削って、強制的に若い花穂を露出させると、光沢があってきれいです。ただし、葉の縁がノコギリ状になっているので、手を切らないよう、取り扱いには注意しましょう。パンパスグラスは、南アメリカとニュージーランド、ニューギニアに分布するススキに似た多年草で、約20種が知られています。栽培されるのは、明治中ごろに渡来したセロアナ種です。雌雄異株で、雌株の花穂には長い毛があり、観賞価値が高くなります。耐寒性は強くなく、2~3℃程度です。地中まで凍ると傷むので、若苗は凍らせないように防寒が必要です。寒冷地では大株でも防寒しないと、株が弱ります。
 オオヒエンソウ(大飛燕草)は、キンポウゲ科の多年草で、デルフィニウムとも呼ばれます。中国、モンゴル、シベリアなどが原産で、草原や潅木帯に自生しています。花は青紫色から青色で、花弁のように見えるのは萼片で、距(きょ)と呼ばれる突起があるのが特徴です。園芸品種も多く、シネンシス系、パシフィックジャイアント系、リトル系、ベラドンナ系などがあります。オオヒエンソウはその強靭さと手入れのしやすさが特徴で、庭師にとって簡単な植物です。主なケアポイントには、十分な日光を確保し、排水の良い土壌を提供することが含まれます。オオヒエンソウの元気はそのような環境で最良に支援されます。ナメクジやカタツムリの予防に特別な注意を払う必要があります。これらの害虫はオオヒエンソウに特に引き寄せられるため、健康と美観を損なう可能性があります。
オオヒエンソウ(大飛燕草)は、キンポウゲ科の多年草で、デルフィニウムとも呼ばれます。中国、モンゴル、シベリアなどが原産で、草原や潅木帯に自生しています。花は青紫色から青色で、花弁のように見えるのは萼片で、距(きょ)と呼ばれる突起があるのが特徴です。園芸品種も多く、シネンシス系、パシフィックジャイアント系、リトル系、ベラドンナ系などがあります。オオヒエンソウはその強靭さと手入れのしやすさが特徴で、庭師にとって簡単な植物です。主なケアポイントには、十分な日光を確保し、排水の良い土壌を提供することが含まれます。オオヒエンソウの元気はそのような環境で最良に支援されます。ナメクジやカタツムリの予防に特別な注意を払う必要があります。これらの害虫はオオヒエンソウに特に引き寄せられるため、健康と美観を損なう可能性があります。
 ヒロハヒルガオは北半球のヨーロッパ、アジア、北西アフリカ、北アメリカ、南半球のオーストラリア、南米のアルゼンチンなどに広く分布するツル植物です。検索すると日本では北海道でのヒットが多く、冷温帯の植物なのでしょう。高さ数mになり、葉は長さ5~10cm、幅3~7cmで矢じり形で、花は晩春から夏の終わりまで咲き、直径は3~7cm、花色は白(から青ざめた桃色)です。基本種の他、7亜種が報告されていますが、区別点はかならずしも明瞭ではないらしいです。ヒロハヒルガオは美しい白い花を咲かせるものの、旺盛な成長力で低木に巻きつくなど有害な雑草でもあります。種子は30年以上も発芽能力を維持し、数メートルもの地下茎で繁殖するので、根絶は困難であるとの事でした。ヒロハヒルガオは草地や道端で咲かせる純白の花が特徴のツル植物ですが、周りの植物に巻き付き地下茎を伸ばして繁殖するため、農業においては根絶が難しい雑草とみなされています。
昼に花を咲かせ、葉がヒルガオより広いことから広葉昼顔という和名がつきました。
ヒロハヒルガオは北半球のヨーロッパ、アジア、北西アフリカ、北アメリカ、南半球のオーストラリア、南米のアルゼンチンなどに広く分布するツル植物です。検索すると日本では北海道でのヒットが多く、冷温帯の植物なのでしょう。高さ数mになり、葉は長さ5~10cm、幅3~7cmで矢じり形で、花は晩春から夏の終わりまで咲き、直径は3~7cm、花色は白(から青ざめた桃色)です。基本種の他、7亜種が報告されていますが、区別点はかならずしも明瞭ではないらしいです。ヒロハヒルガオは美しい白い花を咲かせるものの、旺盛な成長力で低木に巻きつくなど有害な雑草でもあります。種子は30年以上も発芽能力を維持し、数メートルもの地下茎で繁殖するので、根絶は困難であるとの事でした。ヒロハヒルガオは草地や道端で咲かせる純白の花が特徴のツル植物ですが、周りの植物に巻き付き地下茎を伸ばして繁殖するため、農業においては根絶が難しい雑草とみなされています。
昼に花を咲かせ、葉がヒルガオより広いことから広葉昼顔という和名がつきました。
 オトメイヌゴマは多年草で、植物体全体に白毛が密生しています。茎は根茎から直立し、高さは約1 cmになり、4稜があって、稜に下向きの剛毛があります。花冠は濃紅紫色から淡紫色で、上唇の外側に毛が生え、下唇は3裂して中裂片の内側に白斑があります。ヨーロッパ中部から北部の原産で、ヨーロッパ全域、北アメリカ、オーストラリア、ニュージーランドに帰化しています。日本では、北海道名寄市や千葉県で知られています。種子がイヌゴマに似ていることが名前の由来です。30㎝~1m程度の高さに成長します。長楕円形で縁に鋸葉がある対生の葉を持ち、泡紫色の花を7月~9月に咲かせます。花の形状は唇形です。種子は黒褐色で小さく、表面に細かい突起があります。日本の気温に適応しているため、適切に水やりを行えば初心者でも育成することが可能です。オトメイヌゴマは美しい姿と特徴的な形状から、庭や公園の装飾で見ることが出来ます。また、古くから薬草としての効能がある事が知られています。
オトメイヌゴマは多年草で、植物体全体に白毛が密生しています。茎は根茎から直立し、高さは約1 cmになり、4稜があって、稜に下向きの剛毛があります。花冠は濃紅紫色から淡紫色で、上唇の外側に毛が生え、下唇は3裂して中裂片の内側に白斑があります。ヨーロッパ中部から北部の原産で、ヨーロッパ全域、北アメリカ、オーストラリア、ニュージーランドに帰化しています。日本では、北海道名寄市や千葉県で知られています。種子がイヌゴマに似ていることが名前の由来です。30㎝~1m程度の高さに成長します。長楕円形で縁に鋸葉がある対生の葉を持ち、泡紫色の花を7月~9月に咲かせます。花の形状は唇形です。種子は黒褐色で小さく、表面に細かい突起があります。日本の気温に適応しているため、適切に水やりを行えば初心者でも育成することが可能です。オトメイヌゴマは美しい姿と特徴的な形状から、庭や公園の装飾で見ることが出来ます。また、古くから薬草としての効能がある事が知られています。
 カッコウチョロギ(郭公草石蚕)は、すべてのレベルのガーデナーに適した簡単なお手入れで知られています。重要な管理ポイントには、良く水をけし、充分な日光から部分的な日陰を提供することが含まれます。カッコウチョロギ(郭公草石蚕)にとって特に重要な管理ポイントは、湿度が適度であることです。定期的な枯れ枝取りは、シーズン中の追加の開花を促すことができます。湿潤な草地に生育するカッコウチョロギは、自然な生息地の湿度レベルを模倣した環境で繁栄します。この多年草は耐干ばつ性がありますが、過剰な水はけを避けながら一貫した土壌の湿気を好みます。最適な水分維持のため、1週間に1度の水やりが必要です。屋内で育てる場合、カッコウチョロギは適度な湿度と良く排水された土壌を好み、健康な成長のために湿気保持と排水のバランスが重要です。抵抗力を持つハーブとして知られるカッコウチョロギは、土壌の湿度を保つためにマルチングの追加サポートを受けることでしばしば繁栄します。
カッコウチョロギ(郭公草石蚕)は、すべてのレベルのガーデナーに適した簡単なお手入れで知られています。重要な管理ポイントには、良く水をけし、充分な日光から部分的な日陰を提供することが含まれます。カッコウチョロギ(郭公草石蚕)にとって特に重要な管理ポイントは、湿度が適度であることです。定期的な枯れ枝取りは、シーズン中の追加の開花を促すことができます。湿潤な草地に生育するカッコウチョロギは、自然な生息地の湿度レベルを模倣した環境で繁栄します。この多年草は耐干ばつ性がありますが、過剰な水はけを避けながら一貫した土壌の湿気を好みます。最適な水分維持のため、1週間に1度の水やりが必要です。屋内で育てる場合、カッコウチョロギは適度な湿度と良く排水された土壌を好み、健康な成長のために湿気保持と排水のバランスが重要です。抵抗力を持つハーブとして知られるカッコウチョロギは、土壌の湿度を保つためにマルチングの追加サポートを受けることでしばしば繁栄します。
 ヒルザキツキミソウは、夕方~夜咲きの多いツキミソウの仲間ですが、本種は名前の通り明るい時間に花を開くので花壇にもよく用いられています。形が少し角ばった広釣鐘型で、ピンクと白の混じったような花を、初夏から長期間咲かせます。葉は比較的小さく、枝は直立しますが、それほど背丈は伸びません。いつの間にか増えるほど丈夫な花で、駐車場の脇のような荒れた場所でも育ちます。野生化して空き地などに咲いている姿もよく見かけます。必ず日当たり水はけのよい、やや乾燥した場所に植えます。適地に植えれば後は放任で育ちます。ジメジメした場所では美しく育ってくれません。やせ地のような肥料分が少ない場所で育ち、土が肥沃すぎると葉ばかりが茂って花が咲きにくくなります。移植を嫌うので、苗を植える場合は根鉢を崩さないようにします。株分けもできますが直まきのほうが楽に増やせます。洋風の庭に向きますが、和風や自然風の庭にも使えます。横に広がるように育つのが魅力なので、広めの鉢やプランターに単独で植えるか、 花壇に植えます。寄せ植えにはあまり適していません。性質は強健で野性的な印象がありますが、 花色や草姿は優しげなので他の花とも違和感なく合わせられます。境裁や沿路脇などに植えるとよく似合います。
ヒルザキツキミソウは、夕方~夜咲きの多いツキミソウの仲間ですが、本種は名前の通り明るい時間に花を開くので花壇にもよく用いられています。形が少し角ばった広釣鐘型で、ピンクと白の混じったような花を、初夏から長期間咲かせます。葉は比較的小さく、枝は直立しますが、それほど背丈は伸びません。いつの間にか増えるほど丈夫な花で、駐車場の脇のような荒れた場所でも育ちます。野生化して空き地などに咲いている姿もよく見かけます。必ず日当たり水はけのよい、やや乾燥した場所に植えます。適地に植えれば後は放任で育ちます。ジメジメした場所では美しく育ってくれません。やせ地のような肥料分が少ない場所で育ち、土が肥沃すぎると葉ばかりが茂って花が咲きにくくなります。移植を嫌うので、苗を植える場合は根鉢を崩さないようにします。株分けもできますが直まきのほうが楽に増やせます。洋風の庭に向きますが、和風や自然風の庭にも使えます。横に広がるように育つのが魅力なので、広めの鉢やプランターに単独で植えるか、 花壇に植えます。寄せ植えにはあまり適していません。性質は強健で野性的な印象がありますが、 花色や草姿は優しげなので他の花とも違和感なく合わせられます。境裁や沿路脇などに植えるとよく似合います。
 ヤマノイモ(山の芋)は、ヤマノイモ科ヤマノイモ属のつる性多年草で、地下茎が芋状に発達したものを食用とします。山に自生するものだけでなく、栽培されることもあります。一般的に「ヤマイモ」と呼ばれることもありますが、これはサトイモと区別するための総称でもあります。北海道〜沖縄の山野にふつうに生えています。葉は対生し、長さ5〜10cmの三角状披針形で基部は心形、先は長くとがっています。葉腋にしばしば珠芽(ムカゴ)がつき、雌雄異株です。雄花序は葉腋から直立し、白い小さな花を多数つけます。花被片は6個あり、雌花序は葉腋から垂れ下がり、白い花がまばらにつきます。雌花はやや小さく、子房に翼があります。成熟すると翼が大きく張りだし、さく果は下向きにつき、扁平な丸い翼が3個あります。種子は円形で周りに薄い翼があり、花期は7〜8月です。
ヤマノイモ(山の芋)は、ヤマノイモ科ヤマノイモ属のつる性多年草で、地下茎が芋状に発達したものを食用とします。山に自生するものだけでなく、栽培されることもあります。一般的に「ヤマイモ」と呼ばれることもありますが、これはサトイモと区別するための総称でもあります。北海道〜沖縄の山野にふつうに生えています。葉は対生し、長さ5〜10cmの三角状披針形で基部は心形、先は長くとがっています。葉腋にしばしば珠芽(ムカゴ)がつき、雌雄異株です。雄花序は葉腋から直立し、白い小さな花を多数つけます。花被片は6個あり、雌花序は葉腋から垂れ下がり、白い花がまばらにつきます。雌花はやや小さく、子房に翼があります。成熟すると翼が大きく張りだし、さく果は下向きにつき、扁平な丸い翼が3個あります。種子は円形で周りに薄い翼があり、花期は7〜8月です。
 コウリンタンポポは、鮮やかなオレンジ色の花を咲かせる多年草で、ヨーロッパ原産の外来種です。日本では主に北海道に帰化しており、道端や空き地などに群生しています。繁殖力が強く、匍匐茎で広がるため、他の植物を圧倒することがあります。コウリンタンポポは、ヨーロッパ原産の帰化植物で、繁殖力が強く、生態系への影響が懸念される外来種です。日本では明治中期に観賞用として持ち込まれ、野生化したとされています。外来生物法による規制は特にありませんが、生態系被害防止外来種リストに指定されています。コウリンタンポポは、道端や空き地、開けた草地などに生育し、タンポポに似た花を咲かせます。全体に黒い剛毛を密布し、地下茎を伸ばして増殖します。ロゼット状の葉を地表に広げるため、草刈りだけでは駆除が難しく、開花前の抜き取りが効果的です。コウリンタンポポは、在来の植物との競争や、希少な植物への影響が懸念されています。そのため、駆除活動が行われることもあります。例えば、裏磐梯では、環境省の「生態系被害防止外来種リスト」に指定されているコウリンタンポポの防除活動が行われています。
コウリンタンポポは、鮮やかなオレンジ色の花を咲かせる多年草で、ヨーロッパ原産の外来種です。日本では主に北海道に帰化しており、道端や空き地などに群生しています。繁殖力が強く、匍匐茎で広がるため、他の植物を圧倒することがあります。コウリンタンポポは、ヨーロッパ原産の帰化植物で、繁殖力が強く、生態系への影響が懸念される外来種です。日本では明治中期に観賞用として持ち込まれ、野生化したとされています。外来生物法による規制は特にありませんが、生態系被害防止外来種リストに指定されています。コウリンタンポポは、道端や空き地、開けた草地などに生育し、タンポポに似た花を咲かせます。全体に黒い剛毛を密布し、地下茎を伸ばして増殖します。ロゼット状の葉を地表に広げるため、草刈りだけでは駆除が難しく、開花前の抜き取りが効果的です。コウリンタンポポは、在来の植物との競争や、希少な植物への影響が懸念されています。そのため、駆除活動が行われることもあります。例えば、裏磐梯では、環境省の「生態系被害防止外来種リスト」に指定されているコウリンタンポポの防除活動が行われています。
 ガマは北海道から九州、および世界の温帯北半球から熱帯、オーストラリアなどに広く分布する多年生の草本です。沼沢地やため池の湖岸、放棄水田などに広く分布しています。大形の抽水(ちゅうすい)植物であり、高さ2m程になりまか。地中に柔らかくて通気組織の発達した太い地下茎を発達させ、群落を形成します。初夏に花茎を形成し、上部に雄花群を、それに接して雌花群を付けます。雄花からは大量の花粉が形成され、飛散する。雌花は成熟するとより太く、褐色になるので、まるで祭りで売っているフランクフルトソーセージのようになります。ガマの生産する花粉の量はすさまじく、これを集めたものを蒲黄(ほおう)と呼び、漢方では利尿剤や止血剤として利用すると言います。葉は柔組織が発達して柔らかくしなやかで、駕籠やむしろなどに細工・加工されます。ガマの加工品はしっとりと柔らかくて手触りがよいです。秋になると穂は綿状になって崩れ、風に乗って飛散します。昔はこの綿毛を集めて布団の綿に使用したり、火をおこす際の火口に利用したこともあるそうです。穂をほぐしてみると劇的に膨らみ、布団の綿として使えそうなホカホカ状態になり、稲葉の白兎で有名な蒲の穂綿です。
ガマは北海道から九州、および世界の温帯北半球から熱帯、オーストラリアなどに広く分布する多年生の草本です。沼沢地やため池の湖岸、放棄水田などに広く分布しています。大形の抽水(ちゅうすい)植物であり、高さ2m程になりまか。地中に柔らかくて通気組織の発達した太い地下茎を発達させ、群落を形成します。初夏に花茎を形成し、上部に雄花群を、それに接して雌花群を付けます。雄花からは大量の花粉が形成され、飛散する。雌花は成熟するとより太く、褐色になるので、まるで祭りで売っているフランクフルトソーセージのようになります。ガマの生産する花粉の量はすさまじく、これを集めたものを蒲黄(ほおう)と呼び、漢方では利尿剤や止血剤として利用すると言います。葉は柔組織が発達して柔らかくしなやかで、駕籠やむしろなどに細工・加工されます。ガマの加工品はしっとりと柔らかくて手触りがよいです。秋になると穂は綿状になって崩れ、風に乗って飛散します。昔はこの綿毛を集めて布団の綿に使用したり、火をおこす際の火口に利用したこともあるそうです。穂をほぐしてみると劇的に膨らみ、布団の綿として使えそうなホカホカ状態になり、稲葉の白兎で有名な蒲の穂綿です。
 カモジグサは、日本各地、朝鮮・中国にも分布する多年生の草本で、路傍や空き地などに普通に生育しています。秋から生育を始め、初夏に花穂を形成して目立つようになります。花は青紫色を帯びており、黒っぽい頴が伸びているものを採取して束ね、付け髪(かもじ)に例えて遊んだことに由来すると言います。同じ属の植物によく似たアオカモジグサがあり、混生していることもあります。カモジグサの花穂の中軸はアオカモジグサよりも細いのか、より曲がって垂れ下がります。特に種子が稔ってくるとその傾向は顕著になります。カモジグサは平地や草地に普通に見られる多年草です。植物体は大きいもので約1mにもなり、先端の花序の部分が垂れ下がるのが特徴です。この花序は紫色ですが,青っぽいものは「アオカモジグサ」とよばれて区別されています。しかし色は中間的な形質を持つものが多産するのでまぎらわしいです。この場合,小穂がまばらについているのがカモジグサです。
カモジグサは、日本各地、朝鮮・中国にも分布する多年生の草本で、路傍や空き地などに普通に生育しています。秋から生育を始め、初夏に花穂を形成して目立つようになります。花は青紫色を帯びており、黒っぽい頴が伸びているものを採取して束ね、付け髪(かもじ)に例えて遊んだことに由来すると言います。同じ属の植物によく似たアオカモジグサがあり、混生していることもあります。カモジグサの花穂の中軸はアオカモジグサよりも細いのか、より曲がって垂れ下がります。特に種子が稔ってくるとその傾向は顕著になります。カモジグサは平地や草地に普通に見られる多年草です。植物体は大きいもので約1mにもなり、先端の花序の部分が垂れ下がるのが特徴です。この花序は紫色ですが,青っぽいものは「アオカモジグサ」とよばれて区別されています。しかし色は中間的な形質を持つものが多産するのでまぎらわしいです。この場合,小穂がまばらについているのがカモジグサです。
 荒げ川原岳は、以前はサルノコシカケ化とされていましたが、他行金貨又は玉猪苓岳かともいわれています。倒木に繁殖し、カイガラタケ同様、漢方では癌に効くと言われるキノコ類の一つです。薬用になるので毒ではありませんが、苦く硬いので食用にはなりません。カワラタケは、一般的に食用には適さないとされています。非常に硬い肉質で、食べても美味しくないため、食用不適とされています。また、一部では免疫力を高める物質を含むとして薬用キノコとして扱われることもありますが、毒性成分も含まれている可能性があるため注意が必要です。カワラタケの培養菌糸体は抗がん剤として使用されているクレスチンの原料 で、これは医薬品としての実績があります。 カワラタケの子実体は高血圧予防や強壮、健 胃、美肌などに関心がある方向けの健康食品として、その機能性が注目されています。アラゲカワラタケは、生育する環境によって色の違いを観察することができます。傘の表面は短い毛で覆われていて、乾燥しているときは光が反射して光沢があるように見えます。 裏側は管孔になっていて、未熟なものでは白色をしていますが成長すると次第にクリーム色、褐色へと変化していきます。
荒げ川原岳は、以前はサルノコシカケ化とされていましたが、他行金貨又は玉猪苓岳かともいわれています。倒木に繁殖し、カイガラタケ同様、漢方では癌に効くと言われるキノコ類の一つです。薬用になるので毒ではありませんが、苦く硬いので食用にはなりません。カワラタケは、一般的に食用には適さないとされています。非常に硬い肉質で、食べても美味しくないため、食用不適とされています。また、一部では免疫力を高める物質を含むとして薬用キノコとして扱われることもありますが、毒性成分も含まれている可能性があるため注意が必要です。カワラタケの培養菌糸体は抗がん剤として使用されているクレスチンの原料 で、これは医薬品としての実績があります。 カワラタケの子実体は高血圧予防や強壮、健 胃、美肌などに関心がある方向けの健康食品として、その機能性が注目されています。アラゲカワラタケは、生育する環境によって色の違いを観察することができます。傘の表面は短い毛で覆われていて、乾燥しているときは光が反射して光沢があるように見えます。 裏側は管孔になっていて、未熟なものでは白色をしていますが成長すると次第にクリーム色、褐色へと変化していきます。
 チシマイチゴは小低木の多年草植物で、樹高は10~25cmです。縁がギザギザした葉は三出複葉(1枚の葉が3つの葉に分かれたような形のこと)で緑色をしています。チシマイチゴは虫媒、自家受粉の両方です。赤、もしくは赤紫の花は個別につき、開花時期は6から7月にかけてです。果実は濃い赤色、緑がかったもの、茶色、または黒みがあるものがあり味と香りの良い石果です。実はしっかりとくっついています。チシマイチゴはフィンランド全国に自生していますが、一般的な自生範囲は中部のクオピオからケミにかけてです。小さい森や土壌の豊かな湿地帯、原野、水際、溝や小川また小道の脇、伐採された土地や畑の枕地や年数の経った牧草地などに自生します。以前は放牧や焼き畑などの影響はあまり見られませんでしたが、近年の機械による土地や森林の手入れにより自生場所が少なくなって来ている等の悪影響があります。
チシマイチゴは小低木の多年草植物で、樹高は10~25cmです。縁がギザギザした葉は三出複葉(1枚の葉が3つの葉に分かれたような形のこと)で緑色をしています。チシマイチゴは虫媒、自家受粉の両方です。赤、もしくは赤紫の花は個別につき、開花時期は6から7月にかけてです。果実は濃い赤色、緑がかったもの、茶色、または黒みがあるものがあり味と香りの良い石果です。実はしっかりとくっついています。チシマイチゴはフィンランド全国に自生していますが、一般的な自生範囲は中部のクオピオからケミにかけてです。小さい森や土壌の豊かな湿地帯、原野、水際、溝や小川また小道の脇、伐採された土地や畑の枕地や年数の経った牧草地などに自生します。以前は放牧や焼き畑などの影響はあまり見られませんでしたが、近年の機械による土地や森林の手入れにより自生場所が少なくなって来ている等の悪影響があります。
 日本では地方によって様々な別の呼び名があり、ヨシノユリ(吉野百合、芳野百合)、エイザンユリ(叡山百合)、ホウライジユリ(蓬莱寺百合、鳳来寺百合)、リョウリユリなどともよばれていて、各産地に因んで名付けられています。。日本特産のユリで、北陸地方を除く本州の近畿地方以北の山地に分布し、山地、山野の林縁や草地に自生しています。北海道や九州には栽培していたものが野生化したものが見られ、観賞用に多く栽培もされています。日当たりのよい原野、丘陵などに生えていて、夏の里山の植林地などの木漏れ日が当たるところでは、ひときわ目立つ白い花を咲かせているヤマユリが見かけられます。
日本では地方によって様々な別の呼び名があり、ヨシノユリ(吉野百合、芳野百合)、エイザンユリ(叡山百合)、ホウライジユリ(蓬莱寺百合、鳳来寺百合)、リョウリユリなどともよばれていて、各産地に因んで名付けられています。。日本特産のユリで、北陸地方を除く本州の近畿地方以北の山地に分布し、山地、山野の林縁や草地に自生しています。北海道や九州には栽培していたものが野生化したものが見られ、観賞用に多く栽培もされています。日当たりのよい原野、丘陵などに生えていて、夏の里山の植林地などの木漏れ日が当たるところでは、ひときわ目立つ白い花を咲かせているヤマユリが見かけられます。
 ヒヨドリバナは、北海道から九州の各地に分布するキク科ヒヨドリバナ属の多年草です。日本の在来種であり、山野の草地や林縁に自生し、夏から秋にかけてフジバカマに似た花を多数咲かせます。日本以外では中国や朝鮮半島、フィリピンなどに分布しています。ヒヨドリバナという名前は、ヒヨドリが鳴く頃に咲くこと、あるいは花殻に生じる綿毛(冠毛)がヒヨドリの冠毛に似ることによります。花は頭状花と呼ばれるタイプの小さなもので、枝分かれの多い花茎の先に散在します。筒状の小花が五つ集まって一まとまりになり、花色は普通、白色ですが、土壌によっては淡い紫を帯びます。花から飛び出すのは雌しべで、先端が二つに裂けています。ヒヨドリバナの葉は長さ6~18センチほどで、先端が尾状に少し尖った長楕円形で、茎から対になって生じます。両面に縮れた毛があり、葉の裏には腺点と呼ばれるものがたくさんあります。
ヒヨドリバナは、北海道から九州の各地に分布するキク科ヒヨドリバナ属の多年草です。日本の在来種であり、山野の草地や林縁に自生し、夏から秋にかけてフジバカマに似た花を多数咲かせます。日本以外では中国や朝鮮半島、フィリピンなどに分布しています。ヒヨドリバナという名前は、ヒヨドリが鳴く頃に咲くこと、あるいは花殻に生じる綿毛(冠毛)がヒヨドリの冠毛に似ることによります。花は頭状花と呼ばれるタイプの小さなもので、枝分かれの多い花茎の先に散在します。筒状の小花が五つ集まって一まとまりになり、花色は普通、白色ですが、土壌によっては淡い紫を帯びます。花から飛び出すのは雌しべで、先端が二つに裂けています。ヒヨドリバナの葉は長さ6~18センチほどで、先端が尾状に少し尖った長楕円形で、茎から対になって生じます。両面に縮れた毛があり、葉の裏には腺点と呼ばれるものがたくさんあります。
 タイワンハチジョウナは、キク科ノゲシ属の一種です。ヨーロッパ原産で、外来種として世界的に分布しています。道端や荒地で見られれ、背丈は高く、80~150cmほどにもなります。ノゲシ同様に茎は直立し、頭頂部で分枝し数個の頭花をつけます。葉は比較的下部につき、茎を抱きます。日本ではタイワンハチジョウナが古くから沖縄に帰化していることが知られており、最近は各地で見られるようになったといわれています。開花は5月から開始した。6月中旬~7月上旬に花が一度終わり、新しい花茎が出て再び開花し、秋まで花が続きます。茎は無毛、葉は下部に集まってつき、長さ9~31㎝、幅1.5~10㎝、羽状に分裂し、葉の縁には刺状の鋸歯があり、葉の基部は茎を抱く。葉裏は粉白色です。茎の上部には苞のような小さな葉があり、春の羽状に分裂する葉は春の花が終わる頃には枯れ、夏の葉は分裂が少なく、ほぼ全縁です。
タイワンハチジョウナは、キク科ノゲシ属の一種です。ヨーロッパ原産で、外来種として世界的に分布しています。道端や荒地で見られれ、背丈は高く、80~150cmほどにもなります。ノゲシ同様に茎は直立し、頭頂部で分枝し数個の頭花をつけます。葉は比較的下部につき、茎を抱きます。日本ではタイワンハチジョウナが古くから沖縄に帰化していることが知られており、最近は各地で見られるようになったといわれています。開花は5月から開始した。6月中旬~7月上旬に花が一度終わり、新しい花茎が出て再び開花し、秋まで花が続きます。茎は無毛、葉は下部に集まってつき、長さ9~31㎝、幅1.5~10㎝、羽状に分裂し、葉の縁には刺状の鋸歯があり、葉の基部は茎を抱く。葉裏は粉白色です。茎の上部には苞のような小さな葉があり、春の羽状に分裂する葉は春の花が終わる頃には枯れ、夏の葉は分裂が少なく、ほぼ全縁です。
 ホテイアオイは、単子葉植物ミズアオイ科に属する水草です。南アメリカ原産で、水面に浮かんで生育します。花が青く美しいので観賞用に栽培されます。湖沼や流れの緩やかな川などの水面に浮かんで生育する水草で、葉は水面から立ち上がります。葉そのものは丸っぽく、艶があります。変わった特徴は、葉柄が丸く膨らんで浮き袋の役目をしていることで、浮き袋の半ばまでが水の中にあります。日本では、この浮き袋のような丸い形の葉柄を布袋の膨らんだ腹に見立てて「ホテイアオイ(布袋のような形をしているアオイ)」と呼ばれるようになりました。茎はごく短く、葉はロゼット状につきます。つまり、タンポポのような草が根元まで水に浸かっている形です。水中には根が伸びます。根はひげ根状のものがバラバラと水中に広がり、それぞれの根からはたくさんの根毛が出るので、試験管洗いのブラシのようです。これは重りとして機能して、浮袋状の葉柄など空隙に富んだ水上部とバランスを取って水面での姿勢を保っています。
ホテイアオイは、単子葉植物ミズアオイ科に属する水草です。南アメリカ原産で、水面に浮かんで生育します。花が青く美しいので観賞用に栽培されます。湖沼や流れの緩やかな川などの水面に浮かんで生育する水草で、葉は水面から立ち上がります。葉そのものは丸っぽく、艶があります。変わった特徴は、葉柄が丸く膨らんで浮き袋の役目をしていることで、浮き袋の半ばまでが水の中にあります。日本では、この浮き袋のような丸い形の葉柄を布袋の膨らんだ腹に見立てて「ホテイアオイ(布袋のような形をしているアオイ)」と呼ばれるようになりました。茎はごく短く、葉はロゼット状につきます。つまり、タンポポのような草が根元まで水に浸かっている形です。水中には根が伸びます。根はひげ根状のものがバラバラと水中に広がり、それぞれの根からはたくさんの根毛が出るので、試験管洗いのブラシのようです。これは重りとして機能して、浮袋状の葉柄など空隙に富んだ水上部とバランスを取って水面での姿勢を保っています。
 オオマツヨイグサはアカバナ科マツヨイグサ属の二年草です。北米大陸の原種をもとに、ヨーロッパで作り出された園芸種とも云われています。日本では帰化植物の一つとされ、誤ってツキミソウとも呼ばれてます。和名はマツヨイグサよりも大形の意味です。二年草または短命な多年草で、直立して高さは50~150cmになります。茎は全体に硬い毛が生え、毛の基部が膨れて暗赤色の凸点になります。根性葉は地面に張り付いてロゼットをつくり、柄がついて葉先が円くなりますが、茎上の葉は無柄で葉先が尖っています。茎の葉は狭楕円形から披針形で、長さ5~15 cm、幅2.5~4 cm位です。ともに縁にはまばらに鋸歯があり、葉面は凹凸があって中央脈は白色を帯びています。花期は夏(7~10月)で、花は径8cm内外、無柄で子房下位、自家和合性があり、夕方に咲いて翌朝にしぼみます。黄色い花弁は4枚で、広倒卵形で長さよりも幅のほうが大きいです。花がしぼむと黄色から赤橙色に変わります。
オオマツヨイグサはアカバナ科マツヨイグサ属の二年草です。北米大陸の原種をもとに、ヨーロッパで作り出された園芸種とも云われています。日本では帰化植物の一つとされ、誤ってツキミソウとも呼ばれてます。和名はマツヨイグサよりも大形の意味です。二年草または短命な多年草で、直立して高さは50~150cmになります。茎は全体に硬い毛が生え、毛の基部が膨れて暗赤色の凸点になります。根性葉は地面に張り付いてロゼットをつくり、柄がついて葉先が円くなりますが、茎上の葉は無柄で葉先が尖っています。茎の葉は狭楕円形から披針形で、長さ5~15 cm、幅2.5~4 cm位です。ともに縁にはまばらに鋸歯があり、葉面は凹凸があって中央脈は白色を帯びています。花期は夏(7~10月)で、花は径8cm内外、無柄で子房下位、自家和合性があり、夕方に咲いて翌朝にしぼみます。黄色い花弁は4枚で、広倒卵形で長さよりも幅のほうが大きいです。花がしぼむと黄色から赤橙色に変わります。
 ハマスゲは、世界の強害雑草のトップにあげられている雑草で、熱帯や亜熱帯地方の畑地に広く分布しています。わが国では東北以南の海岸の砂地、河原、樹園地、芝地、農道などに分布していますが、暖地や沖縄では畑地にも発生します。刈り取りに耐性を示すので、ゴルフ場などの芝地で問題となっています。春に気温が10~15℃になると塊茎から萌芽してきますが、萌芽の適温は30~35℃であり、生育には高温と光の強い条件を好む植物です。塊茎は土中0~6cm層に多く形成されますが、地下30cmからも萌芽できます。地上部の茎葉は刈り取りに対して強い耐性を示します。自然光下で生育した場合、毎週続けて9回地上部を切除しても、なお容易に茎葉が再生するばかりか、植付け21日後の4回目の切除時には新塊茎の形成が認められています。しかし、55%程度の遮光条件下では、毎週7回の切除で茎葉の再生は停止し、萌芽力を失ったとされます。
ハマスゲは、世界の強害雑草のトップにあげられている雑草で、熱帯や亜熱帯地方の畑地に広く分布しています。わが国では東北以南の海岸の砂地、河原、樹園地、芝地、農道などに分布していますが、暖地や沖縄では畑地にも発生します。刈り取りに耐性を示すので、ゴルフ場などの芝地で問題となっています。春に気温が10~15℃になると塊茎から萌芽してきますが、萌芽の適温は30~35℃であり、生育には高温と光の強い条件を好む植物です。塊茎は土中0~6cm層に多く形成されますが、地下30cmからも萌芽できます。地上部の茎葉は刈り取りに対して強い耐性を示します。自然光下で生育した場合、毎週続けて9回地上部を切除しても、なお容易に茎葉が再生するばかりか、植付け21日後の4回目の切除時には新塊茎の形成が認められています。しかし、55%程度の遮光条件下では、毎週7回の切除で茎葉の再生は停止し、萌芽力を失ったとされます。
 イヌゴマは日本全国の湿地に生育する高さ40~70cmほどになる多年草です。湿地とは言っても、サギソウなどの生えるような貧栄養な湿地よりも、休耕田や畦溝、河川敷などやや栄養分の豊かな場所を好むようです。茎はシソ科の特徴である四角形をしており、稜(角)の上、葉の下面の主脈上には下向きの小さなトゲがあって触るとざらつきます。葉は対生(おなじところに対になって付く)で、長さ4~8cmの細長い三角形、茎の下部の葉にははっきりした柄がありますが、茎の上部の葉柄は短く、茎を抱いているように見えます。地中には長い地下茎が伸び、節から芽が出て広がります。花は7~8月、茎の上部に淡紅色の花が輪生状に多数咲きます。花が終わると5つに裂けた萼(がく)の奥に、黒い種子が3~4個できます。
イヌゴマは日本全国の湿地に生育する高さ40~70cmほどになる多年草です。湿地とは言っても、サギソウなどの生えるような貧栄養な湿地よりも、休耕田や畦溝、河川敷などやや栄養分の豊かな場所を好むようです。茎はシソ科の特徴である四角形をしており、稜(角)の上、葉の下面の主脈上には下向きの小さなトゲがあって触るとざらつきます。葉は対生(おなじところに対になって付く)で、長さ4~8cmの細長い三角形、茎の下部の葉にははっきりした柄がありますが、茎の上部の葉柄は短く、茎を抱いているように見えます。地中には長い地下茎が伸び、節から芽が出て広がります。花は7~8月、茎の上部に淡紅色の花が輪生状に多数咲きます。花が終わると5つに裂けた萼(がく)の奥に、黒い種子が3~4個できます。
 アメリカオニアザミは、ヨーロッパ原産のキク科の植物で、生態系被害防止外来種に指定されています。日本では、7月から10月頃に紅紫色の花を咲かせ、繁殖力が非常に強く、在来の植物の生育場所を奪うなどの影響が懸念されています。また、葉や茎に鋭いトゲを持つため、人やペットを傷つける危険もあります。アメリカオニアザミは、名前に「アメリカ」とありますが、ヨーロッパ原産のキク科アザミ属の多年草で、北アメリカから輸入された穀物や牧草に混入して持ち込まれました。茎の高さは0.5メートルから1.5メートル、大きい個体は2メートルにもなり、夏から秋にかけて紅紫色の花を咲かせます。種にはタンポポのような綿毛がついており、風に乗って拡散します。葉や茎にはとても鋭いトゲがあるため、人や動物にケガをさせることがあり、動物もアメリカオニアザミを捕食することはありません。また、アメリカオニアザミは大変繁殖力が強く、その土地にあった植物(在来種)の生育場所を占領し、駆逐してしまう恐れがあり、環境省により生態系被害防止外来種に指定されています。
アメリカオニアザミは、ヨーロッパ原産のキク科の植物で、生態系被害防止外来種に指定されています。日本では、7月から10月頃に紅紫色の花を咲かせ、繁殖力が非常に強く、在来の植物の生育場所を奪うなどの影響が懸念されています。また、葉や茎に鋭いトゲを持つため、人やペットを傷つける危険もあります。アメリカオニアザミは、名前に「アメリカ」とありますが、ヨーロッパ原産のキク科アザミ属の多年草で、北アメリカから輸入された穀物や牧草に混入して持ち込まれました。茎の高さは0.5メートルから1.5メートル、大きい個体は2メートルにもなり、夏から秋にかけて紅紫色の花を咲かせます。種にはタンポポのような綿毛がついており、風に乗って拡散します。葉や茎にはとても鋭いトゲがあるため、人や動物にケガをさせることがあり、動物もアメリカオニアザミを捕食することはありません。また、アメリカオニアザミは大変繁殖力が強く、その土地にあった植物(在来種)の生育場所を占領し、駆逐してしまう恐れがあり、環境省により生態系被害防止外来種に指定されています。