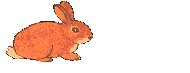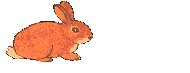
 ヨシは、河川敷や池・沼のまわりなど、水辺にごく普通に生えています。群生することが多く、ヨシ原と呼ばれる環境をつくりだしています。ヨシ原はいろんな生きものたちの生活の場として、重要な役割を担っています。地下茎をどんどん伸ばして、旺盛に繁殖していきます。洪水や天地返しなどで土がかき混ぜられても、ちぎれた地下茎からすぐに再生できる能力を持っています。夏の終わりごろから穂を出しはじめます。この穂は晩秋に成熟し、綿毛つきのタネをたくさん飛ばします。冬になると地上の茎は枯れますが、これを利用して作ったすだれを葦簀(よしず)と言います。「スルメ」を「アタリメ」と言うように、縁起の悪い言葉を連想させるものを、縁起の良いものに呼びかえることがあります。
じつはヨシもこの手の呼びかえが定着したものです。ヨシはもともとアシと呼ばれていました。その語源には「青し」「桿(ハシ)」など、いくつかの説があります。いずれにせよ音が「悪し」を連想させるため、それを嫌って対義語のヨシ(良し)がをあてられました。
ヨシは、河川敷や池・沼のまわりなど、水辺にごく普通に生えています。群生することが多く、ヨシ原と呼ばれる環境をつくりだしています。ヨシ原はいろんな生きものたちの生活の場として、重要な役割を担っています。地下茎をどんどん伸ばして、旺盛に繁殖していきます。洪水や天地返しなどで土がかき混ぜられても、ちぎれた地下茎からすぐに再生できる能力を持っています。夏の終わりごろから穂を出しはじめます。この穂は晩秋に成熟し、綿毛つきのタネをたくさん飛ばします。冬になると地上の茎は枯れますが、これを利用して作ったすだれを葦簀(よしず)と言います。「スルメ」を「アタリメ」と言うように、縁起の悪い言葉を連想させるものを、縁起の良いものに呼びかえることがあります。
じつはヨシもこの手の呼びかえが定着したものです。ヨシはもともとアシと呼ばれていました。その語源には「青し」「桿(ハシ)」など、いくつかの説があります。いずれにせよ音が「悪し」を連想させるため、それを嫌って対義語のヨシ(良し)がをあてられました。
 セイヨウヒイラギは。ヨーロッパ中南部、西アジア及び北アフリカを原産とする常緑樹です。赤い実と濃緑の葉のコントラストが美しく、花の少ないクリスマス期を演出するリースなどに使うため、欧米では古くから庭木として栽培され、園芸品種も多いです。セイヨウヒイラギがクリスマスのデコレーションに使われるのは、イタリアの古い習慣で農業の神(サツヌルス)を祭る際、本種の葉を用いたことに遠因があるとされます。葉のトゲには悪魔を払う力があり、葉を飾ると翌年に幸運が訪れるとされ、日本におけるサカキやヒイラギに通じるものがあります。葉の形はヒイラギと同様ですが、セイヨウヒイラギの方がやや大く、葉は厚い革質で表面には艶があり、若い葉には三角形に近いトゲ状のギザギザがありますが、ヒイラギと同様に老木ではトゲのない葉もあります。
セイヨウヒイラギは。ヨーロッパ中南部、西アジア及び北アフリカを原産とする常緑樹です。赤い実と濃緑の葉のコントラストが美しく、花の少ないクリスマス期を演出するリースなどに使うため、欧米では古くから庭木として栽培され、園芸品種も多いです。セイヨウヒイラギがクリスマスのデコレーションに使われるのは、イタリアの古い習慣で農業の神(サツヌルス)を祭る際、本種の葉を用いたことに遠因があるとされます。葉のトゲには悪魔を払う力があり、葉を飾ると翌年に幸運が訪れるとされ、日本におけるサカキやヒイラギに通じるものがあります。葉の形はヒイラギと同様ですが、セイヨウヒイラギの方がやや大く、葉は厚い革質で表面には艶があり、若い葉には三角形に近いトゲ状のギザギザがありますが、ヒイラギと同様に老木ではトゲのない葉もあります。
 タンチョウソウは中国東北部から朝鮮半島の低山から山地に分布し、川岸の岩上や川沿いの岩壁に生えます。春、地面を這う頑丈な根茎から、ヤツデやモミジを思わせるような7裂に切れ込んだ葉を数枚広げます。ただし、個体や栄養状態によっては5裂や9裂のものもあります。花は、葉が展開する直前かほぼ同時に咲きます。花茎はまっすぐに伸び、上のほうで枝分かれして、花径5mmほどの白い花を多数咲かせます。白い萼と白い花弁が重なり合って、花びらが10枚あるように見えます。秋の終わりには葉が枯れて休眠します。タンチョウソウ(ユキノシタ科)
多年草 花期3~4月花は径5㎜ほどの白色の5弁花(時に6弁花)で白い萼と花弁が重なって10弁(時に12弁)に見えますが外花披が萼で内花披が花弁です。中央に雌しべが1個で柱頭は2裂
その周りに雄しべが5、6本ほど並んでいるそうです。
タンチョウソウは中国東北部から朝鮮半島の低山から山地に分布し、川岸の岩上や川沿いの岩壁に生えます。春、地面を這う頑丈な根茎から、ヤツデやモミジを思わせるような7裂に切れ込んだ葉を数枚広げます。ただし、個体や栄養状態によっては5裂や9裂のものもあります。花は、葉が展開する直前かほぼ同時に咲きます。花茎はまっすぐに伸び、上のほうで枝分かれして、花径5mmほどの白い花を多数咲かせます。白い萼と白い花弁が重なり合って、花びらが10枚あるように見えます。秋の終わりには葉が枯れて休眠します。タンチョウソウ(ユキノシタ科)
多年草 花期3~4月花は径5㎜ほどの白色の5弁花(時に6弁花)で白い萼と花弁が重なって10弁(時に12弁)に見えますが外花披が萼で内花披が花弁です。中央に雌しべが1個で柱頭は2裂
その周りに雄しべが5、6本ほど並んでいるそうです。
 チョウセンシラベは、朝鮮半島の南およそ100kmに浮かぶ韓国の済州島には、同国の最高峰、漢拏山があります。その高地にはチョウセンシラベというモミの木の小規模な群落があり、「クリスマスツリーの森」と呼ばれています。この常緑の針葉樹は、世界中の家庭で冬に飾られるヨーロッパモミやオウシュウトウヒなどによく似ていて、韓国の人々はクリスマスツリーにしています。チョウセンシラベは韓国にしか自生しておらず、特に南部に多いです。最大の群落があるのが済州島です。チョウセンシラベはモミ属の樹木としては小さく、他の種類のモミが樹高90m以上に達することもあるのに対して、9~18m程度にしかならなりません。また、主に亜高山帯で生育するため成長が遅く、成熟までに約30年を要し、わずか樹高1mほどで球果をつけます。
チョウセンシラベは、朝鮮半島の南およそ100kmに浮かぶ韓国の済州島には、同国の最高峰、漢拏山があります。その高地にはチョウセンシラベというモミの木の小規模な群落があり、「クリスマスツリーの森」と呼ばれています。この常緑の針葉樹は、世界中の家庭で冬に飾られるヨーロッパモミやオウシュウトウヒなどによく似ていて、韓国の人々はクリスマスツリーにしています。チョウセンシラベは韓国にしか自生しておらず、特に南部に多いです。最大の群落があるのが済州島です。チョウセンシラベはモミ属の樹木としては小さく、他の種類のモミが樹高90m以上に達することもあるのに対して、9~18m程度にしかならなりません。また、主に亜高山帯で生育するため成長が遅く、成熟までに約30年を要し、わずか樹高1mほどで球果をつけます。
 チョウノスケソウは北海道から本州中部以北の高山の礫地に生える小型の植物です。一見、草のように見えますが、木質化した枝を四方に這わせて伸びる高山矮小常緑低木です。雪解けとともに、しわが多い楕円形の新葉を広げます。葉の展開が終わるころ、太い芽では先端から蕾を出して、花弁が8枚の白い花を咲かせます。花後には白く長い綿毛をつけた果実を実らせます。やがて、少し紅葉して雪の下で休眠に入ります。生育中、茎は四方にほふくして株を広げていきます。花は自生地では7月から8月に咲きますが、栽培下の開花は5月中旬から6月下旬です。高山植物愛好家には欠かせない植物ですが、なかなかの難物で上級者向きの植物です。
チョウノスケソウは北海道から本州中部以北の高山の礫地に生える小型の植物です。一見、草のように見えますが、木質化した枝を四方に這わせて伸びる高山矮小常緑低木です。雪解けとともに、しわが多い楕円形の新葉を広げます。葉の展開が終わるころ、太い芽では先端から蕾を出して、花弁が8枚の白い花を咲かせます。花後には白く長い綿毛をつけた果実を実らせます。やがて、少し紅葉して雪の下で休眠に入ります。生育中、茎は四方にほふくして株を広げていきます。花は自生地では7月から8月に咲きますが、栽培下の開花は5月中旬から6月下旬です。高山植物愛好家には欠かせない植物ですが、なかなかの難物で上級者向きの植物です。
 猛暑が去り秋支度に向かう山野は、ツリガネニンジンの鈴なりの薄紫色の花で彩られます。ツリガネニンジンは北海道から本州、四国、琉球諸島まで広く分布する多年草です。花は釣り鐘形で下向きに咲き、花柱が花冠からわずかに突き出ています。直立した茎を折ると白い乳液が出るのが特徴です。若芽は山菜料理の横綱格と言われるほど美味しいそうです。和名は、その釣鐘型の花と、漢方薬の朝鮮人参の太い根に似ているところから名付けられたと言われています。ツリガネニンジン属の植物は、中国で一般に「沙参」と呼ばれ、水辺の砂地(沙地)が生育に適することから、この名が付いたと言われています。中国名の「沙参」は、厳密にはトウシャジンを指しています。夏の終わり頃に根を掘り取り、日干ししたものが生薬「シャジン」です。その煎じ液を去痰、鎮咳を目的に服用します。苦みやえぐみがあるので、シャジンの半量ほどの甘草や茶さじ1杯の砂糖を加えると良いとされています。
猛暑が去り秋支度に向かう山野は、ツリガネニンジンの鈴なりの薄紫色の花で彩られます。ツリガネニンジンは北海道から本州、四国、琉球諸島まで広く分布する多年草です。花は釣り鐘形で下向きに咲き、花柱が花冠からわずかに突き出ています。直立した茎を折ると白い乳液が出るのが特徴です。若芽は山菜料理の横綱格と言われるほど美味しいそうです。和名は、その釣鐘型の花と、漢方薬の朝鮮人参の太い根に似ているところから名付けられたと言われています。ツリガネニンジン属の植物は、中国で一般に「沙参」と呼ばれ、水辺の砂地(沙地)が生育に適することから、この名が付いたと言われています。中国名の「沙参」は、厳密にはトウシャジンを指しています。夏の終わり頃に根を掘り取り、日干ししたものが生薬「シャジン」です。その煎じ液を去痰、鎮咳を目的に服用します。苦みやえぐみがあるので、シャジンの半量ほどの甘草や茶さじ1杯の砂糖を加えると良いとされています。
 ナツシロギク は、伝統的な薬用ハーブであり、ヨーロッパなどで古くから庭に植えられてきた植物です。装飾に使用されることもあります。成長すると柑橘系の香りをもつ葉に覆われた高さ46センチメートルほどの小さなブッシュとなり、デイジーに似た花をつけます。広がるのがとても早く、数年で広いエリアを覆ってしまいます。ナツシロギクはユーラシア大陸のバルカン半島やアナトリア半島やコーカサス地方辺りが原産です。しかし世界中で栽培されるようになったため、今ではヨーロッパ、北アメリカ、チリなどでも見られます。薬草として使われだしたのがいつ頃からなのかは分かっていませんが、ギリシャのディオスコリデスが抗炎症剤として記したのが、文書に記載された最初の事例です。
ナツシロギク は、伝統的な薬用ハーブであり、ヨーロッパなどで古くから庭に植えられてきた植物です。装飾に使用されることもあります。成長すると柑橘系の香りをもつ葉に覆われた高さ46センチメートルほどの小さなブッシュとなり、デイジーに似た花をつけます。広がるのがとても早く、数年で広いエリアを覆ってしまいます。ナツシロギクはユーラシア大陸のバルカン半島やアナトリア半島やコーカサス地方辺りが原産です。しかし世界中で栽培されるようになったため、今ではヨーロッパ、北アメリカ、チリなどでも見られます。薬草として使われだしたのがいつ頃からなのかは分かっていませんが、ギリシャのディオスコリデスが抗炎症剤として記したのが、文書に記載された最初の事例です。
 ナツノハナワラビ は、ハナヤスリ科に属する大葉シダ植物の1つで、長い共通柄の先に羽状複葉の栄養葉同じく羽状に枝を出す胞子葉をセットにつけます。胞子葉を初夏に出す、夏緑性の真嚢シダ類です。本種はハナワラビ類の特徴を持ちますが、日本の他の種と較べると担葉体が長くて栄養葉を地表から離れた場所に出し、夏緑性であることなどで独特です。北半球の温帯から暖帯にかけて(ロシア、朝鮮、中国、南アジア、ヨーロッパ、北アメリカ)に加え、中南米までに広く分布しています。日本では北海道、本州、四国、九州中部までに分布しています。落葉樹林やスギ林の土上に生えるシダで、花が咲いているような姿が特徴で、夏頃に葉を出します。切れ細かな葉が涼しげな印象を与えます。
ナツノハナワラビ は、ハナヤスリ科に属する大葉シダ植物の1つで、長い共通柄の先に羽状複葉の栄養葉同じく羽状に枝を出す胞子葉をセットにつけます。胞子葉を初夏に出す、夏緑性の真嚢シダ類です。本種はハナワラビ類の特徴を持ちますが、日本の他の種と較べると担葉体が長くて栄養葉を地表から離れた場所に出し、夏緑性であることなどで独特です。北半球の温帯から暖帯にかけて(ロシア、朝鮮、中国、南アジア、ヨーロッパ、北アメリカ)に加え、中南米までに広く分布しています。日本では北海道、本州、四国、九州中部までに分布しています。落葉樹林やスギ林の土上に生えるシダで、花が咲いているような姿が特徴で、夏頃に葉を出します。切れ細かな葉が涼しげな印象を与えます。
 ナラカシワは、岩手及び秋田県以南の本州、四国及び九州に分布するブナ科の落葉高木です。コナラやミズナラに似ていますが、葉の縁にカシワと同じような波形の大きなギザギザがあるため、ナラガシワと名付けられました。ナラかカシワかはっきりしない名前に多少モヤモヤしますが、いづれもブナ科コナラ属に属し、交雑もよく生じます。日本以外では朝鮮半島南部、中国東北部、ベトナム、タイ、ミャンマーなどの東南アジアに広く分布しています。樹皮にはクヌギと同じような裂け目があり、樹液にクワガタやカブトムシが集まる木として知られています。また、秋にできる実は硬い殻で覆われ、いわゆるドングリのなる木の一つです。葉は先端が尖った楕円形で形状はミズナラに似ていますが、長さは10~25センチにもなり、ミズナラより大きく、古来はホオノキと同じように食物を盛るのに使われました。葉の付け根にある葉柄は長さが2~3センチもあり、ミズナラやカシワのそれとは異なります。
ナラカシワは、岩手及び秋田県以南の本州、四国及び九州に分布するブナ科の落葉高木です。コナラやミズナラに似ていますが、葉の縁にカシワと同じような波形の大きなギザギザがあるため、ナラガシワと名付けられました。ナラかカシワかはっきりしない名前に多少モヤモヤしますが、いづれもブナ科コナラ属に属し、交雑もよく生じます。日本以外では朝鮮半島南部、中国東北部、ベトナム、タイ、ミャンマーなどの東南アジアに広く分布しています。樹皮にはクヌギと同じような裂け目があり、樹液にクワガタやカブトムシが集まる木として知られています。また、秋にできる実は硬い殻で覆われ、いわゆるドングリのなる木の一つです。葉は先端が尖った楕円形で形状はミズナラに似ていますが、長さは10~25センチにもなり、ミズナラより大きく、古来はホオノキと同じように食物を盛るのに使われました。葉の付け根にある葉柄は長さが2~3センチもあり、ミズナラやカシワのそれとは異なります。
 ヨメナは、中部以西の本州、四国及び九州に自生するキク科の多年草です。田畑の畔や川べりなど、湿った場所を好んで育ちます。代表的な野菊であり、花の美しさを新妻に擬えてヨメナと名付けられました。若菜には春菊のような香りがあり、山菜としても人気が高いです。葉は長さ8~10cm、幅3cmほどで茎から互い違いに生じます。食用となる若葉は柔らかで、やや紫色を帯びますが、成葉は濃緑で表面はピカピカしており、縁には粗いギザギザがあります。春先に摘んだ葉は天婦羅、煮浸し、和え物などにして食べられます。「ヨメナ飯」という混ぜご飯にするのはこのヨメナで、関東地方に生えているカントウヨメナは使いません。ヨメナの開花は夏から秋で、茎から枝分かれした花茎の先端に画像のような花を一輪ずつ咲かせます。花は直径3cmほどで、中央部にある黄色の管状花と、周囲を囲む淡い青色の舌状花に分けられます。
ヨメナは、中部以西の本州、四国及び九州に自生するキク科の多年草です。田畑の畔や川べりなど、湿った場所を好んで育ちます。代表的な野菊であり、花の美しさを新妻に擬えてヨメナと名付けられました。若菜には春菊のような香りがあり、山菜としても人気が高いです。葉は長さ8~10cm、幅3cmほどで茎から互い違いに生じます。食用となる若葉は柔らかで、やや紫色を帯びますが、成葉は濃緑で表面はピカピカしており、縁には粗いギザギザがあります。春先に摘んだ葉は天婦羅、煮浸し、和え物などにして食べられます。「ヨメナ飯」という混ぜご飯にするのはこのヨメナで、関東地方に生えているカントウヨメナは使いません。ヨメナの開花は夏から秋で、茎から枝分かれした花茎の先端に画像のような花を一輪ずつ咲かせます。花は直径3cmほどで、中央部にある黄色の管状花と、周囲を囲む淡い青色の舌状花に分けられます。
 本州〜沖縄の道ばたや畑、野原など、日当たりのよいところにふつうに見られます。葉は8〜16個の小葉からなり、先の方の1〜3個の小葉はふつう3分岐した巻きひげになります。葉柄基部の托葉は三角形で、黒っぽい花外蜜腺があり、蜜を分泌します。小葉は2〜3cmの狭倒卵形で、先端は矢筈状にへこんでいます。花は葉腋に1〜3個つき、紅紫色で長さ1.2〜1.8cmで、豆果は斜上し、扁平で長さ3〜5cm位です。なかには5〜10個の種子が入っています。熟すと真っ黒になって2つに裂け、果皮がよじれて黒い種子をはじきだします。別名カラスノエンドウと云い花期は3〜6月です。カラスノエンドウの若くて柔らかい部分(先端の若芽や花)は食べられます。葉、花、実(豆)が食用可能で、豆苗に似た食感や風味があり、サラダや味噌汁、天ぷら、炒め物、豆ご飯などに使えます。
本州〜沖縄の道ばたや畑、野原など、日当たりのよいところにふつうに見られます。葉は8〜16個の小葉からなり、先の方の1〜3個の小葉はふつう3分岐した巻きひげになります。葉柄基部の托葉は三角形で、黒っぽい花外蜜腺があり、蜜を分泌します。小葉は2〜3cmの狭倒卵形で、先端は矢筈状にへこんでいます。花は葉腋に1〜3個つき、紅紫色で長さ1.2〜1.8cmで、豆果は斜上し、扁平で長さ3〜5cm位です。なかには5〜10個の種子が入っています。熟すと真っ黒になって2つに裂け、果皮がよじれて黒い種子をはじきだします。別名カラスノエンドウと云い花期は3〜6月です。カラスノエンドウの若くて柔らかい部分(先端の若芽や花)は食べられます。葉、花、実(豆)が食用可能で、豆苗に似た食感や風味があり、サラダや味噌汁、天ぷら、炒め物、豆ご飯などに使えます。
 ハルサキヤマガラシまたはフユガラシとも呼ばれます。国内では北日本や高原地帯といった涼しい地域を中心に広がっています。亜高山帯など貴重な植生環境の場所にも入りこんで繁茂し、問題になっています。ハルザキヤマガラシはもともとヨーロッパに分布している野草でしたが、現在は北アメリカや北アフリカ、アジア、オセアニアなど、温帯地域の広域に広がっています。これは麦に混入するかたちで、世界中に拡散した結果と考えられています。国内でも、群馬県内の牧場で野生状態のものが確認され、やはりこれも麦に混入するかたちで侵入し、そこから定着したと考えられています。北日本では小麦畑やあぜなどに大発生して問題となっています。また高原地帯などの自然豊かな場所にも広がっており、現地の希少な植生をおびやかしています。
ハルサキヤマガラシまたはフユガラシとも呼ばれます。国内では北日本や高原地帯といった涼しい地域を中心に広がっています。亜高山帯など貴重な植生環境の場所にも入りこんで繁茂し、問題になっています。ハルザキヤマガラシはもともとヨーロッパに分布している野草でしたが、現在は北アメリカや北アフリカ、アジア、オセアニアなど、温帯地域の広域に広がっています。これは麦に混入するかたちで、世界中に拡散した結果と考えられています。国内でも、群馬県内の牧場で野生状態のものが確認され、やはりこれも麦に混入するかたちで侵入し、そこから定着したと考えられています。北日本では小麦畑やあぜなどに大発生して問題となっています。また高原地帯などの自然豊かな場所にも広がっており、現地の希少な植生をおびやかしています。
 ヒメコウガイゼキショウは、ヨーロッパ、アジア、アメリカ、アフリカの主要な地域に生息しており、広範囲にわたって分布しています。これらの大陸全体に渡るさまざまな気候帯を含む広大な生息域を持っています。さらに、ヒメコウガイゼキショウは北アメリカ、チリ、ニュージーランドなどの追加の地域にも導入されており、その適応性や原産地を超えての確立能力を示しています。一般的には、緑の塊の草のようなラッシュで、多くの細い茎が糸状の葉で包まれています。花は花序で、また花序が茎から分岐する関節で生まれます。それは、丈夫なbやがく片の中に折りたたまれた草花です。ヒメコウガイゼキショウは湿地から起源し、常に湿った環境で育ち、湿気のある条件を好みます。
ヒメコウガイゼキショウは、ヨーロッパ、アジア、アメリカ、アフリカの主要な地域に生息しており、広範囲にわたって分布しています。これらの大陸全体に渡るさまざまな気候帯を含む広大な生息域を持っています。さらに、ヒメコウガイゼキショウは北アメリカ、チリ、ニュージーランドなどの追加の地域にも導入されており、その適応性や原産地を超えての確立能力を示しています。一般的には、緑の塊の草のようなラッシュで、多くの細い茎が糸状の葉で包まれています。花は花序で、また花序が茎から分岐する関節で生まれます。それは、丈夫なbやがく片の中に折りたたまれた草花です。ヒメコウガイゼキショウは湿地から起源し、常に湿った環境で育ち、湿気のある条件を好みます。
 ペラペラヨメナは、中央アメリカを中心に分布するキク科ムカシヨモギ属の多年草です。分布域はメキシコから中央アメリカ、コロンビア、ベネズエラにあり、丘陵地帯の斜面や森林の開けた場所、岩場などに自生しています。多様な環境に適応する高い生命力から、アフリカやヨーロッパ、アジアなど、世界中の熱帯から亜熱帯、温帯地域に移入分布しています。日本には明治時代末期に渡来しており、関東以南の本州、四国、九州などで帰化植物として定着しています。和名はペラペラヨメナですが、主にゲンペイコギクの名前で流通します。その他、エリゲロン、ペラペラヒメジョオン、メキシコヒナギクと呼ばれることもあります。花期は5月~11月です。花期になると、下部で細かく分枝した茎の頂部に、直径1.5~2㎝の小さな頭花(トウカ)を咲かせます。
ペラペラヨメナは、中央アメリカを中心に分布するキク科ムカシヨモギ属の多年草です。分布域はメキシコから中央アメリカ、コロンビア、ベネズエラにあり、丘陵地帯の斜面や森林の開けた場所、岩場などに自生しています。多様な環境に適応する高い生命力から、アフリカやヨーロッパ、アジアなど、世界中の熱帯から亜熱帯、温帯地域に移入分布しています。日本には明治時代末期に渡来しており、関東以南の本州、四国、九州などで帰化植物として定着しています。和名はペラペラヨメナですが、主にゲンペイコギクの名前で流通します。その他、エリゲロン、ペラペラヒメジョオン、メキシコヒナギクと呼ばれることもあります。花期は5月~11月です。花期になると、下部で細かく分枝した茎の頂部に、直径1.5~2㎝の小さな頭花(トウカ)を咲かせます。
 マリアアザミはキク科オオアザミ属の二年草で、英名はミルクシスル と云います。原産地はヨーロッパで、日本には嘉永年間に渡来し、西日本などに点在して帰化植物として分布しています。標準和名はオオアザミで、マリアアザミはその別名です。聖母マリアにミルクを捧げる娘がトゲに触れ、驚いてこぼしたミルクが葉を白くしたという伝説によるものです。花期は夏で、茎の頂部に頭花を1個つけるます。総苞は幅5~7cmあり、総苞片は幅1.5cmにもなり縁にトゲが多く付いています。筒状花は紅紫色から淡紅色で、両生花、花糸の下部が合着して筒になるのは本種の特徴であるです。花床には毛状の鱗片が多くあります。花後にできる果実は黒褐色で長さ6~7mmで 、無毛で滑らかです。冠毛は長さ1.5cmで脱落しやすく、種子にはシリマリン と呼ばれる4種のフラボノリグナン類が多く含まれ、傷ついた肝細胞の修復を助けるとされています。
マリアアザミはキク科オオアザミ属の二年草で、英名はミルクシスル と云います。原産地はヨーロッパで、日本には嘉永年間に渡来し、西日本などに点在して帰化植物として分布しています。標準和名はオオアザミで、マリアアザミはその別名です。聖母マリアにミルクを捧げる娘がトゲに触れ、驚いてこぼしたミルクが葉を白くしたという伝説によるものです。花期は夏で、茎の頂部に頭花を1個つけるます。総苞は幅5~7cmあり、総苞片は幅1.5cmにもなり縁にトゲが多く付いています。筒状花は紅紫色から淡紅色で、両生花、花糸の下部が合着して筒になるのは本種の特徴であるです。花床には毛状の鱗片が多くあります。花後にできる果実は黒褐色で長さ6~7mmで 、無毛で滑らかです。冠毛は長さ1.5cmで脱落しやすく、種子にはシリマリン と呼ばれる4種のフラボノリグナン類が多く含まれ、傷ついた肝細胞の修復を助けるとされています。
 マンネングサは、多肉質な葉を持つ1年草または多年草で、常緑な葉を持ち、丈夫でいつまでも枯れないことから万年草と呼ばれています 海岸や道端など日当たりの良い乾燥した場所で見られ、ほふく性のものが多くグランドカバーやハンギングにも向きます。日本では石垣などの被覆に使われたこともあり、また多肉植物として栽培されるものも多いです。また、乾燥、高低温、塩害、アルカリ性に強く、屋上緑化に適した植物としても注目・利用されましたが、日本の夏の高温多湿下では蒸れに弱く、病気で衰退してしまう、マンネングサの葉は小さい上にCAM型光合成を行う特性上、水分の蒸発量が少ないので緑化による冷却効果が少ない、などの理由から廃れつつあります。
マンネングサは、多肉質な葉を持つ1年草または多年草で、常緑な葉を持ち、丈夫でいつまでも枯れないことから万年草と呼ばれています 海岸や道端など日当たりの良い乾燥した場所で見られ、ほふく性のものが多くグランドカバーやハンギングにも向きます。日本では石垣などの被覆に使われたこともあり、また多肉植物として栽培されるものも多いです。また、乾燥、高低温、塩害、アルカリ性に強く、屋上緑化に適した植物としても注目・利用されましたが、日本の夏の高温多湿下では蒸れに弱く、病気で衰退してしまう、マンネングサの葉は小さい上にCAM型光合成を行う特性上、水分の蒸発量が少ないので緑化による冷却効果が少ない、などの理由から廃れつつあります。
 ミルスベリヒユは沿岸環境に豊かに成長する頑丈で力強い植物であり、手入れがほとんど不要であり、手間のかからない植物を求める人に最適です。ミルスベリヒユの特別なケアポイントは、その自然な砂の生息地を模倣するように、十分に排水された土壌を確保することです。さらに、耐塩性を持ち、定期的な水やりが十分で、ミルスベリヒユは非常に耐干ばつ性に優れています。沿岸地域原産のミルスベリヒユは、塩分の多い環境に適応しており、排水の良い砂質土壌で繁栄します。この多肉植物は乾燥に対する高い耐性を示し、葉に効果的に水分を保持します。ミルスベリヒユは部分的な日光にも耐えますが、理想的な光強度から長い時間離れると成長が不十分になり、繁栄能力の低下の可能性があります。適応力があるミルスベリヒユは、葉を変化させて光の吸収を最大化することで、さまざまな光レベルに耐えることができます。
ミルスベリヒユは沿岸環境に豊かに成長する頑丈で力強い植物であり、手入れがほとんど不要であり、手間のかからない植物を求める人に最適です。ミルスベリヒユの特別なケアポイントは、その自然な砂の生息地を模倣するように、十分に排水された土壌を確保することです。さらに、耐塩性を持ち、定期的な水やりが十分で、ミルスベリヒユは非常に耐干ばつ性に優れています。沿岸地域原産のミルスベリヒユは、塩分の多い環境に適応しており、排水の良い砂質土壌で繁栄します。この多肉植物は乾燥に対する高い耐性を示し、葉に効果的に水分を保持します。ミルスベリヒユは部分的な日光にも耐えますが、理想的な光強度から長い時間離れると成長が不十分になり、繁栄能力の低下の可能性があります。適応力があるミルスベリヒユは、葉を変化させて光の吸収を最大化することで、さまざまな光レベルに耐えることができます。
 ヤエムグラは、身近な場所に普通に生える1年から越年草です。茎はやわらかく、あちこちにもたれかかったり折り重なったりしながら、50センチメートルから100センチメートル近くにまでのびていきます。茎や葉には下向きの小さな刺がたくさん生えていて、さわるとザラザラしています。この刺は茎のずり落ち防止に役立っています。4月から6月ごろに、直径1ミリメートルから2ミリメートルほどのとても小さな黄緑色の花を多数咲かせます。花びらは4枚あるように見えますが、合弁花なので根元で全部つながっていて、冠状になっています。このような花びらを花冠(かかん)と言います。果実は直径2ミリメートルほどの球形で、ふつう2個1組となってつきます。熟すと真っ黒になり、かぎづめ状の刺で洋服や動物の体によくくっつきます。
ヤエムグラは、身近な場所に普通に生える1年から越年草です。茎はやわらかく、あちこちにもたれかかったり折り重なったりしながら、50センチメートルから100センチメートル近くにまでのびていきます。茎や葉には下向きの小さな刺がたくさん生えていて、さわるとザラザラしています。この刺は茎のずり落ち防止に役立っています。4月から6月ごろに、直径1ミリメートルから2ミリメートルほどのとても小さな黄緑色の花を多数咲かせます。花びらは4枚あるように見えますが、合弁花なので根元で全部つながっていて、冠状になっています。このような花びらを花冠(かかん)と言います。果実は直径2ミリメートルほどの球形で、ふつう2個1組となってつきます。熟すと真っ黒になり、かぎづめ状の刺で洋服や動物の体によくくっつきます。
 ハラタケは、肥沃な草地や芝生に発生し、(菌輪)”をつくることでも知られています。また、傘の表面は白色~若干黄色みを帯びたような白色をしており、キレイな絹状の光沢が見られます。傘の裏側である“ひだ”の部分は淡紅色をしており、この淡紅色は「胞子」そのものの色に由来するそう。“ひだ”が淡紅色というのはハラタケ属の特徴の一つとされていますが、春からみられる点や、やわらかいピンク色は、なんだか春を象徴するようです。ちなみに、ハラタケは、食用きのこである“マッシュルーム”と近縁の種であり、食べることのできるきのことされています。しかし、ハラタケにはよく似たきのこで毒成分を持った種類もあり、判断が難しいとされていますので、専門家の確認がない場合は決してお召し上がりいただかず、きのこの姿を見たり、触れたりして楽しむようにして下さい。
ハラタケは、肥沃な草地や芝生に発生し、(菌輪)”をつくることでも知られています。また、傘の表面は白色~若干黄色みを帯びたような白色をしており、キレイな絹状の光沢が見られます。傘の裏側である“ひだ”の部分は淡紅色をしており、この淡紅色は「胞子」そのものの色に由来するそう。“ひだ”が淡紅色というのはハラタケ属の特徴の一つとされていますが、春からみられる点や、やわらかいピンク色は、なんだか春を象徴するようです。ちなみに、ハラタケは、食用きのこである“マッシュルーム”と近縁の種であり、食べることのできるきのことされています。しかし、ハラタケにはよく似たきのこで毒成分を持った種類もあり、判断が難しいとされていますので、専門家の確認がない場合は決してお召し上がりいただかず、きのこの姿を見たり、触れたりして楽しむようにして下さい。
 地衣類は、菌類と藻類(主に緑藻やシアノバクテリア)が共生関係を結んでできた複合体です。また、分類学(国際植物命名規約)上は、その複合体を構成する菌類(共生菌)のことを地衣類とみなしています。従って地衣類は、系統的に一つのまとまりを成す分類群ではなく、複数の系統から生じた、藻類との共生という生態的あるいは生理的な特徴を共有する(=「地衣化」する)菌類の総称です。一方、地衣類は、一般には蘚苔(センタイ)類(コケ植物)などとともに「こけ」と認識されていることが多いです。「こけ」は「むし」などと同じく雑多な小さな生物群の総称であり専門用語ではありませんので、地衣類のことを「こけ」と呼んでも間違いではありません。しかし、コケ植物(あるいはコケ類)というと間違いになります。
地衣類は、菌類と藻類(主に緑藻やシアノバクテリア)が共生関係を結んでできた複合体です。また、分類学(国際植物命名規約)上は、その複合体を構成する菌類(共生菌)のことを地衣類とみなしています。従って地衣類は、系統的に一つのまとまりを成す分類群ではなく、複数の系統から生じた、藻類との共生という生態的あるいは生理的な特徴を共有する(=「地衣化」する)菌類の総称です。一方、地衣類は、一般には蘚苔(センタイ)類(コケ植物)などとともに「こけ」と認識されていることが多いです。「こけ」は「むし」などと同じく雑多な小さな生物群の総称であり専門用語ではありませんので、地衣類のことを「こけ」と呼んでも間違いではありません。しかし、コケ植物(あるいはコケ類)というと間違いになります。
 シナダレスズメガヤは南アフリカ原産の多年生草本で、法面の緑化などの目的で導入されました。葉は細くて(~2mm)垂れ下がります。乾燥すると葉は上面を巻き込んで更に細くなります。初夏から盛夏にかけて花穂を形成します。花の色は灰緑色のものから掲載した紫色のものまであり多様です。染色体数にかなりの幅があり、多様な系統があるものと思われます。乾燥に強く、荒れ地の緑化などに用いられています。法面の緑化では、複数の種類を混合して播種することが普通ですが、オニウシノケグサと混合して播種されると、乾燥する痩悪地ではシナダレスズメガヤが、適潤地ではオニウシノケグサが優勢となります。シナダレスズメガヤは株状となって繁茂し、葉が垂れ下がるために株と株の間が無植生となる傾向が高いです。したがって初期には良好な地被となりますが、やがて株間が空き、斜面侵食が発生する可能性が指摘されています。
シナダレスズメガヤは南アフリカ原産の多年生草本で、法面の緑化などの目的で導入されました。葉は細くて(~2mm)垂れ下がります。乾燥すると葉は上面を巻き込んで更に細くなります。初夏から盛夏にかけて花穂を形成します。花の色は灰緑色のものから掲載した紫色のものまであり多様です。染色体数にかなりの幅があり、多様な系統があるものと思われます。乾燥に強く、荒れ地の緑化などに用いられています。法面の緑化では、複数の種類を混合して播種することが普通ですが、オニウシノケグサと混合して播種されると、乾燥する痩悪地ではシナダレスズメガヤが、適潤地ではオニウシノケグサが優勢となります。シナダレスズメガヤは株状となって繁茂し、葉が垂れ下がるために株と株の間が無植生となる傾向が高いです。したがって初期には良好な地被となりますが、やがて株間が空き、斜面侵食が発生する可能性が指摘されています。
 カヤタケはカサの形が特徴的なキノコで、幼菌時は丸い山形、成長すると中央部に窪みが見られる饅頭型となり、最終的には反り返って漏斗型となります。色は淡い橙色~淡い赤茶色で周辺部分は白っぽくなっています。また、周辺のフチ付近には放射状の短い溝線が見られる事があります。ヒダは柄に大きく垂生しており、色は白色。全体的に密に並んでいます。カヤタケは柄は長さが4~7cmほどで基本的に上から下まで太さは変わりませんが、まれに根元に近づくほど、やや太くなっているものもあります。柄の色はカサとほぼ同色で、白色をした綿毛状の菌糸が基部を覆っています。肉はカサの部分は厚みがありますが、柄の部分は薄く、色は白色。特徴的な味や匂いは殆ど感じられません。このカヤタケはドクササコやホテイシメジとよく似ており、間違われやすい事でも知られているキノコです。
カヤタケはカサの形が特徴的なキノコで、幼菌時は丸い山形、成長すると中央部に窪みが見られる饅頭型となり、最終的には反り返って漏斗型となります。色は淡い橙色~淡い赤茶色で周辺部分は白っぽくなっています。また、周辺のフチ付近には放射状の短い溝線が見られる事があります。ヒダは柄に大きく垂生しており、色は白色。全体的に密に並んでいます。カヤタケは柄は長さが4~7cmほどで基本的に上から下まで太さは変わりませんが、まれに根元に近づくほど、やや太くなっているものもあります。柄の色はカサとほぼ同色で、白色をした綿毛状の菌糸が基部を覆っています。肉はカサの部分は厚みがありますが、柄の部分は薄く、色は白色。特徴的な味や匂いは殆ど感じられません。このカヤタケはドクササコやホテイシメジとよく似ており、間違われやすい事でも知られているキノコです。
 ヒメシバは、イネ科メヒシバ属の植物で、身近にごく普通に見られるイネ科の植物であす。細い茎で地表を這い、立ち上がった花茎の先に、数本の細い穂を放射状に伸ばします。勢力の強い雑草としても知られています。さほど大きくない一年草で、根元の茎は地表を這い、立ち上がった茎の先に細い穂を数本、放射状に広げます。名前の由来は雌日芝で、その形がややオヒシバに似ていますが、ずっと優しげであることからの名と思われます。メイシバ、あるいはメイジワと表記されることもあります。茎は細く、基部は分枝しながら地表を這い、節々から根を下ろします。葉は細い長楕円形、長さは8~20cm、薄くて柔らかく、つやがありません。花茎は立ち上がり、高さは30~70cmになります。夏から秋にかけて、緑紫色の花穂をつけます。花茎の先端に数本の穂が伸び、当初は束になって出ますが、次第に放射状に広がります。
ヒメシバは、イネ科メヒシバ属の植物で、身近にごく普通に見られるイネ科の植物であす。細い茎で地表を這い、立ち上がった花茎の先に、数本の細い穂を放射状に伸ばします。勢力の強い雑草としても知られています。さほど大きくない一年草で、根元の茎は地表を這い、立ち上がった茎の先に細い穂を数本、放射状に広げます。名前の由来は雌日芝で、その形がややオヒシバに似ていますが、ずっと優しげであることからの名と思われます。メイシバ、あるいはメイジワと表記されることもあります。茎は細く、基部は分枝しながら地表を這い、節々から根を下ろします。葉は細い長楕円形、長さは8~20cm、薄くて柔らかく、つやがありません。花茎は立ち上がり、高さは30~70cmになります。夏から秋にかけて、緑紫色の花穂をつけます。花茎の先端に数本の穂が伸び、当初は束になって出ますが、次第に放射状に広がります。
 ヘビイチゴの仲間を見つけたら、まず見るべきポイントは花の数です。 一本の茎が枝を分けていくつも花を咲かせていたら、それ以外の種類だと判別できます。 花の後にイチゴ状の果実ができることがこの2種の共通点となります。ヘビイチゴは食べられますが、美味しくはありません。毒はないため食べても害はありませんが、甘みや酸味、ジューシーさがほとんどなく、食感もスカスカで種が目立つため、食用にはあまり適していません。ヘビイチゴには、生薬名「蛇莓(ジャバイ)」として、解熱、通経(生理を促す)、咳止めの効能があるとされます。また、民間療法では、虫刺されや肌荒れのかゆみ止めとしても利用され、焼酎に漬け込んだ「ヘビイチゴのチンキ(薬酒)」が作られます。これは、ポリフェノールなどを含む成分による抗酸化作用、抗炎症作用によるものと考えられています。
ヘビイチゴの仲間を見つけたら、まず見るべきポイントは花の数です。 一本の茎が枝を分けていくつも花を咲かせていたら、それ以外の種類だと判別できます。 花の後にイチゴ状の果実ができることがこの2種の共通点となります。ヘビイチゴは食べられますが、美味しくはありません。毒はないため食べても害はありませんが、甘みや酸味、ジューシーさがほとんどなく、食感もスカスカで種が目立つため、食用にはあまり適していません。ヘビイチゴには、生薬名「蛇莓(ジャバイ)」として、解熱、通経(生理を促す)、咳止めの効能があるとされます。また、民間療法では、虫刺されや肌荒れのかゆみ止めとしても利用され、焼酎に漬け込んだ「ヘビイチゴのチンキ(薬酒)」が作られます。これは、ポリフェノールなどを含む成分による抗酸化作用、抗炎症作用によるものと考えられています。
 オオバセンキュウは、セリ科の多年草で、北海道、本州中部以北の山中の渓谷などに生えます。茎は太く柔らかく中空で、直立しますが上部で枝分かれします。高さは80~120cmになります。葉は、円くふくらんで、柄があり、羽状複葉に分裂します。小葉は卵形で、先端は尖り、縁には鋸歯があります。秋、枝の先端に白色の小花が傘状に密生して咲きます。中国原産と推定されている多年生草本植物です。暖かい気候での生育はよくありません。ですから夏季にあまり気温が上がらない北海道や東北地方,長野などの冷涼地に生えてています。全株に特有の香りがあります。根茎は節が重なり合うように塊状に肥大しています。葉は長い柄をつけ,2~3回羽状に深く切れ込んでいます。花は白色で小さく,花茎の先端に複散形状に多数つき晩夏から秋に咲きますが,果実は結実しません。
オオバセンキュウは、セリ科の多年草で、北海道、本州中部以北の山中の渓谷などに生えます。茎は太く柔らかく中空で、直立しますが上部で枝分かれします。高さは80~120cmになります。葉は、円くふくらんで、柄があり、羽状複葉に分裂します。小葉は卵形で、先端は尖り、縁には鋸歯があります。秋、枝の先端に白色の小花が傘状に密生して咲きます。中国原産と推定されている多年生草本植物です。暖かい気候での生育はよくありません。ですから夏季にあまり気温が上がらない北海道や東北地方,長野などの冷涼地に生えてています。全株に特有の香りがあります。根茎は節が重なり合うように塊状に肥大しています。葉は長い柄をつけ,2~3回羽状に深く切れ込んでいます。花は白色で小さく,花茎の先端に複散形状に多数つき晩夏から秋に咲きますが,果実は結実しません。
 ヤブタバコは、林の中や公園の木陰など、やや薄暗い場所にたくさん生える越年草です。茎ののびかたが独特で、初めのうちはまっすぐ上へとのびていきますが、1mくらいの高さになるとそこで頭打ちとなり、そこから横に向かって枝をどんどん広げていきます。夏から秋にかけて、葉のわきに直径1cmほどの黄色い花を咲かせます。花は葉に隠れるようにして下向きにつくため、観察するには見上げるか、枝を軽く裏返してみる必要があります。その後できるタネは細長いかたちで、表面はべたべたした粘液に覆われ、独特の匂いがします。名前の由来は、株もとの葉の雰囲気が、まるでタバコの葉のように見えることから来ています。タバコはナス科の植物ですが、ヤブタバコはキク科とまったく別の種類です。もちろんタバコの原料にはなりません。
ヤブタバコは、林の中や公園の木陰など、やや薄暗い場所にたくさん生える越年草です。茎ののびかたが独特で、初めのうちはまっすぐ上へとのびていきますが、1mくらいの高さになるとそこで頭打ちとなり、そこから横に向かって枝をどんどん広げていきます。夏から秋にかけて、葉のわきに直径1cmほどの黄色い花を咲かせます。花は葉に隠れるようにして下向きにつくため、観察するには見上げるか、枝を軽く裏返してみる必要があります。その後できるタネは細長いかたちで、表面はべたべたした粘液に覆われ、独特の匂いがします。名前の由来は、株もとの葉の雰囲気が、まるでタバコの葉のように見えることから来ています。タバコはナス科の植物ですが、ヤブタバコはキク科とまったく別の種類です。もちろんタバコの原料にはなりません。
 キンミズヒキは、夏から秋まで細い花茎に連なるように黄色の花を咲かせるバラ科の多年草。道端や野原、山林、林の中などいたるところで見かけ、山野草として分類されることもあります。夏から秋にかけて赤や白の花が開花する名前が似ているミズヒキはタデ科、キンミズヒキはバラ科なので、分類は別の植物です。ミズヒキとは違い、ひとつひとつの花は小さいながらも目立ちます。キンミズヒキの葉は、いちごやポテンティラの葉に似た形をしています。夏になると、株元からすっと花茎が立ち上がり、秋にかけて黄色い花が開花します。
キンミズヒキは、夏から秋まで細い花茎に連なるように黄色の花を咲かせるバラ科の多年草。道端や野原、山林、林の中などいたるところで見かけ、山野草として分類されることもあります。夏から秋にかけて赤や白の花が開花する名前が似ているミズヒキはタデ科、キンミズヒキはバラ科なので、分類は別の植物です。ミズヒキとは違い、ひとつひとつの花は小さいながらも目立ちます。キンミズヒキの葉は、いちごやポテンティラの葉に似た形をしています。夏になると、株元からすっと花茎が立ち上がり、秋にかけて黄色い花が開花します。
 オシロイタケは、針葉樹や広葉樹の枯木に生える白いキノコです。傘は半円形~丸山形で、白色から次第に黄ばみ、表面は無毛で環紋(輪状の模様)がありません。肉は柔軟な肉質で、乾燥すると軽く脆くなります。古くなるにつれて表面は次第に黄ばんできます。オオオシロイタケによく似ていますが、こちらはまったくの別種で表面に毛があります。褐色腐朽菌に分類され、材を分解する役割を担っています。オシロイタケは、一部では食べられるとされていますが、酸味や苦味があり美味しくないため、一般的に食用には不適とされています。また、キシメジ科のオシロイシメジのように、下痢を引き起こす場合があるなど、人によっては中毒症状を起こす野生きのこも存在するため、専門知識なしに食べることは危険です。オシロイタケ属にはチーズのような柔らかい質感を持つキノコがおり、これらは栄養循環において重要な役割を果たします。「アケボノオシロイタケ」という赤いキノコも存在しますが、これはオシロイタケとは全く異なる種です。
オシロイタケは、針葉樹や広葉樹の枯木に生える白いキノコです。傘は半円形~丸山形で、白色から次第に黄ばみ、表面は無毛で環紋(輪状の模様)がありません。肉は柔軟な肉質で、乾燥すると軽く脆くなります。古くなるにつれて表面は次第に黄ばんできます。オオオシロイタケによく似ていますが、こちらはまったくの別種で表面に毛があります。褐色腐朽菌に分類され、材を分解する役割を担っています。オシロイタケは、一部では食べられるとされていますが、酸味や苦味があり美味しくないため、一般的に食用には不適とされています。また、キシメジ科のオシロイシメジのように、下痢を引き起こす場合があるなど、人によっては中毒症状を起こす野生きのこも存在するため、専門知識なしに食べることは危険です。オシロイタケ属にはチーズのような柔らかい質感を持つキノコがおり、これらは栄養循環において重要な役割を果たします。「アケボノオシロイタケ」という赤いキノコも存在しますが、これはオシロイタケとは全く異なる種です。
 ヒトクチタケは、主にマツの枯れ木に発生するサルノコシカケ科のキノコです。栗まんじゅうのような光沢のある黄褐色~茶色の傘を持ち、成熟すると傘の下面に楕円形の穴(一口)が開くことが名前の由来です。食用には適さず、干物のような臭いがあり、内部には昆虫やその幼虫が多数生息していることが多いのが特徴です。黄褐色~栗褐色の栗まんじゅうのような形をしており、表面にはニス状の光沢があります。成熟すると、傘の下面に包皮に開いた楕円形の穴(一口)ができます。主に枯れて間もないアカマツやクロマツに発生します。春から夏にかけて見られます。干した魚のような独特の臭いがあります。傘の下面の穴の中や空洞部分には、甲虫やその幼虫などが多数生息しています。食用には適しません。
ヒトクチタケは、主にマツの枯れ木に発生するサルノコシカケ科のキノコです。栗まんじゅうのような光沢のある黄褐色~茶色の傘を持ち、成熟すると傘の下面に楕円形の穴(一口)が開くことが名前の由来です。食用には適さず、干物のような臭いがあり、内部には昆虫やその幼虫が多数生息していることが多いのが特徴です。黄褐色~栗褐色の栗まんじゅうのような形をしており、表面にはニス状の光沢があります。成熟すると、傘の下面に包皮に開いた楕円形の穴(一口)ができます。主に枯れて間もないアカマツやクロマツに発生します。春から夏にかけて見られます。干した魚のような独特の臭いがあります。傘の下面の穴の中や空洞部分には、甲虫やその幼虫などが多数生息しています。食用には適しません。
 ヤマブキソウは、明るめの森や林の落葉樹の株元などに自生する日本原産の宿根草です。本州をはじめ、四国、九州に分布しています。少し湿った土を好み、環境に合えば、こぼれ種で増えていきます。現在は、採取や森林伐採により野生種が減少傾向で、各自治体の絶滅危惧種(レッドリスト)に掲載されていることもあります。ヤマブキソウの名前の由来は、落葉低木のヤマブキの花の色や形に似ていることからつきましたが、ヤマブキはバラ科の木、ヤマブキソウはケシ科の草なので、分類的には違う植物です。また、バラ科のヤマブキの花弁は5枚、ヤマブキソウは4枚と見た目の違いもあります。4月~6月の開花時になると、株元から花茎を立ち上げ、茎先に花が1~3輪開花します。草丈30cm前後で、4枚の花弁の明るい黄色の花が落葉樹の足元で開花し、開花時は華やかな風景となります。
ヤマブキソウは、明るめの森や林の落葉樹の株元などに自生する日本原産の宿根草です。本州をはじめ、四国、九州に分布しています。少し湿った土を好み、環境に合えば、こぼれ種で増えていきます。現在は、採取や森林伐採により野生種が減少傾向で、各自治体の絶滅危惧種(レッドリスト)に掲載されていることもあります。ヤマブキソウの名前の由来は、落葉低木のヤマブキの花の色や形に似ていることからつきましたが、ヤマブキはバラ科の木、ヤマブキソウはケシ科の草なので、分類的には違う植物です。また、バラ科のヤマブキの花弁は5枚、ヤマブキソウは4枚と見た目の違いもあります。4月~6月の開花時になると、株元から花茎を立ち上げ、茎先に花が1~3輪開花します。草丈30cm前後で、4枚の花弁の明るい黄色の花が落葉樹の足元で開花し、開花時は華やかな風景となります。
 コガサタケは、傘もヒダも線状で薄茶色の小型キノコですが、幻覚を誘発する物質を含む有毒性キノコとされており、所持、保管、販売、摂取などは管理されています。コガサタケは草地や牧草地、公園の芝生、林縁、林道脇などで見られます。地上のほか、落ち葉やマルチ材のウッドチップに発生します。コガサタケは、見た目は普通ですが、非常に危険な毒キノコの仲間です。この種の研究はまだ十分されているわけではありませんが、近縁種は強力な毒素を含んでおり、嘔吐や胃痙攣、血圧低下、息切れ、肝不全、腎不全などを引き起こします。湿気の多い時期に水をあげすぎると、キコガサタケが生えてくるかもしれません。 もし生えてきたときは、手で引き抜くなどの対処をするようにしましょう。 大量に生えてきた場合は、除菌剤を使って対処するのも有効です。 また、キノコによっては芝生が枯れてしまう原因にもなるため、湿気の多い時期には注意しましょう。
コガサタケは、傘もヒダも線状で薄茶色の小型キノコですが、幻覚を誘発する物質を含む有毒性キノコとされており、所持、保管、販売、摂取などは管理されています。コガサタケは草地や牧草地、公園の芝生、林縁、林道脇などで見られます。地上のほか、落ち葉やマルチ材のウッドチップに発生します。コガサタケは、見た目は普通ですが、非常に危険な毒キノコの仲間です。この種の研究はまだ十分されているわけではありませんが、近縁種は強力な毒素を含んでおり、嘔吐や胃痙攣、血圧低下、息切れ、肝不全、腎不全などを引き起こします。湿気の多い時期に水をあげすぎると、キコガサタケが生えてくるかもしれません。 もし生えてきたときは、手で引き抜くなどの対処をするようにしましょう。 大量に生えてきた場合は、除菌剤を使って対処するのも有効です。 また、キノコによっては芝生が枯れてしまう原因にもなるため、湿気の多い時期には注意しましょう。
 アメリカ合衆国原産のオオホナガアオゲイトウですが、南アメリカ、ユーラシア、アフリカに世界中に分布しています。アメリカ合衆国では非常に侵略的であり、オハイオ州やミネソタ州で侵略的な植物とされています。自然な生息地は砂漠ですが、雑草として作物と一緒に見られることもあります。北米原産ですが日本には1930年代に渡来し、道端や空き地などで見られます。高さ1 mを超すこともある直立する茎を持ち、長く伸びる花序に花を穂状に付けます。アメリカでは有害雑草とされますが、除草剤への耐性を獲得したものが確認されています。オオホナガアオゲイトウ は、窒素が豊富な土壌で栽培されると葉に硝酸塩を蓄積する可能性があり、大量に摂取すると有害です。硝酸塩は、胃癌やブルーべビー症候群に関連しています、また、速い呼吸、心拍数の増加、震え、そして場合によっては死に至ることもあります。オオホナガアオゲイトウは、飛散によるアレルギーや皮膚接触による皮膚炎を引き起こしません。
アメリカ合衆国原産のオオホナガアオゲイトウですが、南アメリカ、ユーラシア、アフリカに世界中に分布しています。アメリカ合衆国では非常に侵略的であり、オハイオ州やミネソタ州で侵略的な植物とされています。自然な生息地は砂漠ですが、雑草として作物と一緒に見られることもあります。北米原産ですが日本には1930年代に渡来し、道端や空き地などで見られます。高さ1 mを超すこともある直立する茎を持ち、長く伸びる花序に花を穂状に付けます。アメリカでは有害雑草とされますが、除草剤への耐性を獲得したものが確認されています。オオホナガアオゲイトウ は、窒素が豊富な土壌で栽培されると葉に硝酸塩を蓄積する可能性があり、大量に摂取すると有害です。硝酸塩は、胃癌やブルーべビー症候群に関連しています、また、速い呼吸、心拍数の増加、震え、そして場合によっては死に至ることもあります。オオホナガアオゲイトウは、飛散によるアレルギーや皮膚接触による皮膚炎を引き起こしません。
 サルノコシカケは、北海道から本州、四国、九州及び北半球に分布し、枯木や倒木、弱った木に自生する多年生菌類です。傘は半円形で厚さ5〜 20cm、径5〜 30cm、時には60cmほどになります。写真は酒田市内公園のソメイヨシノの幹にできたコフキサルノコシカケです。この種のキノコはサクラ類の他、ケヤキなどの広葉樹、イチョウなどの針葉樹と広い樹種に発生します。サルノコシカケは担子菌類という菌が傷口から樹木の内に入って悪さをしたことで発生する病気です。サルノコシカケは一般的に食用ではなく、薬用として煎じて飲まれたり、細工物や飾り物に使われたりするキノコです。特にコフキサルノコシカケは、胞子を吹きつける様子からその名がついたキノコで、民間薬として利用されることが話題になることがありますが、食用には適していません。
サルノコシカケは、北海道から本州、四国、九州及び北半球に分布し、枯木や倒木、弱った木に自生する多年生菌類です。傘は半円形で厚さ5〜 20cm、径5〜 30cm、時には60cmほどになります。写真は酒田市内公園のソメイヨシノの幹にできたコフキサルノコシカケです。この種のキノコはサクラ類の他、ケヤキなどの広葉樹、イチョウなどの針葉樹と広い樹種に発生します。サルノコシカケは担子菌類という菌が傷口から樹木の内に入って悪さをしたことで発生する病気です。サルノコシカケは一般的に食用ではなく、薬用として煎じて飲まれたり、細工物や飾り物に使われたりするキノコです。特にコフキサルノコシカケは、胞子を吹きつける様子からその名がついたキノコで、民間薬として利用されることが話題になることがありますが、食用には適していません。
 キダチコンギクの葉は交互に配置され、滑らかな縁を持っています。上面は緑色を示し、下面は灰色です。縁と葉柄には明確な毛が生えており、手触りに寄与しています。葉の形は通常、披針形で、長さは約1から2.5cmから10cmです。葉脈は明確な中央葉脈が特徴で、そこから二次葉脈が外向きに枝分かれし、葉の構造と機能を支えています。キダチコンギクは小さな白いヒナギクのような花を持ち、それぞれの幅は1/2から1.3cmから1.9cmです。これらの花は9月下旬から11月にかけて、1.2mの茎に咲きます。各花は中央に黄色の管状花のクラスターを持ち、16から25の白い舌状花が周囲を取り囲み、独特で魅力的な外観を呈します。黄色の中心部と白い花弁との鮮やかなコントラストがキダチコンギクの花を庭園に魅力的なアクセントとして追加します。
キダチコンギクの葉は交互に配置され、滑らかな縁を持っています。上面は緑色を示し、下面は灰色です。縁と葉柄には明確な毛が生えており、手触りに寄与しています。葉の形は通常、披針形で、長さは約1から2.5cmから10cmです。葉脈は明確な中央葉脈が特徴で、そこから二次葉脈が外向きに枝分かれし、葉の構造と機能を支えています。キダチコンギクは小さな白いヒナギクのような花を持ち、それぞれの幅は1/2から1.3cmから1.9cmです。これらの花は9月下旬から11月にかけて、1.2mの茎に咲きます。各花は中央に黄色の管状花のクラスターを持ち、16から25の白い舌状花が周囲を取り囲み、独特で魅力的な外観を呈します。黄色の中心部と白い花弁との鮮やかなコントラストがキダチコンギクの花を庭園に魅力的なアクセントとして追加します。
 ツルフジバカマは、川沿いの土手にある草地などに生える蔓性の多年草です。近似種のクサフジがフジの仲間ではないように、本種もフジバカマの仲間ではまったくありません。牧野富太郎博士によれば赤紫系の花色がフジバカマに喩(たと)えられたとのことですが、色味がまったく異なるので類似性はこれっぽっちも感じられません。誰かがクサフジに対応させて風流気取って命名するもスベったようです。ツルフジバカマ は半日陰または明るい日陰で最もよく育ちますが、直射日光にも耐える可能性があります。果実は春の終わりから初夏に向かって熟します。シーズン後半の高温と多くの日光にさらされるとツルフジバカマ が害を被る可能性があるため、できるだけ日陰を提供することがベストです。
ツルフジバカマは、川沿いの土手にある草地などに生える蔓性の多年草です。近似種のクサフジがフジの仲間ではないように、本種もフジバカマの仲間ではまったくありません。牧野富太郎博士によれば赤紫系の花色がフジバカマに喩(たと)えられたとのことですが、色味がまったく異なるので類似性はこれっぽっちも感じられません。誰かがクサフジに対応させて風流気取って命名するもスベったようです。ツルフジバカマ は半日陰または明るい日陰で最もよく育ちますが、直射日光にも耐える可能性があります。果実は春の終わりから初夏に向かって熟します。シーズン後半の高温と多くの日光にさらされるとツルフジバカマ が害を被る可能性があるため、できるだけ日陰を提供することがベストです。
 オギは河原などに生育する多年草です。ススキによく似ていますが、草丈は2mを越えます。種子でも繁殖すしますが、群落の拡大は地下茎で行いますので、土壌は粘土質から砂質であることが必要で、礫を多く含む河原では生育しません。洪水などの増水には耐えることができますが、地下部が長期にわたって水没するような場所にも生育できません。したがって、広い群落を形成する場所は、中流の下部から下流の上部までの範囲であり、通常水位から高い高水敷などです。下流の感潮域では、ヨシ群落よりも高い場所に生育します。日本全国と朝鮮半島・中国大陸に分布しています。ススキとよく似ており、区別に迷うことがありますが、オギは地中に横走する地下茎から地上茎を立ち上げるので、群落を形成していても株立ちすることはありません。茎は堅く、ササの幹のようであり、簡単には引きちぎることができません。葉の幅も広く、花穂もより大型です。
オギは河原などに生育する多年草です。ススキによく似ていますが、草丈は2mを越えます。種子でも繁殖すしますが、群落の拡大は地下茎で行いますので、土壌は粘土質から砂質であることが必要で、礫を多く含む河原では生育しません。洪水などの増水には耐えることができますが、地下部が長期にわたって水没するような場所にも生育できません。したがって、広い群落を形成する場所は、中流の下部から下流の上部までの範囲であり、通常水位から高い高水敷などです。下流の感潮域では、ヨシ群落よりも高い場所に生育します。日本全国と朝鮮半島・中国大陸に分布しています。ススキとよく似ており、区別に迷うことがありますが、オギは地中に横走する地下茎から地上茎を立ち上げるので、群落を形成していても株立ちすることはありません。茎は堅く、ササの幹のようであり、簡単には引きちぎることができません。葉の幅も広く、花穂もより大型です。
 アカハツタケは、傘は径5~15cmで中央がくぼみ,茎は太めで短いです。橙黄色または黄赤色で,傷つけると赤みがかった乳液が出て空気に触れると青変します。秋に,モミ林の地上に生じます。
ヨーロッパ、北米、およびオーストラリアなどの針葉樹林で見られるチチタケの仲間です。学名を直訳すると「美味しいチチタケ」という意味で、その名の通り一般的には食用とされています。スペインなどでは食材として評価の高いキノコですが、同じアカハツタケでも食感や風味が異なる場合があるため、美味しくないという人もいるかもしれません。特に料理界で人気があり、旨味のある味わいのためにさまざまな料理に使用されます。主に秋に入手可能で、採集者や美食家にとって高い価値を持ちます。一般的に消費されていますが、混同を避けるためには正しい同定が必要です。消費前に適切な知識や専門家の助言を確認してください。
アカハツタケは、傘は径5~15cmで中央がくぼみ,茎は太めで短いです。橙黄色または黄赤色で,傷つけると赤みがかった乳液が出て空気に触れると青変します。秋に,モミ林の地上に生じます。
ヨーロッパ、北米、およびオーストラリアなどの針葉樹林で見られるチチタケの仲間です。学名を直訳すると「美味しいチチタケ」という意味で、その名の通り一般的には食用とされています。スペインなどでは食材として評価の高いキノコですが、同じアカハツタケでも食感や風味が異なる場合があるため、美味しくないという人もいるかもしれません。特に料理界で人気があり、旨味のある味わいのためにさまざまな料理に使用されます。主に秋に入手可能で、採集者や美食家にとって高い価値を持ちます。一般的に消費されていますが、混同を避けるためには正しい同定が必要です。消費前に適切な知識や専門家の助言を確認してください。
 ツタノハルコウはヒルガオ科サツマイモ属のつる性一年生草の帰化植物です。葉は3つまたは5つに深裂する点で、よく似たマルバルコウソウと区別できます。葉形は変化が多く、夏から秋にかけて葉腋に花序を出し、直径3 cmほどの五角形で朱色の花をつけます。花冠中央付近も赤く、果実は直径8mmほどで熟すると褐色になります。花後も果柄は曲がらず、果実が上向きのままで成熟し、果柄が曲がるマルバルコウソウと異なります。種子の表面は黒褐色と褐色のまだら模様で銀白色の綿毛に覆われています。ツタノハルコウは中南米原産です。この植物は急速に広がり、再生力が強いため雑草として分類されています。資源を競合するため、庭の周囲の植物に悪影響を与え、成長を妨げたり、野菜作物の収量を減少させたりします。
ツタノハルコウはヒルガオ科サツマイモ属のつる性一年生草の帰化植物です。葉は3つまたは5つに深裂する点で、よく似たマルバルコウソウと区別できます。葉形は変化が多く、夏から秋にかけて葉腋に花序を出し、直径3 cmほどの五角形で朱色の花をつけます。花冠中央付近も赤く、果実は直径8mmほどで熟すると褐色になります。花後も果柄は曲がらず、果実が上向きのままで成熟し、果柄が曲がるマルバルコウソウと異なります。種子の表面は黒褐色と褐色のまだら模様で銀白色の綿毛に覆われています。ツタノハルコウは中南米原産です。この植物は急速に広がり、再生力が強いため雑草として分類されています。資源を競合するため、庭の周囲の植物に悪影響を与え、成長を妨げたり、野菜作物の収量を減少させたりします。
 チカラシバは、北海道から沖縄まで、日本全国に分布するイネ科の多年草で、野原や道端、空き地やグラウンドなど、どこにでも普通に見られます。踏みつけても起き上がり、力の限り抜こうとして容易に抜けないため、チカラシバと命名されました。 ススキに似た大型の雑草で、開花期に群生する黒紫色をした花穂の様子は美しいです。開花は8~10月で、ススキよりやや遅れることが多いです。花は50~70cmほどある花茎の先端に咲き、通常は茶褐色の毛をまといます。花の後には果実ができますが、上記の毛によって他物に付着して拡散されます。葉は線状で長さ30~60cm、幅5~8mmほどになり、尖った先端は垂れ下がります。葉も茎もかなり丈夫で、刈り取りや踏圧に強いですが、晩秋には枯れます。地下にある根は細かな「ヒゲ根」になり、引き抜かれることを阻止しています。
チカラシバは、北海道から沖縄まで、日本全国に分布するイネ科の多年草で、野原や道端、空き地やグラウンドなど、どこにでも普通に見られます。踏みつけても起き上がり、力の限り抜こうとして容易に抜けないため、チカラシバと命名されました。 ススキに似た大型の雑草で、開花期に群生する黒紫色をした花穂の様子は美しいです。開花は8~10月で、ススキよりやや遅れることが多いです。花は50~70cmほどある花茎の先端に咲き、通常は茶褐色の毛をまといます。花の後には果実ができますが、上記の毛によって他物に付着して拡散されます。葉は線状で長さ30~60cm、幅5~8mmほどになり、尖った先端は垂れ下がります。葉も茎もかなり丈夫で、刈り取りや踏圧に強いですが、晩秋には枯れます。地下にある根は細かな「ヒゲ根」になり、引き抜かれることを阻止しています。
 北海道及び青森を除く日本各地の山野に分布するシソ科の落葉低木で、自生はやや湿気の多い場所ですが、庭木として幅広く植栽されています。同属のムラサキシキブとともに平安時代の作家、紫式部にちなんで名付けられました。ムラサキシキブは樹高が3mになる「木」という印象ですが、本種は樹高が1.5m程度に収まり、いわゆる下草として、より広く親しまれています。コムラサキの開花は6~8月で、葉の脇から伸びた花軸に、淡い紅紫の小花が10~20輪が集まって咲きます。雌雄同株で花には1本の雌しべと4本の雄しべがあり、それぞれが花先から突き出ています。果実が紫に熟すのは9~11月で、果実は直径は3ミリほどだが多数が密集し、ムラサキシキブよりも華やかになります。より正確に見分けるためのポイントは果軸の出方で、ムラサキシキブの果軸は葉柄と同じ場所から生じますが、コムラサキは少しずれた位置から生じます。
北海道及び青森を除く日本各地の山野に分布するシソ科の落葉低木で、自生はやや湿気の多い場所ですが、庭木として幅広く植栽されています。同属のムラサキシキブとともに平安時代の作家、紫式部にちなんで名付けられました。ムラサキシキブは樹高が3mになる「木」という印象ですが、本種は樹高が1.5m程度に収まり、いわゆる下草として、より広く親しまれています。コムラサキの開花は6~8月で、葉の脇から伸びた花軸に、淡い紅紫の小花が10~20輪が集まって咲きます。雌雄同株で花には1本の雌しべと4本の雄しべがあり、それぞれが花先から突き出ています。果実が紫に熟すのは9~11月で、果実は直径は3ミリほどだが多数が密集し、ムラサキシキブよりも華やかになります。より正確に見分けるためのポイントは果軸の出方で、ムラサキシキブの果軸は葉柄と同じ場所から生じますが、コムラサキは少しずれた位置から生じます。
 クマシメジはキシメジ科キシメジ属に属する中型のキノコです。日本各地のほか、北半球温帯以北、オーストラリアに分布しています。夏から晩秋、ときに初冬まで、里山の雑木林や、アカマツ、モミなどの針葉樹林内の地上に発生します。子実体は傘と柄からなり、傘の径は4.8cm位です。最初まんじゅう形で、のちに開くと、中高の扁平となります。傘の表面は暗灰色から暗褐色で、しばしば中央部はやや濃色を呈し、黒い綿毛が密生してフェルト状から細かい鱗片状となります。傘裏のヒダは、灰白色から灰色で、やや疎らに配列し、柄に対して湾生または垂生します。
クマシメジはキシメジ科キシメジ属に属する中型のキノコです。日本各地のほか、北半球温帯以北、オーストラリアに分布しています。夏から晩秋、ときに初冬まで、里山の雑木林や、アカマツ、モミなどの針葉樹林内の地上に発生します。子実体は傘と柄からなり、傘の径は4.8cm位です。最初まんじゅう形で、のちに開くと、中高の扁平となります。傘の表面は暗灰色から暗褐色で、しばしば中央部はやや濃色を呈し、黒い綿毛が密生してフェルト状から細かい鱗片状となります。傘裏のヒダは、灰白色から灰色で、やや疎らに配列し、柄に対して湾生または垂生します。
 ヌメリイグチはカサの直径が3~9cmほどのキノコで、その名の通り、湿気が多い場合はカサの表面全体が強い粘液に覆われています。幼菌時はカサの下の面が白くて薄い膜に覆われていますが、成長する過程でカサが開くことでこれは破れていき、稀にカサのフチの部分に付着したままのものも見る事ができます。カサの形は幼い時で半球型で成長すると平らに開きます。色は黄褐色~チョコレート色です。管孔部は直生またはやや垂生し、色は淡いレモン色~黄色を帯びた褐色で、孔口は小さく円形です。ヌメリイグチの柄は長さが5~10cmで、根元から上部まで太さはほぼ同じ。柄の上部には失われやすい膜質のツバがしばしば見られます。また、柄の表面の色は白色~淡いレモン色で、やや濃い色をした細かい点に柄全体が覆われています。肉の色はカサの部分は淡い黄色で、柄の部分はそれよりもやや濃い色をしています
ヌメリイグチはカサの直径が3~9cmほどのキノコで、その名の通り、湿気が多い場合はカサの表面全体が強い粘液に覆われています。幼菌時はカサの下の面が白くて薄い膜に覆われていますが、成長する過程でカサが開くことでこれは破れていき、稀にカサのフチの部分に付着したままのものも見る事ができます。カサの形は幼い時で半球型で成長すると平らに開きます。色は黄褐色~チョコレート色です。管孔部は直生またはやや垂生し、色は淡いレモン色~黄色を帯びた褐色で、孔口は小さく円形です。ヌメリイグチの柄は長さが5~10cmで、根元から上部まで太さはほぼ同じ。柄の上部には失われやすい膜質のツバがしばしば見られます。また、柄の表面の色は白色~淡いレモン色で、やや濃い色をした細かい点に柄全体が覆われています。肉の色はカサの部分は淡い黄色で、柄の部分はそれよりもやや濃い色をしています
 キンエノコロは、ねこじゃらしの名前でおなじみのエノコログサの仲間で、日当たりの良い野原などにごく普通に生えています。夏の終わりから秋にかけて出てくる穂は、エノコログサによく似ていますが、毛は黄金色に輝きます。また、小穂(穂を構成する粒のような部分ひとつひとつ)をルーペで見ると、横しわが目立つのが特徴です。穂の長さは5cm前後のものが多いですが、乾燥著しい場所などでは、2cmから3cm程度と短くなることもあります。また最近は、ホナガキンエノコロと呼ばれる、穂が10cm近くにも達する系統の株が増加傾向にあります。キンエノコロを見つけたら、ちょっとかがんで、太陽にかざすようにキンエノコロの穂の群れを観察してみましょう。穂の剛毛が黄金色に輝いて、その美しさにハッとさせられるはずです。キンエノコロをはじめとするエノコログサの仲間は、穂が成熟すると、小穂は脱落するものの、剛毛は枯れたあともずっと残ります。この枯れ姿も、太陽にかざすと美しく輝きます。
キンエノコロは、ねこじゃらしの名前でおなじみのエノコログサの仲間で、日当たりの良い野原などにごく普通に生えています。夏の終わりから秋にかけて出てくる穂は、エノコログサによく似ていますが、毛は黄金色に輝きます。また、小穂(穂を構成する粒のような部分ひとつひとつ)をルーペで見ると、横しわが目立つのが特徴です。穂の長さは5cm前後のものが多いですが、乾燥著しい場所などでは、2cmから3cm程度と短くなることもあります。また最近は、ホナガキンエノコロと呼ばれる、穂が10cm近くにも達する系統の株が増加傾向にあります。キンエノコロを見つけたら、ちょっとかがんで、太陽にかざすようにキンエノコロの穂の群れを観察してみましょう。穂の剛毛が黄金色に輝いて、その美しさにハッとさせられるはずです。キンエノコロをはじめとするエノコログサの仲間は、穂が成熟すると、小穂は脱落するものの、剛毛は枯れたあともずっと残ります。この枯れ姿も、太陽にかざすと美しく輝きます。