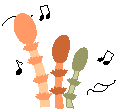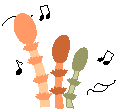
 キンシバイは、中国原産のオトギリソウ科の半常緑低木です。金糸梅の名は、金糸のような長い雄しべと梅のような形の花からつけられました。キンシバイの黄色い花は、初夏に株一面に開花します。刈り込みにも耐え、手入れも簡単なため、公園などの公共空間、街路樹の足元の低木としてなど、日本全国、様々な場所に植栽されています。同じ季節に咲く花は、アジサイを代表としてブルー~紫~ピンクなどの花が多い中で、黄色い花はとても目立つ存在です。キンシバイの花は茎先に数輪の花がつくので開花時はとても華やかです。その花がいっぺんに咲くのではないため、開花期間も長いのが特徴です。キンシバイの種類は斑入り品種などがある他、最近はキンシバイの花の大きさより数倍大きい「ヒペリカム・ヒドコート」が多く普及しています。キンシバイは日当たりを好みますが、半日陰くらいでも十分に育ちます。ただし、日当たりが悪い場所だと花つきが悪くなります。生長力旺盛なため、鉢植えより地植え向きです。
キンシバイは、中国原産のオトギリソウ科の半常緑低木です。金糸梅の名は、金糸のような長い雄しべと梅のような形の花からつけられました。キンシバイの黄色い花は、初夏に株一面に開花します。刈り込みにも耐え、手入れも簡単なため、公園などの公共空間、街路樹の足元の低木としてなど、日本全国、様々な場所に植栽されています。同じ季節に咲く花は、アジサイを代表としてブルー~紫~ピンクなどの花が多い中で、黄色い花はとても目立つ存在です。キンシバイの花は茎先に数輪の花がつくので開花時はとても華やかです。その花がいっぺんに咲くのではないため、開花期間も長いのが特徴です。キンシバイの種類は斑入り品種などがある他、最近はキンシバイの花の大きさより数倍大きい「ヒペリカム・ヒドコート」が多く普及しています。キンシバイは日当たりを好みますが、半日陰くらいでも十分に育ちます。ただし、日当たりが悪い場所だと花つきが悪くなります。生長力旺盛なため、鉢植えより地植え向きです。
 ゴウダソウは、アブラナ科ゴウダソウ属の植物です。別名はルナリア、ギンセンソウ、ギンカソウ等があります。越年生の植物で、一年生植物ないし二年生植物にして、宿根草でもあります。全体に荒い毛が生えています。茎は直立で、高さは30~100センチメートルになり、日本では東京都以南の暖地で30センチメートル程度、東北地方で60~90センチメートルになります。葉は卵型で歯牙縁となり、下部の葉は長い柄を持ち、上部の葉は無柄で両面に白い伏毛が生えています。花は4月から6月にかけて咲き、総状花序となります。通常、色は紅紫色ですが、白色・青色になる個体もあります。花弁は4枚で1.5~2.5センチメートルです。夜間に芳香があり、萼は通常紫色を帯びています。
ゴウダソウは、アブラナ科ゴウダソウ属の植物です。別名はルナリア、ギンセンソウ、ギンカソウ等があります。越年生の植物で、一年生植物ないし二年生植物にして、宿根草でもあります。全体に荒い毛が生えています。茎は直立で、高さは30~100センチメートルになり、日本では東京都以南の暖地で30センチメートル程度、東北地方で60~90センチメートルになります。葉は卵型で歯牙縁となり、下部の葉は長い柄を持ち、上部の葉は無柄で両面に白い伏毛が生えています。花は4月から6月にかけて咲き、総状花序となります。通常、色は紅紫色ですが、白色・青色になる個体もあります。花弁は4枚で1.5~2.5センチメートルです。夜間に芳香があり、萼は通常紫色を帯びています。
 ジャノヒゲは、日本各地の林床などに自生する常緑の多年草です。ヤブランに似ていますが、花は下向きで茎は扁平となり、実が大きくて、秋に熟すと鮮やかなコバルトブルーになります。実は3月ごろまで残り、冬枯れの中で特に目立ちます。細長い葉が地面を覆うように茂り、走出枝を出して広がるので、グラウンドカバープランツとして広く使われています。また、根の一部が紡錘形にふくらみ、これを乾燥させて薬用に使います。水中でも強く、アクアプランツとして熱帯魚の水槽で利用されることがあります。
ジャノヒゲは、日本各地の林床などに自生する常緑の多年草です。ヤブランに似ていますが、花は下向きで茎は扁平となり、実が大きくて、秋に熟すと鮮やかなコバルトブルーになります。実は3月ごろまで残り、冬枯れの中で特に目立ちます。細長い葉が地面を覆うように茂り、走出枝を出して広がるので、グラウンドカバープランツとして広く使われています。また、根の一部が紡錘形にふくらみ、これを乾燥させて薬用に使います。水中でも強く、アクアプランツとして熱帯魚の水槽で利用されることがあります。
 春になると満開のサクラが注目されますが、河川敷や土手、道端などに眼を向ければ、とても地味な土筆(ツクシ)が所々に見られます。ツクシはスギナという植物の一部分ですが、残念ながら花はありません。ツクシは早春に芽を出すスギナの胞子茎です。茎は柔らかな円柱状で退化した「はかま」と呼ばれる葉(葉鞘)が節に付いています。薄茶色で丈は10~15cm程度です。おひたしや佃煮などにしてよく食べた思い出のある方も多いと思います。スギナはトクサ科の耐寒性の多年生草本で、ツクシが枯れた後に芽を出します。草丈は30~40cmになり、中空の円柱状で、節で輪生状に多数分岐します。緑色の葉は小さく鱗片状です。スギナは栄養茎として養分の調達を、ツクシは胞子茎として繁殖をそれぞれ分担しています。和名のスギナは草の形がスギに似ているから、杉菜と名がついたという説や、節のところで抜いて継ぐことができたことから、継ぐ菜から転訛したという説があります。本草綱目には、節と節とが互いに接しているので接続草として登場します。
春になると満開のサクラが注目されますが、河川敷や土手、道端などに眼を向ければ、とても地味な土筆(ツクシ)が所々に見られます。ツクシはスギナという植物の一部分ですが、残念ながら花はありません。ツクシは早春に芽を出すスギナの胞子茎です。茎は柔らかな円柱状で退化した「はかま」と呼ばれる葉(葉鞘)が節に付いています。薄茶色で丈は10~15cm程度です。おひたしや佃煮などにしてよく食べた思い出のある方も多いと思います。スギナはトクサ科の耐寒性の多年生草本で、ツクシが枯れた後に芽を出します。草丈は30~40cmになり、中空の円柱状で、節で輪生状に多数分岐します。緑色の葉は小さく鱗片状です。スギナは栄養茎として養分の調達を、ツクシは胞子茎として繁殖をそれぞれ分担しています。和名のスギナは草の形がスギに似ているから、杉菜と名がついたという説や、節のところで抜いて継ぐことができたことから、継ぐ菜から転訛したという説があります。本草綱目には、節と節とが互いに接しているので接続草として登場します。
 河原や山地の日当たりの良い砂質の土や岩の上、石垣などに黄緑色の群落を作ります。直射日光があたる場所での適応力があることから、苔の生育環境としては厳しいといわれる屋上での緑化素材としても利用されています。但し炎天下では蒸れを起こしやすいので、夏期の水やりは充分な管理が必要です。茎は直立し高さは2~3cm程度で不規則に枝を出し、仮根はあまりつけません。葉は茎にたくさんつけ、先は灰白色で不透明です。植物体全体は黄緑色で、胞子体はあまりつけません。日本各地に分布し、園芸でスナゴケとして扱われる多くがエゾスナゴケ。これにコバノスナゴケやナガエノスナゴケなどが混ざることがあります。寒さに強く剛健。夜露、朝露があたるような開けた場所を好むので、樹木の根元などへの植え付けは避けます。
河原や山地の日当たりの良い砂質の土や岩の上、石垣などに黄緑色の群落を作ります。直射日光があたる場所での適応力があることから、苔の生育環境としては厳しいといわれる屋上での緑化素材としても利用されています。但し炎天下では蒸れを起こしやすいので、夏期の水やりは充分な管理が必要です。茎は直立し高さは2~3cm程度で不規則に枝を出し、仮根はあまりつけません。葉は茎にたくさんつけ、先は灰白色で不透明です。植物体全体は黄緑色で、胞子体はあまりつけません。日本各地に分布し、園芸でスナゴケとして扱われる多くがエゾスナゴケ。これにコバノスナゴケやナガエノスナゴケなどが混ざることがあります。寒さに強く剛健。夜露、朝露があたるような開けた場所を好むので、樹木の根元などへの植え付けは避けます。
 コハコベは3月から9月に白い花を咲かせる小さな雑草です。草丈は10cmから30cmで冬の寒い時期でも緑色の葉をつける上部な特徴があります。集散花序で花をたくさんつけ、コハコベの花弁は10枚あるように見えますが実際には5枚花弁です。コハコベは花がとても小さく、サイズは1cmも満たない大きさです。種子も同じようにとても小さくゴマの粒程度しかないのが特徴です。コハコベは春の七草の1つとして知られているため、食べることができます。おかゆに入れて食べるのがおすすめですが、お浸し、春パスタ、胡麻和えなどもよいでしょう。たけのこや菜の花と一緒に料理に使うのがおすすめです。またコハコベは煎じてお茶にすることもできます。自宅にあるコハコベをお茶にするのもよいでしょう。
コハコベは3月から9月に白い花を咲かせる小さな雑草です。草丈は10cmから30cmで冬の寒い時期でも緑色の葉をつける上部な特徴があります。集散花序で花をたくさんつけ、コハコベの花弁は10枚あるように見えますが実際には5枚花弁です。コハコベは花がとても小さく、サイズは1cmも満たない大きさです。種子も同じようにとても小さくゴマの粒程度しかないのが特徴です。コハコベは春の七草の1つとして知られているため、食べることができます。おかゆに入れて食べるのがおすすめですが、お浸し、春パスタ、胡麻和えなどもよいでしょう。たけのこや菜の花と一緒に料理に使うのがおすすめです。またコハコベは煎じてお茶にすることもできます。自宅にあるコハコベをお茶にするのもよいでしょう。
 ヨーロッパ原産の越年草ですが、世界中に広がっています。国内では、1990年代には既に日本海側を中心に定着しているのが確認されていましたが、現在は全国各地の乾燥した芝地などにごく普通に見られます。早ければ2月ごろから咲きはじめ、梅雨前にはタネを飛ばして枯れます。花が咲き進むとともに茎がのびていきますが、茎につく葉は小さくて数も少なめです。また、株もとの葉は果実期まで残ります。一番の特徴は、葉のつけ根に白い毛がまばらに生えることで、見分けに迷ったときはここを見れば確実です。海外ではヘアリービタークレスと呼ばれ、開花前の葉を摘んで、スープやサラダ、サンドイッチなどの香辛野菜として利用されます。ピリッとした辛味と独特な苦味があります。
ヨーロッパ原産の越年草ですが、世界中に広がっています。国内では、1990年代には既に日本海側を中心に定着しているのが確認されていましたが、現在は全国各地の乾燥した芝地などにごく普通に見られます。早ければ2月ごろから咲きはじめ、梅雨前にはタネを飛ばして枯れます。花が咲き進むとともに茎がのびていきますが、茎につく葉は小さくて数も少なめです。また、株もとの葉は果実期まで残ります。一番の特徴は、葉のつけ根に白い毛がまばらに生えることで、見分けに迷ったときはここを見れば確実です。海外ではヘアリービタークレスと呼ばれ、開花前の葉を摘んで、スープやサラダ、サンドイッチなどの香辛野菜として利用されます。ピリッとした辛味と独特な苦味があります。
 ムスカリは鮮やかな青紫色の花が春の花壇を彩り、チューリップなどほかの花を引き立てる名わき役といってもよい花です。丈夫で育てやすい秋植え球根で、丸い壺形の小花が、ブドウの房のように密集して咲く様子も愛嬌があります。花壇の縁取りやマッス植えなど、ある程度数をまとめて群生させると、さらにそのよさが発揮されます。植えっぱなしでも毎年よく咲き、グラウンドカバーとしても利用しやすく、青いカーペットを敷いたような景観がつくれます。ムスカリ属には40~50種がありますが、M・ボトリオイデスとM・アルメニアカムが最も多く一般的で、濃紫から淡青、白花などいくつかの品種があり、香りの強いものも見られます。そのほか、羽毛のような花が咲くハネムスカリや、花房の上部と下部で色が異なる2色咲きなど、ユニークな種類もあります。
ムスカリは鮮やかな青紫色の花が春の花壇を彩り、チューリップなどほかの花を引き立てる名わき役といってもよい花です。丈夫で育てやすい秋植え球根で、丸い壺形の小花が、ブドウの房のように密集して咲く様子も愛嬌があります。花壇の縁取りやマッス植えなど、ある程度数をまとめて群生させると、さらにそのよさが発揮されます。植えっぱなしでも毎年よく咲き、グラウンドカバーとしても利用しやすく、青いカーペットを敷いたような景観がつくれます。ムスカリ属には40~50種がありますが、M・ボトリオイデスとM・アルメニアカムが最も多く一般的で、濃紫から淡青、白花などいくつかの品種があり、香りの強いものも見られます。そのほか、羽毛のような花が咲くハネムスカリや、花房の上部と下部で色が異なる2色咲きなど、ユニークな種類もあります。
 ホソウリゴケは、コンクリートの隙間や塀などにギンゴケと一緒に生えていることが多く、こちらもタフな苔です。敷きつめられたじゅうたんのような見た目で、ギンゴケよりも濃い緑色が特徴です。雨上がりには緑がより一層きれいになるので、もこもこした絨毯のようで大変魅力的です。ホソウリゴケは小型のハリガネゴケ科に属しており、都市部のコンクリート壁などにも見つけることができる苔です。都市部ではギンゴケやハマキゴケなどと同じような環境に自生しているため乾燥にも強い苔であることがわかると思います。ホソウリゴケはコロニーを作る小型のハリガネゴケ科特有の密生をしていますので蒸れには弱い面を持ち合わせています。寒い季節には青々としたコロニーを形成する一方、暑い季節には乾燥して茶褐色になっている姿を目にすることもあります。
ホソウリゴケは、コンクリートの隙間や塀などにギンゴケと一緒に生えていることが多く、こちらもタフな苔です。敷きつめられたじゅうたんのような見た目で、ギンゴケよりも濃い緑色が特徴です。雨上がりには緑がより一層きれいになるので、もこもこした絨毯のようで大変魅力的です。ホソウリゴケは小型のハリガネゴケ科に属しており、都市部のコンクリート壁などにも見つけることができる苔です。都市部ではギンゴケやハマキゴケなどと同じような環境に自生しているため乾燥にも強い苔であることがわかると思います。ホソウリゴケはコロニーを作る小型のハリガネゴケ科特有の密生をしていますので蒸れには弱い面を持ち合わせています。寒い季節には青々としたコロニーを形成する一方、暑い季節には乾燥して茶褐色になっている姿を目にすることもあります。
 荒れ地や畑のまわりなど、乾燥した日当たりのよい場所に生える越年草です。ふつう結実後に枯れますが、数年程度生き続けることもあります。国内では1954年に小石川植物園(東京)で野生化したという記録があり、現在は同じ仲間のウサギアオイといっしょに生えている姿をいたるところで見かけます。草丈は30センチメートルから60センチメートルくらいで、茎は環境によって地を這うようにのびたり、やや立ちあがり気味にのびたりします。花はウサギアオイよりも大きく直径1センチメートルほど。花びらの長さはがくの長さの2倍から3倍あります。花色は薄いピンクまたは白色です。
荒れ地や畑のまわりなど、乾燥した日当たりのよい場所に生える越年草です。ふつう結実後に枯れますが、数年程度生き続けることもあります。国内では1954年に小石川植物園(東京)で野生化したという記録があり、現在は同じ仲間のウサギアオイといっしょに生えている姿をいたるところで見かけます。草丈は30センチメートルから60センチメートルくらいで、茎は環境によって地を這うようにのびたり、やや立ちあがり気味にのびたりします。花はウサギアオイよりも大きく直径1センチメートルほど。花びらの長さはがくの長さの2倍から3倍あります。花色は薄いピンクまたは白色です。
 身近な場所にごく普通に生え、春の野花としておなじみの存在です。名前のカラスは、果実が熟すとカラスのように真っ黒になることに由来します。葉先が矢筈のようにへこむことから、ヤハズエンドウとも呼ばれます。茎は30センチメートルから50センチメートルの高さになりますが、やわらかいため自分で自分の体を支えられるほどの強さはありません。葉の一部が変形してできた巻きひげを使って、体を支えています。花は赤紫色ですが色の濃淡には個体差があります。白花種はシロバナヤハズエンドウと呼ばれており、市内でもたまに見つかります。葉のつけ根にある托葉には蜜腺があり、蜜を求めてアリがやってきます。またカラスノエンドウはアブラムシがつきやすく、アブラムシを食べるためにテントウムシがたくさん集まります。アリはアブラムシの出す甘露と言う甘い分泌物も大好きです。
身近な場所にごく普通に生え、春の野花としておなじみの存在です。名前のカラスは、果実が熟すとカラスのように真っ黒になることに由来します。葉先が矢筈のようにへこむことから、ヤハズエンドウとも呼ばれます。茎は30センチメートルから50センチメートルの高さになりますが、やわらかいため自分で自分の体を支えられるほどの強さはありません。葉の一部が変形してできた巻きひげを使って、体を支えています。花は赤紫色ですが色の濃淡には個体差があります。白花種はシロバナヤハズエンドウと呼ばれており、市内でもたまに見つかります。葉のつけ根にある托葉には蜜腺があり、蜜を求めてアリがやってきます。またカラスノエンドウはアブラムシがつきやすく、アブラムシを食べるためにテントウムシがたくさん集まります。アリはアブラムシの出す甘露と言う甘い分泌物も大好きです。
 ヨーロッパ原産で、1936年に千葉県で採集され、その後東北地方などで見いだされています。ノハラムラサキ(野原紫)は一般的に、排水の良い土壌で繁栄し、定期的な水やりを好みますが、異なる土壌タイプでも弾力性を示し、様々な条件に耐性を示します。ノハラムラサキ(野原紫)は過度に濡れた状態に敏感であり、根腐れを引き起こす可能性がある過剰な水分を避けるよう特別な注意が必要です。その適応性の高さから、ノハラムラサキ(野原紫)は一般的に手入れが簡単で、手間のかからない植物と考えられており、手入れが少ない植物を求めるガーデナーに最適です。
ヨーロッパ原産で、1936年に千葉県で採集され、その後東北地方などで見いだされています。ノハラムラサキ(野原紫)は一般的に、排水の良い土壌で繁栄し、定期的な水やりを好みますが、異なる土壌タイプでも弾力性を示し、様々な条件に耐性を示します。ノハラムラサキ(野原紫)は過度に濡れた状態に敏感であり、根腐れを引き起こす可能性がある過剰な水分を避けるよう特別な注意が必要です。その適応性の高さから、ノハラムラサキ(野原紫)は一般的に手入れが簡単で、手間のかからない植物と考えられており、手入れが少ない植物を求めるガーデナーに最適です。
 オオヤマチョウチンゴケは日本では珍しいコケの一種です。実をつけた姿は、まるで白鳥が長い首を湾曲させているように見えます。地面や岩、木の樹皮の上で成長し、毛穴から水分を吸収して生きています。鉢植えで楽しむこともできます。オオヤマチョウチンゴケは、その装飾的な特性と育てやすさが評価される手入れの簡単なコケの種です。重要な管理要件は、コケを一貫して湿らせ、自然の林床の生育環境を模倣するために日陰に置くことです。コケを過水にしないように注意し、長時間直射日光にさらさないように特別に注意する必要があります。
オオヤマチョウチンゴケは日本では珍しいコケの一種です。実をつけた姿は、まるで白鳥が長い首を湾曲させているように見えます。地面や岩、木の樹皮の上で成長し、毛穴から水分を吸収して生きています。鉢植えで楽しむこともできます。オオヤマチョウチンゴケは、その装飾的な特性と育てやすさが評価される手入れの簡単なコケの種です。重要な管理要件は、コケを一貫して湿らせ、自然の林床の生育環境を模倣するために日陰に置くことです。コケを過水にしないように注意し、長時間直射日光にさらさないように特別に注意する必要があります。
 ノゲシは日本のみならず世界じゅうに分布する、いわゆる「コスモポリタン種」です。市街地から山地まで環境を問わずに、どこでもごく普通に見られます。草丈は1メートルから2メートルほどになります。同じキク科のアキノノゲシに対して、春に花が目立つことから「ハルノノゲシ」とも呼ばれます。ただノゲシは周年開花性が強く、季節に関係なく1年じゅうダラダラと花を咲かせ、タネを飛ばしています。タネには綿毛がついていて、風であちこちに運ばれていきます。ノゲシの春の若葉は苦味がありますが、タンポポと同じように食べられます。茹でてから水にさらして好みに合うよう苦味を抜きます。茎も皮をむいて、アスパラガス、ルバーブ、フキのように食べられるという情報もあります。
ノゲシは日本のみならず世界じゅうに分布する、いわゆる「コスモポリタン種」です。市街地から山地まで環境を問わずに、どこでもごく普通に見られます。草丈は1メートルから2メートルほどになります。同じキク科のアキノノゲシに対して、春に花が目立つことから「ハルノノゲシ」とも呼ばれます。ただノゲシは周年開花性が強く、季節に関係なく1年じゅうダラダラと花を咲かせ、タネを飛ばしています。タネには綿毛がついていて、風であちこちに運ばれていきます。ノゲシの春の若葉は苦味がありますが、タンポポと同じように食べられます。茹でてから水にさらして好みに合うよう苦味を抜きます。茎も皮をむいて、アスパラガス、ルバーブ、フキのように食べられるという情報もあります。
 山地の林内や草原に生え、長さ30cm、幅15cmにも達するような大きな葉を、次々と出して大株になります。沖縄を除く広域に分布する種で、山地では特段珍しいものではありませんが、千葉県内に限ればかなり稀な植物です。夏に高さ1mにもなる花茎をのばし、薄紫色または白色の花を多数咲かせます。タネは真っ黒で、紙のように薄くて軽く、風によって遠くまで運ばれていきます。ギボウシの仲間は種類問わず、春の新芽は山菜として食用になります。特にオオバギボウシは「うるい」と呼ばれて人気があります。近年は量産されるようになり、春の味覚のひとつとしてスーパーの青果売り場でも簡単に入手できます。
山地の林内や草原に生え、長さ30cm、幅15cmにも達するような大きな葉を、次々と出して大株になります。沖縄を除く広域に分布する種で、山地では特段珍しいものではありませんが、千葉県内に限ればかなり稀な植物です。夏に高さ1mにもなる花茎をのばし、薄紫色または白色の花を多数咲かせます。タネは真っ黒で、紙のように薄くて軽く、風によって遠くまで運ばれていきます。ギボウシの仲間は種類問わず、春の新芽は山菜として食用になります。特にオオバギボウシは「うるい」と呼ばれて人気があります。近年は量産されるようになり、春の味覚のひとつとしてスーパーの青果売り場でも簡単に入手できます。
 アマドコロは、山野に自生する落葉性の多年草です。名前の由来は、太い根茎の形がトコロ(ヤマノイモ)に似ていて、甘みがあることによります。春の新芽は山菜として食用にされます。ただし、果実は有毒です。観賞用に栽培されるのは、主に葉に白い覆輪が入る品種です。清涼感があり、庭やコンテナを明るく彩り、葉はフラワーアレンジメントなどの花材としても広く利用されています。茎は弓なりにやや湾曲し、春にスズランのように下向きの花を咲かせます。地中では太い根茎が枝分かれしながら広がり、群生させると見ごたえがあります。鉢植えでは、草丈低くこぢんまりとした姿になります。
アマドコロは、山野に自生する落葉性の多年草です。名前の由来は、太い根茎の形がトコロ(ヤマノイモ)に似ていて、甘みがあることによります。春の新芽は山菜として食用にされます。ただし、果実は有毒です。観賞用に栽培されるのは、主に葉に白い覆輪が入る品種です。清涼感があり、庭やコンテナを明るく彩り、葉はフラワーアレンジメントなどの花材としても広く利用されています。茎は弓なりにやや湾曲し、春にスズランのように下向きの花を咲かせます。地中では太い根茎が枝分かれしながら広がり、群生させると見ごたえがあります。鉢植えでは、草丈低くこぢんまりとした姿になります。
 ハナダイコン(花大根)は一般的に手入れの簡単な植物と考えられており、湿った排水の良い土壌の中でも栄養を摂取します。ハナダイコン(花大根)には成長するスペースを十分に与えることが重要です。そのため、広がりやすく豊富に自己播種することができるので、範囲化されたエリアでの自然の植物化には有益であり、望ましくない拡散を防ぐためにも特別な注意が必要です。日光も重要な要素です。ハナダイコン(花大根)は日光をたっぷり浴びる場所から半日陰まで栄え、豊かな花を咲かせます。温帯地域に起源を持つハナダイコン(花大根)は、適度な湿度に適応し、水をたくさん含むことなく一定の土壌水分を好みます。
ハナダイコン(花大根)は一般的に手入れの簡単な植物と考えられており、湿った排水の良い土壌の中でも栄養を摂取します。ハナダイコン(花大根)には成長するスペースを十分に与えることが重要です。そのため、広がりやすく豊富に自己播種することができるので、範囲化されたエリアでの自然の植物化には有益であり、望ましくない拡散を防ぐためにも特別な注意が必要です。日光も重要な要素です。ハナダイコン(花大根)は日光をたっぷり浴びる場所から半日陰まで栄え、豊かな花を咲かせます。温帯地域に起源を持つハナダイコン(花大根)は、適度な湿度に適応し、水をたくさん含むことなく一定の土壌水分を好みます。
 シャク属は、主に草本植物と低木を特徴とする被子植物の一群であり、時には樹木も含まれます。傘のような花の房を持ち、さまざまな受粉者を引き寄せることが特徴で、シャク属は複雑な葉と中空の茎を持っています。これらの適応機能により、シャク属は林床から開けた野原までさまざまな環境で繁栄することができ、その構造は耐久性と競争力のある成長を支えます。「シャク」は、セリ科シャク属の多年草で、山菜として利用される植物です。若芽は山菜として食べられ、根も薬用や食用に用いられています。別名コジャク、コシャク、ワイルドチャービル、ヤマニンジン、ノニンジンなどとも呼ばれます。
シャク属は、主に草本植物と低木を特徴とする被子植物の一群であり、時には樹木も含まれます。傘のような花の房を持ち、さまざまな受粉者を引き寄せることが特徴で、シャク属は複雑な葉と中空の茎を持っています。これらの適応機能により、シャク属は林床から開けた野原までさまざまな環境で繁栄することができ、その構造は耐久性と競争力のある成長を支えます。「シャク」は、セリ科シャク属の多年草で、山菜として利用される植物です。若芽は山菜として食べられ、根も薬用や食用に用いられています。別名コジャク、コシャク、ワイルドチャービル、ヤマニンジン、ノニンジンなどとも呼ばれます。
 アオキは常緑性で、しかも耐寒性が強いため、寒い地域では冬の庭を彩る貴重な樹種です。さらに冬には赤くつやのある美しい果実をつけますが、雌花をつける雌株と雄花をつける雄株とに分かれる雌雄異株なので、果実は雌株のみに実ります。花は目立たず、観賞の対象は赤い実と、光沢のある大きな葉です。斑入り葉の品種も多く、ほかの常緑樹ともいろいろな組み合わせが楽しめます。一般的に樹木の新梢は、発生した年は緑色でも翌年には幹と同じような色になります。ところがアオキの枝はその名前が示すように数年間は緑色を保ち続けます。また、耐陰性が高いため、直射日光が当たらない場所でも生育するのでシェードガーデン(日陰の庭)などでもたいへん重宝します。
アオキは常緑性で、しかも耐寒性が強いため、寒い地域では冬の庭を彩る貴重な樹種です。さらに冬には赤くつやのある美しい果実をつけますが、雌花をつける雌株と雄花をつける雄株とに分かれる雌雄異株なので、果実は雌株のみに実ります。花は目立たず、観賞の対象は赤い実と、光沢のある大きな葉です。斑入り葉の品種も多く、ほかの常緑樹ともいろいろな組み合わせが楽しめます。一般的に樹木の新梢は、発生した年は緑色でも翌年には幹と同じような色になります。ところがアオキの枝はその名前が示すように数年間は緑色を保ち続けます。また、耐陰性が高いため、直射日光が当たらない場所でも生育するのでシェードガーデン(日陰の庭)などでもたいへん重宝します。
 あの有名な物語や映画に魔法使いの杖として登場していたのがニワトコという植物です。ニワトコは山野に見られる落葉の低木です。葉は対生で、羽状の複葉は長さ15~30cmになり、花は新芽が出る春に開き、赤い果実を付けます。若葉は食用または民間薬として用いられます。生薬として利用される薬用部位は3箇所あり、茎はセッコツボク(接骨木)、葉はセッコツボクヨウ(接骨木葉)、花はセッコツボクカ(接骨木花)と、それぞれ呼びます。茎と葉は7~8月に取り、花は開花直前に採取し陰干しにして使用します。セッコツボクは粉末にしてオウバクと混ぜ、水を加えて練った物をガーゼに塗り、打撲傷やうち身に用いられます。セッコツボクヨウとセッコツボクカは煎じて服用することで利尿を目的に使われています。
あの有名な物語や映画に魔法使いの杖として登場していたのがニワトコという植物です。ニワトコは山野に見られる落葉の低木です。葉は対生で、羽状の複葉は長さ15~30cmになり、花は新芽が出る春に開き、赤い果実を付けます。若葉は食用または民間薬として用いられます。生薬として利用される薬用部位は3箇所あり、茎はセッコツボク(接骨木)、葉はセッコツボクヨウ(接骨木葉)、花はセッコツボクカ(接骨木花)と、それぞれ呼びます。茎と葉は7~8月に取り、花は開花直前に採取し陰干しにして使用します。セッコツボクは粉末にしてオウバクと混ぜ、水を加えて練った物をガーゼに塗り、打撲傷やうち身に用いられます。セッコツボクヨウとセッコツボクカは煎じて服用することで利尿を目的に使われています。
 ユキノシタ(雪の下)は、本州から四国、九州にかけての渓谷沿いの湿った斜面の岩陰に分布している山野草で、人家周辺にも庭の下草としてよく植えられる常緑の多年草です。半日陰から日陰のやや湿った環境を好みます。ユキノシタ(雪の下)の葉は直径3cm~8cmほどで丸く、葉裏は褐茶色、葉脈上に白い斑が入ります。繁殖力が強く、株元からランナーを伸ばし、株が増えていきます。4月~5月頃に株の中心から20cm~50cmほどの花茎が伸びて白い花が開花し、5枚の花弁のうち上に3枚ある小さな花弁には赤紫色の斑点が入る独特な形状をしています。薬がなかった時代には民間薬として重宝され、食用としても利用されたため、どこの家の井戸周りにもある生活になじみの深い植物でした。現在でも食用のほか、化粧品の素材など、さまざまな用途に利用されています。
ユキノシタ(雪の下)は、本州から四国、九州にかけての渓谷沿いの湿った斜面の岩陰に分布している山野草で、人家周辺にも庭の下草としてよく植えられる常緑の多年草です。半日陰から日陰のやや湿った環境を好みます。ユキノシタ(雪の下)の葉は直径3cm~8cmほどで丸く、葉裏は褐茶色、葉脈上に白い斑が入ります。繁殖力が強く、株元からランナーを伸ばし、株が増えていきます。4月~5月頃に株の中心から20cm~50cmほどの花茎が伸びて白い花が開花し、5枚の花弁のうち上に3枚ある小さな花弁には赤紫色の斑点が入る独特な形状をしています。薬がなかった時代には民間薬として重宝され、食用としても利用されたため、どこの家の井戸周りにもある生活になじみの深い植物でした。現在でも食用のほか、化粧品の素材など、さまざまな用途に利用されています。
 トゲナシムグラはヨーロッパ原産ですが日本にも帰化しており、乾いた草原などに自生します。初夏から秋にかけて小さな白い花を咲かせ、直立する四角い茎には毛がなく、1 m近くまで成長することがあります。多くの種類のハエを引き付けます。トゲナシムグラは、北アメリカの多くの地域、主に東部および西部のアメリカ合衆国とカナダで成長する雑草です。その好む生息地は、野原、芝生、河岸、牧草地、道路脇や鉄道の沿線などです。ニューハンプシャー、ウィスコンシン、ウェストバージニア州では外来種と見なされています。トゲナシムグラの問題点は、フィールド作物と競合して、水分と土壌の栄養分を争うことです。また、動物に有害な毒素が含まれています。拡散を抑制するには、地下根茎系を含む植物を土壌から引き抜くか、種子生成を減少させるために植物を刈り取ります。
トゲナシムグラはヨーロッパ原産ですが日本にも帰化しており、乾いた草原などに自生します。初夏から秋にかけて小さな白い花を咲かせ、直立する四角い茎には毛がなく、1 m近くまで成長することがあります。多くの種類のハエを引き付けます。トゲナシムグラは、北アメリカの多くの地域、主に東部および西部のアメリカ合衆国とカナダで成長する雑草です。その好む生息地は、野原、芝生、河岸、牧草地、道路脇や鉄道の沿線などです。ニューハンプシャー、ウィスコンシン、ウェストバージニア州では外来種と見なされています。トゲナシムグラの問題点は、フィールド作物と競合して、水分と土壌の栄養分を争うことです。また、動物に有害な毒素が含まれています。拡散を抑制するには、地下根茎系を含む植物を土壌から引き抜くか、種子生成を減少させるために植物を刈り取ります。
 オオカワヂシャはヨーロッパからアジア北部原産の帰化植物です。湿地に生え、川岸などに見かけます。多年草で草丈は1mに達します。葉は長楕円形から披針形で、対生し葉柄は無いです。背の低い鋸歯が間隔をあけてつき、両面無毛で、質感はやや厚みがあります。初夏から盛夏にかけて葉腋に花序を出し、白色かやや淡紫色の花をたくさんつけます。良く似た植物に、在来植物のカワヂシャがあり、近年個体数を減らしていると言います。カワヂシャは葉に明瞭な鋸歯がありますが、オオカワヂシャはほとんど全縁に見える点で区別できます。他にも、カワヂシャは花柄が真っ直ぐ斜上しますが、オオカワヂシャは花柄が湾曲して斜上する点でも区別できます。生育条件により一概には言えませんが、オオカワヂシャはその名の通りカワヂシャよりも全体的に大型です。
オオカワヂシャはヨーロッパからアジア北部原産の帰化植物です。湿地に生え、川岸などに見かけます。多年草で草丈は1mに達します。葉は長楕円形から披針形で、対生し葉柄は無いです。背の低い鋸歯が間隔をあけてつき、両面無毛で、質感はやや厚みがあります。初夏から盛夏にかけて葉腋に花序を出し、白色かやや淡紫色の花をたくさんつけます。良く似た植物に、在来植物のカワヂシャがあり、近年個体数を減らしていると言います。カワヂシャは葉に明瞭な鋸歯がありますが、オオカワヂシャはほとんど全縁に見える点で区別できます。他にも、カワヂシャは花柄が真っ直ぐ斜上しますが、オオカワヂシャは花柄が湾曲して斜上する点でも区別できます。生育条件により一概には言えませんが、オオカワヂシャはその名の通りカワヂシャよりも全体的に大型です。
 セイヨウキヅタは、常緑のつる植物であり、高さ20-30メートルに成長し、細根を利用して、崖や壁などによじ登って成長します。また、垂直面以外の場所でも地面を覆うようにして成長します。葉は互生で、長さ50^100mm、葉柄は15^20mmです。葉は若葉のときは掌状で5裂ですが、成葉になると切れ込みが見られず心臓のような形となります。花は、それぞれ直径3^5センチで、小さな緑がかった黄色をしています。そして蜜が豊富にあり、晩夏から晩秋までのミツバチや他の昆虫のための重要な食料源となっています。果実は直径6^8mmで、冬の終わり頃に橙黄色から紫黒色に成熟します。人間にとっては有毒ですが、多くの鳥にとっては重要な食料です。果実には種子が5個あり、鳥に食べられることにより、広範囲に種子が散布されます。
セイヨウキヅタは、常緑のつる植物であり、高さ20-30メートルに成長し、細根を利用して、崖や壁などによじ登って成長します。また、垂直面以外の場所でも地面を覆うようにして成長します。葉は互生で、長さ50^100mm、葉柄は15^20mmです。葉は若葉のときは掌状で5裂ですが、成葉になると切れ込みが見られず心臓のような形となります。花は、それぞれ直径3^5センチで、小さな緑がかった黄色をしています。そして蜜が豊富にあり、晩夏から晩秋までのミツバチや他の昆虫のための重要な食料源となっています。果実は直径6^8mmで、冬の終わり頃に橙黄色から紫黒色に成熟します。人間にとっては有毒ですが、多くの鳥にとっては重要な食料です。果実には種子が5個あり、鳥に食べられることにより、広範囲に種子が散布されます。
 ハナニラは、道端や花壇に植えっぱなしにしておいても、春に藤青色からピンク、白の星形の花をよく咲かせる、非常に丈夫で手間いらずな植物です。葉や球根を傷つけると、その名のとおりネギやニラのようなにおいがします。イフェイオン属は南アメリカに約25種が分布する球根植物で、最もよく目にするのはユニフロルムで、日本ではハナニラと呼ばれています。近年は早春から黄色い花を咲かせる近縁の黄花ハナニラや、晩秋から初冬に白い花を咲かせるパルビフローラなども手に入るようになり、開花期の異なる種を組み合わせて栽培することで、長期間楽しめるようになっています。秋に球根で入手できるほか、ポリポットに植えられた苗でも流通しています。
ハナニラは、道端や花壇に植えっぱなしにしておいても、春に藤青色からピンク、白の星形の花をよく咲かせる、非常に丈夫で手間いらずな植物です。葉や球根を傷つけると、その名のとおりネギやニラのようなにおいがします。イフェイオン属は南アメリカに約25種が分布する球根植物で、最もよく目にするのはユニフロルムで、日本ではハナニラと呼ばれています。近年は早春から黄色い花を咲かせる近縁の黄花ハナニラや、晩秋から初冬に白い花を咲かせるパルビフローラなども手に入るようになり、開花期の異なる種を組み合わせて栽培することで、長期間楽しめるようになっています。秋に球根で入手できるほか、ポリポットに植えられた苗でも流通しています。
 オノマンネングサは、雑草としては比較的管理しやすいとされていますが、広範囲に増える場合は除草対策が必要になります。水はけの良い場所を好むため、水はけの悪い場所で増える場合は、植え替えや水やり頻度の調整などを検討すると良いでしょう。オノマンネングサ(雄の万年草)は、日本各地の岩の上や石垣でよく見られ、星のような形の黄色い花を多数咲かせます。暑さや乾燥に強いだけではなく、耐寒性もあり大変丈夫であるため、土地を覆う被覆植物として植えられます。オノマンネングサ(雄の万年草)は、多肉植物マンネングサの仲間です。メノマンネングサ(雌の万年草)に対して大きいことから「雄」と名付けられたようです。メノマンネングサは葉っぱが太く短いことから見て、葉っぱが雄だということなのでしょう。
オノマンネングサは、雑草としては比較的管理しやすいとされていますが、広範囲に増える場合は除草対策が必要になります。水はけの良い場所を好むため、水はけの悪い場所で増える場合は、植え替えや水やり頻度の調整などを検討すると良いでしょう。オノマンネングサ(雄の万年草)は、日本各地の岩の上や石垣でよく見られ、星のような形の黄色い花を多数咲かせます。暑さや乾燥に強いだけではなく、耐寒性もあり大変丈夫であるため、土地を覆う被覆植物として植えられます。オノマンネングサ(雄の万年草)は、多肉植物マンネングサの仲間です。メノマンネングサ(雌の万年草)に対して大きいことから「雄」と名付けられたようです。メノマンネングサは葉っぱが太く短いことから見て、葉っぱが雄だということなのでしょう。
 市内の山林にはアケビとミツバアケビの2種類があり、一緒に生えていることも珍しくありません。両者の間で自然交雑がおき、生まれたのがこのゴヨウアケビです。比較的交雑しやすいのか、ゴヨウアケビは雑種でありながらそこそこの頻度で見ることができます。アケビとミツバアケビ、両方を足して2で割ったような姿をしています。小葉の枚数は3枚から5枚で、同じ株の中でも枚数の異なる葉がいろいろと混じる傾向があります。また葉の縁はうねうねと波打つような切れ込みがはいります。ただアケビも若葉は縁が波打って紛らわしいことがあるため、判別するときは成熟した葉も確認したいところです。春に開花しますがふつう結実しません。花はミツバアケビのような色合いですが、それに比べると若干淡めです。
市内の山林にはアケビとミツバアケビの2種類があり、一緒に生えていることも珍しくありません。両者の間で自然交雑がおき、生まれたのがこのゴヨウアケビです。比較的交雑しやすいのか、ゴヨウアケビは雑種でありながらそこそこの頻度で見ることができます。アケビとミツバアケビ、両方を足して2で割ったような姿をしています。小葉の枚数は3枚から5枚で、同じ株の中でも枚数の異なる葉がいろいろと混じる傾向があります。また葉の縁はうねうねと波打つような切れ込みがはいります。ただアケビも若葉は縁が波打って紛らわしいことがあるため、判別するときは成熟した葉も確認したいところです。春に開花しますがふつう結実しません。花はミツバアケビのような色合いですが、それに比べると若干淡めです。
 アザミ(薊)とは、キク科アザミ属に属する植物の総称です。葉にトゲがあり、そのトゲが動物に食べられるのを防ぐ効果があります。また、アザミはスコットランドの国花として知られており、花言葉には「厳しさ」や「独立」などが付けられています。アザミの名称は、古語の「あざむく(欺く、驚く)」に由来するとされ、美しい花だと思って触れたらトゲで驚かされることから、こう呼ばれたという説があります.アザミは、薬草としても利用され、根を乾燥させたものは「薊(あざみ)」と呼ばれる生薬として、健胃、利尿、解毒などの効果があるとされています. また、アザミの葉も食用として利用でき、様々な料理に用いられます.アザミは、キク科の植物で、世界中に約300種存在し、日本にはそのうちの約1/3が分布しています. アザミは、葉の形や大きさ、花の色など、種類によって様々な特徴を持っています.
アザミ(薊)とは、キク科アザミ属に属する植物の総称です。葉にトゲがあり、そのトゲが動物に食べられるのを防ぐ効果があります。また、アザミはスコットランドの国花として知られており、花言葉には「厳しさ」や「独立」などが付けられています。アザミの名称は、古語の「あざむく(欺く、驚く)」に由来するとされ、美しい花だと思って触れたらトゲで驚かされることから、こう呼ばれたという説があります.アザミは、薬草としても利用され、根を乾燥させたものは「薊(あざみ)」と呼ばれる生薬として、健胃、利尿、解毒などの効果があるとされています. また、アザミの葉も食用として利用でき、様々な料理に用いられます.アザミは、キク科の植物で、世界中に約300種存在し、日本にはそのうちの約1/3が分布しています. アザミは、葉の形や大きさ、花の色など、種類によって様々な特徴を持っています.
 ナガミヒナゲシは、ヨーロッパ地中海沿岸を原産とするケシ科の一年草です。名前のとおり、ヒナゲシ、ポピーと似たオレンジ色の花を4月から5月に咲かせます。一つの株から最大で約15万粒程度の種子ができ、繁殖力も強いことが特徴で、根から他の植物の生育を妨げる成分を含んだ物質を出すため、周辺の他の植物の生育に影響を与える植物です。ナガミヒナゲシの茎や葉にはアルカロイド性の有毒物質が含まれています。害虫や動物から身を守るための植物毒であるため、素手で茎に触ったり、折ったりすると手がかぶれるおそれがあります。素手では、触らないようにしてください。ナガミヒナゲシは、環境省が駆除対象として指定する「特定外来生物」には該当しませんが、自宅の庭など管理地内で見つけた場合には、できる範囲で駆除していただくよう、ご協力をお願いします。
ナガミヒナゲシは、ヨーロッパ地中海沿岸を原産とするケシ科の一年草です。名前のとおり、ヒナゲシ、ポピーと似たオレンジ色の花を4月から5月に咲かせます。一つの株から最大で約15万粒程度の種子ができ、繁殖力も強いことが特徴で、根から他の植物の生育を妨げる成分を含んだ物質を出すため、周辺の他の植物の生育に影響を与える植物です。ナガミヒナゲシの茎や葉にはアルカロイド性の有毒物質が含まれています。害虫や動物から身を守るための植物毒であるため、素手で茎に触ったり、折ったりすると手がかぶれるおそれがあります。素手では、触らないようにしてください。ナガミヒナゲシは、環境省が駆除対象として指定する「特定外来生物」には該当しませんが、自宅の庭など管理地内で見つけた場合には、できる範囲で駆除していただくよう、ご協力をお願いします。
 ヨーロッパ原産で、観賞用に栽培され、湿ったところに野生化しています。とくに北海道や長野県に多いです。茎は高さ20〜50cmになり、しばしば基部から長い匐枝をだします。下部の葉は柄があって倒披針形です。上部の葉は無柄で長楕円形。枝先にサソリ形花序をだし、直径6〜9mmの花を次々に開きます。花冠は淡青紫色で、のどに黄色の鱗片があります。花期は5〜7月(野に咲く花)。昔、ルドルフとベルタという恋人同士が暖かい春のタべ、ドナウ川のほとりを散策していました。乙女のベルタは、河岸に咲く青い小さな花を見つけた。彼女は、若者のルドルフにその可憐な花を採って欲しいと頼みました。彼は、岸に降りていきその花を手折った瞬間、足を滑らせ急流に巻き込まれてしまいました。ルドルフは、最後の力を尽くして、花を岸辺に投げ、「私を忘れないで」と叫び、流れに飲まれていってしまいました。
ヨーロッパ原産で、観賞用に栽培され、湿ったところに野生化しています。とくに北海道や長野県に多いです。茎は高さ20〜50cmになり、しばしば基部から長い匐枝をだします。下部の葉は柄があって倒披針形です。上部の葉は無柄で長楕円形。枝先にサソリ形花序をだし、直径6〜9mmの花を次々に開きます。花冠は淡青紫色で、のどに黄色の鱗片があります。花期は5〜7月(野に咲く花)。昔、ルドルフとベルタという恋人同士が暖かい春のタべ、ドナウ川のほとりを散策していました。乙女のベルタは、河岸に咲く青い小さな花を見つけた。彼女は、若者のルドルフにその可憐な花を採って欲しいと頼みました。彼は、岸に降りていきその花を手折った瞬間、足を滑らせ急流に巻き込まれてしまいました。ルドルフは、最後の力を尽くして、花を岸辺に投げ、「私を忘れないで」と叫び、流れに飲まれていってしまいました。
 カラマツはマツ科の中では珍しい、落葉性の高木です。本州の宮城・新潟県以南から中部山岳地帯に自然分布しています。火山地帯に生育することが多く、荒れ地・痩せ地・湿地に生育し、パイオニア的性格を持つ-っています。本来の生育地は亜高山帯からブナ帯上部であると考えられます。各地の高海抜地域にに広く植林されています。樹高は30m近くになり、直径も1mを越えるものがあります。葉は線形で長さ2~3cmです。短枝では葉は円形に配列され、枝先などの長枝では螺旋状に配列されています。花は5月頃に咲きます。和名は葉の付いた様子が唐文様に似ているとの意味であり、落葉するので落葉松、富士山に生育するのでフジマツの別名もあります。秋には黄葉し、春は新緑が美しいです。
カラマツはマツ科の中では珍しい、落葉性の高木です。本州の宮城・新潟県以南から中部山岳地帯に自然分布しています。火山地帯に生育することが多く、荒れ地・痩せ地・湿地に生育し、パイオニア的性格を持つ-っています。本来の生育地は亜高山帯からブナ帯上部であると考えられます。各地の高海抜地域にに広く植林されています。樹高は30m近くになり、直径も1mを越えるものがあります。葉は線形で長さ2~3cmです。短枝では葉は円形に配列され、枝先などの長枝では螺旋状に配列されています。花は5月頃に咲きます。和名は葉の付いた様子が唐文様に似ているとの意味であり、落葉するので落葉松、富士山に生育するのでフジマツの別名もあります。秋には黄葉し、春は新緑が美しいです。
 セイヨウジュウニヒトエは、シソ科キランソウ属の常緑多年草で、別名アジュガやセイヨウキランソウとも呼ばれます。匍匐枝を伸ばしてマット状に広がるのが特徴で、春から夏にかけて穂状の花序に小さな青紫色の花を咲かせます。葉はロゼット状に付き、縁に波状の歯牙があります。北ヨーロッパ原産で、観賞用に栽培されていましたが、1970年頃から逸出して野生化することが認められだしました。水田の畦畔を被うために導入されていますが、各地で逸出しています。常緑で秋から春にかけて全体に紫色を帯びます。開花時期に地上を這う茎を伸ばし、節から発根して新しい個体を生じてマット状に群生します。四角形で高さ30cmほどの花茎を伸ばし、対生する葉状の苞の腋に、長さ1cmほどの青紫色〜白色の唇形花を3〜10個穂状につけます。花期は春〜夏です。
セイヨウジュウニヒトエは、シソ科キランソウ属の常緑多年草で、別名アジュガやセイヨウキランソウとも呼ばれます。匍匐枝を伸ばしてマット状に広がるのが特徴で、春から夏にかけて穂状の花序に小さな青紫色の花を咲かせます。葉はロゼット状に付き、縁に波状の歯牙があります。北ヨーロッパ原産で、観賞用に栽培されていましたが、1970年頃から逸出して野生化することが認められだしました。水田の畦畔を被うために導入されていますが、各地で逸出しています。常緑で秋から春にかけて全体に紫色を帯びます。開花時期に地上を這う茎を伸ばし、節から発根して新しい個体を生じてマット状に群生します。四角形で高さ30cmほどの花茎を伸ばし、対生する葉状の苞の腋に、長さ1cmほどの青紫色〜白色の唇形花を3〜10個穂状につけます。花期は春〜夏です。
 クルマバソウ(ウッドラフ)は、5月~7月に星のような形の白い小さな花を咲かせるアカネ科の多年草のハーブで、山林の多少湿り気のあるところに自生しています。車葉草という名は、車輪のような葉の付き方をしていることに由来します。這うように横に広がりながら地下茎で広がるためグランドカバーとして利用され、地植えにすると初夏の開花時は小さい花ながら美しい光景になります。車輪のような形の明るい緑色の葉は、花のない時期も周囲を明るくしてくれます。また、性質を生かしてハンギングバスケットや寄せ植えの材料にしても周囲の草花を引き立ててくれる存在になります。
クルマバソウ(ウッドラフ)は、5月~7月に星のような形の白い小さな花を咲かせるアカネ科の多年草のハーブで、山林の多少湿り気のあるところに自生しています。車葉草という名は、車輪のような葉の付き方をしていることに由来します。這うように横に広がりながら地下茎で広がるためグランドカバーとして利用され、地植えにすると初夏の開花時は小さい花ながら美しい光景になります。車輪のような形の明るい緑色の葉は、花のない時期も周囲を明るくしてくれます。また、性質を生かしてハンギングバスケットや寄せ植えの材料にしても周囲の草花を引き立ててくれる存在になります。
 ヒマラヤエンゴサクは、自然の森林生息地を真似た、涼しい湿った環境と日陰を好むようです。根腐れを避けるために、良く排水された土壌を確保し、水をためすぎないように一貫した湿度を保つことが重要です。成長期には軽く肥料を施すことで、ヒマラヤエンゴサクの花と葉の健全さを促進することができます。原生林の中で繁栄するヒマラヤエンゴサクは、日陰下で見られる一貫した湿気に慣れています。この種は均等に湿った土壌条件を好み、成長後には穏やかな耐乾性を示します。自然な生息地を模倣するために、ヒマラヤエンゴサクは週に一度の水やりを必要とします。主に屋外で栽培されるヒマラヤエンゴサクは、生育シーズンの降水パターンに敏感であり、灌漑需要と開花ポテンシャルに大きく影響を与えます。
ヒマラヤエンゴサクは、自然の森林生息地を真似た、涼しい湿った環境と日陰を好むようです。根腐れを避けるために、良く排水された土壌を確保し、水をためすぎないように一貫した湿度を保つことが重要です。成長期には軽く肥料を施すことで、ヒマラヤエンゴサクの花と葉の健全さを促進することができます。原生林の中で繁栄するヒマラヤエンゴサクは、日陰下で見られる一貫した湿気に慣れています。この種は均等に湿った土壌条件を好み、成長後には穏やかな耐乾性を示します。自然な生息地を模倣するために、ヒマラヤエンゴサクは週に一度の水やりを必要とします。主に屋外で栽培されるヒマラヤエンゴサクは、生育シーズンの降水パターンに敏感であり、灌漑需要と開花ポテンシャルに大きく影響を与えます。
 ヒメフウロは本州や四国の一部の石灰岩地に自生しています。全草に特有の臭気があり、軟らかい開出した白毛がまばらにあります。茎は基部で分枝して、高さ20〜60cmになります。葉は互生し、長さ3cm、幅5cmほどで、深く3全裂し、小葉はさらに羽状に深裂します。茎の上部の葉は羽状葉状になります。葉腋から長い花序を伸ばして、直径15mmほどの淡紅色の花を1〜2個つけます。花弁には2本、濃色の筋があります。雄しべの葯は赤です。果実は長さ2cmほどの嘴状となります。古くなった葉や、結実期に入った全草は赤く染まることが多いです。最近、帰化したと思われるものが市街地に見られるようになりました。ヒメフウロは、葉をつぶすと独特の臭いがあり、塩を焼いたような臭いとも形容されます。別名「シオヤキソウ」は、この臭いが由来です。
ヒメフウロは本州や四国の一部の石灰岩地に自生しています。全草に特有の臭気があり、軟らかい開出した白毛がまばらにあります。茎は基部で分枝して、高さ20〜60cmになります。葉は互生し、長さ3cm、幅5cmほどで、深く3全裂し、小葉はさらに羽状に深裂します。茎の上部の葉は羽状葉状になります。葉腋から長い花序を伸ばして、直径15mmほどの淡紅色の花を1〜2個つけます。花弁には2本、濃色の筋があります。雄しべの葯は赤です。果実は長さ2cmほどの嘴状となります。古くなった葉や、結実期に入った全草は赤く染まることが多いです。最近、帰化したと思われるものが市街地に見られるようになりました。ヒメフウロは、葉をつぶすと独特の臭いがあり、塩を焼いたような臭いとも形容されます。別名「シオヤキソウ」は、この臭いが由来です。
 カンシロギク(寒白菊)またはノースポールギクは、キク科フランスギク属の半耐寒性多年草です。しかし、高温多湿に極端に弱いため、日本では一年草として扱われています。和名の由来は、花付がよく株全体を真っ白に覆うように見えるところが北極を連想させることによります。「ノースポール」はサカタのタネの商品名ですが、種苗登録などはされていないため、一般名として定着しています。旧学名またはシノニムの「クリサンセマム・パルドスム」と表記されることもあります。高温多湿に極端に弱いため、日本では6月を過ぎると急速に枯れ始め、一年草として扱われています。日本へは、1960年代に輸入されました。カンシロギクはノースポールギクとも呼ばれますが、これは花付きが良く株全体を真っ白に覆うように見えるところが北極を連想させることからつけられた名です。
カンシロギク(寒白菊)またはノースポールギクは、キク科フランスギク属の半耐寒性多年草です。しかし、高温多湿に極端に弱いため、日本では一年草として扱われています。和名の由来は、花付がよく株全体を真っ白に覆うように見えるところが北極を連想させることによります。「ノースポール」はサカタのタネの商品名ですが、種苗登録などはされていないため、一般名として定着しています。旧学名またはシノニムの「クリサンセマム・パルドスム」と表記されることもあります。高温多湿に極端に弱いため、日本では6月を過ぎると急速に枯れ始め、一年草として扱われています。日本へは、1960年代に輸入されました。カンシロギクはノースポールギクとも呼ばれますが、これは花付きが良く株全体を真っ白に覆うように見えるところが北極を連想させることからつけられた名です。
 オオアラセイトウ(ムラサキハナナ)は、アブラナ科の一年草。発芽した状態で冬を越し、春に開花する越年草です。すみれ色とも言える青みがかった紫色の花が可愛らしく、群生すると野原一面を紫に変えます。園芸種もあり、種や苗も流通していますが、繁殖力が強いので野草のように群生している姿をよく見かけます。春になると河原や街中の空き地、道路脇など、身近なところで出会える花の一つです。オオアラセイトウ(ムラサキハナナ)は、元は外国から入ってきたものが野生化した帰化植物です。帰化植物と言うと繁殖力が強いなどと敬遠されがちですが、このムラサキハナナ(オオアラセイトウ)は見た目の可愛らしさもあってか、増えるに任せて繁茂している様子をよく目にします。
オオアラセイトウ(ムラサキハナナ)は、アブラナ科の一年草。発芽した状態で冬を越し、春に開花する越年草です。すみれ色とも言える青みがかった紫色の花が可愛らしく、群生すると野原一面を紫に変えます。園芸種もあり、種や苗も流通していますが、繁殖力が強いので野草のように群生している姿をよく見かけます。春になると河原や街中の空き地、道路脇など、身近なところで出会える花の一つです。オオアラセイトウ(ムラサキハナナ)は、元は外国から入ってきたものが野生化した帰化植物です。帰化植物と言うと繁殖力が強いなどと敬遠されがちですが、このムラサキハナナ(オオアラセイトウ)は見た目の可愛らしさもあってか、増えるに任せて繁茂している様子をよく目にします。
 明治時代の終わりに北海道で発見されたことから、エゾノギシギシと名がつきますが、在来種ではなくヨーロッパから来た外来種です。特に寒さに強いことから、山岳地帯に多く入んでどんどん増え、現地の希少な植物群落を脅かしています。市内でも堤防周辺や牧草地などに多く見られます。ヒロハギシギシと言う別名もあるとおり、株もとにつく葉はとても大きく幅が広いのが特徴です。また葉の裏側をさわるとザラザラと感じます。これは葉裏の葉脈上に毛のような細かい突起がびっしりとあるためです。葉脈や茎はしばしば赤くなります。果実期の花被片は縁がギザギザして刺のようになっています。粒体は3枚の花被片のうち1枚にだけあります。果実が成熟してくると、穂全体が赤茶色に色づきます。
明治時代の終わりに北海道で発見されたことから、エゾノギシギシと名がつきますが、在来種ではなくヨーロッパから来た外来種です。特に寒さに強いことから、山岳地帯に多く入んでどんどん増え、現地の希少な植物群落を脅かしています。市内でも堤防周辺や牧草地などに多く見られます。ヒロハギシギシと言う別名もあるとおり、株もとにつく葉はとても大きく幅が広いのが特徴です。また葉の裏側をさわるとザラザラと感じます。これは葉裏の葉脈上に毛のような細かい突起がびっしりとあるためです。葉脈や茎はしばしば赤くなります。果実期の花被片は縁がギザギザして刺のようになっています。粒体は3枚の花被片のうち1枚にだけあります。果実が成熟してくると、穂全体が赤茶色に色づきます。
 コメツブツメクサ(米粒詰草)は、日当たりのよい乾燥した場所を好む1年草です。草丈は10センチメートルから30センチメートルほどですが、株元から盛んに枝分かれをします。また、多数の株がびっしりと密集するように生える傾向があり、その姿はまるでマットを広げたかのように見えます。春から夏にかけて、黄色い花を次々と咲かせます。花は5個から20個ずつ丸く集まってつき、直径1センチメートル程度の「黄色い花の球」となります。これがまるで米粒のように見えることが名前の由来となっています。そのほか、コゴメツメクサ、キバナツメクサなどの別名もあります。
コメツブツメクサ(米粒詰草)は、日当たりのよい乾燥した場所を好む1年草です。草丈は10センチメートルから30センチメートルほどですが、株元から盛んに枝分かれをします。また、多数の株がびっしりと密集するように生える傾向があり、その姿はまるでマットを広げたかのように見えます。春から夏にかけて、黄色い花を次々と咲かせます。花は5個から20個ずつ丸く集まってつき、直径1センチメートル程度の「黄色い花の球」となります。これがまるで米粒のように見えることが名前の由来となっています。そのほか、コゴメツメクサ、キバナツメクサなどの別名もあります。
 ニシキギ(錦木)とは、ニシキギ科ニシキギ属の落葉低木で、その名の通り絹織物の錦のように紅葉が特に美しい樹木です。枝にコルク質の矢羽根形の翼をもつのも特徴です。 日当たりよい場所を好みますが、耐陰性もあり日陰でも育ちます。 生長が早く育てやすい木です。ニシキギはその名のごとく「錦」を思わす秋の紅葉の美しさが最大の魅力です。小さな果実は秋の深まりとともに熟して果皮が裂ける蒴果で、晩秋に橙赤色の仮種皮で覆われたタネが垂れ下がる姿もかわいらしいものです。また、緑色の若い枝には浅い土色でコルク質の翼(よく)がある特徴的な枝をもつため、生け花の花材としても好まれます。芽吹きもよく刈り込みにも耐えるので、仕立てものや生け垣としても人気があります。
ニシキギ(錦木)とは、ニシキギ科ニシキギ属の落葉低木で、その名の通り絹織物の錦のように紅葉が特に美しい樹木です。枝にコルク質の矢羽根形の翼をもつのも特徴です。 日当たりよい場所を好みますが、耐陰性もあり日陰でも育ちます。 生長が早く育てやすい木です。ニシキギはその名のごとく「錦」を思わす秋の紅葉の美しさが最大の魅力です。小さな果実は秋の深まりとともに熟して果皮が裂ける蒴果で、晩秋に橙赤色の仮種皮で覆われたタネが垂れ下がる姿もかわいらしいものです。また、緑色の若い枝には浅い土色でコルク質の翼(よく)がある特徴的な枝をもつため、生け花の花材としても好まれます。芽吹きもよく刈り込みにも耐えるので、仕立てものや生け垣としても人気があります。
 シダ植物は、コケ植物のように花の咲かない「隠花植物」です。シダ類と言うと、ワラビやゼンマイのように山間の斜面などで採れる食用の植物を想像しますが、そのしっとりとした雰囲気から観賞用として重宝されており、園芸ショップでも木性シダ類の幹やゼンマイ類の根塊などの植物が数多く広く販売されています。シダが地球上に誕生したのは4億1千年前頃と言われています。シダは、もともと水中生活をしていましたが、地球の変化で陸上生活が必要になってきたため、水分を地表に運ぶ維管束を発達させながら、体の組織を分化し、丈夫な組織をつくりあげてきました。そのためシダは、植物の体を支えたり、体の各部に水分や養分を運んだりする維管束が大きな特徴となっています。また、「胞子で繁殖する」「胞子体は配属体(前葉体)に比べて著しく大きく発達している」「前葉体は小さく、胞子体から独立して生活する」といった特徴をもつ植物をシダと呼んでいます。
シダ植物は、コケ植物のように花の咲かない「隠花植物」です。シダ類と言うと、ワラビやゼンマイのように山間の斜面などで採れる食用の植物を想像しますが、そのしっとりとした雰囲気から観賞用として重宝されており、園芸ショップでも木性シダ類の幹やゼンマイ類の根塊などの植物が数多く広く販売されています。シダが地球上に誕生したのは4億1千年前頃と言われています。シダは、もともと水中生活をしていましたが、地球の変化で陸上生活が必要になってきたため、水分を地表に運ぶ維管束を発達させながら、体の組織を分化し、丈夫な組織をつくりあげてきました。そのためシダは、植物の体を支えたり、体の各部に水分や養分を運んだりする維管束が大きな特徴となっています。また、「胞子で繁殖する」「胞子体は配属体(前葉体)に比べて著しく大きく発達している」「前葉体は小さく、胞子体から独立して生活する」といった特徴をもつ植物をシダと呼んでいます。
 北海道南西部~東北地方の日本海側に分布するスイカズラ科の落葉低木w\です。山地や海岸沿いの林内に自生しますが、花や果実を観賞するため、庭園や公園にも植栽されています。キンギンボク(金銀木)は一般的に最小限の手入れが必要な堅牢かつ適応力のある植物です。根腐れを防ぐために水はけのよい土壌を確保し、最適な成長のために日当たりの良い場所から日陰まで適切に提供する必要があります。キンギンボク(金銀木)はいくつかの地域で繁殖力がありすぎるため、その拡散を制御することに特に注意を払うべきです。植物の形を整えるために定期的に剪定し、過度な繁殖を抑制することが推奨されます。
北海道南西部~東北地方の日本海側に分布するスイカズラ科の落葉低木w\です。山地や海岸沿いの林内に自生しますが、花や果実を観賞するため、庭園や公園にも植栽されています。キンギンボク(金銀木)は一般的に最小限の手入れが必要な堅牢かつ適応力のある植物です。根腐れを防ぐために水はけのよい土壌を確保し、最適な成長のために日当たりの良い場所から日陰まで適切に提供する必要があります。キンギンボク(金銀木)はいくつかの地域で繁殖力がありすぎるため、その拡散を制御することに特に注意を払うべきです。植物の形を整えるために定期的に剪定し、過度な繁殖を抑制することが推奨されます。
 モッコクモドキ(木斛擬)は、バラ科の常緑低木で、4月に白い花を咲かせ、秋に褐色で球形の果実をつけます。モッコク(木斛)に似ていますが、葉の形状や葉柄の色などで見分けられます。モッコクモドキは、バラ科シャリンバイ属の常緑低木で、別名シャリンバイとも呼ばれます。4月頃に白い梅のような花を咲かせ、秋には小さな実をつけます。皮や根にはタンニンが含まれており、染料として利用されることもあります。モッコクモドキの花言葉は、主に「そよ風の心地よさ」、「純真」、「愛の告白」などがあります。また、モッコク(木斛)の花言葉は「人情家」で、これは良縁を願う意味も含まれています。
モッコクモドキ(木斛擬)は、バラ科の常緑低木で、4月に白い花を咲かせ、秋に褐色で球形の果実をつけます。モッコク(木斛)に似ていますが、葉の形状や葉柄の色などで見分けられます。モッコクモドキは、バラ科シャリンバイ属の常緑低木で、別名シャリンバイとも呼ばれます。4月頃に白い梅のような花を咲かせ、秋には小さな実をつけます。皮や根にはタンニンが含まれており、染料として利用されることもあります。モッコクモドキの花言葉は、主に「そよ風の心地よさ」、「純真」、「愛の告白」などがあります。また、モッコク(木斛)の花言葉は「人情家」で、これは良縁を願う意味も含まれています。
 江戸時代に渡来したマメ科の植物です。茎は断面が四角、這い、やや斜上し、毛があります。葉は3小葉で、小葉は長さ約15㎜の広倒卵形、先端はやや凹頭、葉の先半分だけに鋸歯があります。花はコメツブツメクサと似て黄色、全体に小型、20~30個の花がほぼ球形についています。萼裂片は筒部より長く、花後に花序が長くなり、熟すと果実が黒くなってやや長い総状となります。果実は長さ約2.5㎜、ウマゴヤシのような刺がなく、腎形で、先が半回転ねじれ、中に1個ずつ種子が入っています。。種子は長さ約1.5㎜、淡褐色です。果実に腺毛があるものはネバリコメツブウマゴヤシといいます。ただし、中間的なものもあり、変化が連続的です。ウマゴヤシは葉縁が細裂し、托葉はクシ状に深裂します。果実はやや扁平な円形、らせん状に丸まり、縁に刺があります。
江戸時代に渡来したマメ科の植物です。茎は断面が四角、這い、やや斜上し、毛があります。葉は3小葉で、小葉は長さ約15㎜の広倒卵形、先端はやや凹頭、葉の先半分だけに鋸歯があります。花はコメツブツメクサと似て黄色、全体に小型、20~30個の花がほぼ球形についています。萼裂片は筒部より長く、花後に花序が長くなり、熟すと果実が黒くなってやや長い総状となります。果実は長さ約2.5㎜、ウマゴヤシのような刺がなく、腎形で、先が半回転ねじれ、中に1個ずつ種子が入っています。。種子は長さ約1.5㎜、淡褐色です。果実に腺毛があるものはネバリコメツブウマゴヤシといいます。ただし、中間的なものもあり、変化が連続的です。ウマゴヤシは葉縁が細裂し、托葉はクシ状に深裂します。果実はやや扁平な円形、らせん状に丸まり、縁に刺があります。
 セイタカハハコグサ(背高母子草)はさまざまな環境での成長に適応することができ、庭でよく見られます。一度確立されると、それはコミュニティを形成し、それは環境に悪影響を及ぼし、庭に生い茂ったように見えます。セイタカハハコグサ(キク科の越年草)はヨーロッパ原産の帰化植物で、ハハコグサ(日本の在来種)に似ていますが、ヨーロッパ原産の外来種です。識別ポイントとしては、頭花はブロッコリーのような形で淡い茶色から黄褐色、頭花の柄は長く茎の上方で分枝することが多いです。葉は両面に綿毛があり、線形に近いスプーン状で先端がやや尖り斜上します。草丈は最大60cm程度に達します。
セイタカハハコグサ(背高母子草)はさまざまな環境での成長に適応することができ、庭でよく見られます。一度確立されると、それはコミュニティを形成し、それは環境に悪影響を及ぼし、庭に生い茂ったように見えます。セイタカハハコグサ(キク科の越年草)はヨーロッパ原産の帰化植物で、ハハコグサ(日本の在来種)に似ていますが、ヨーロッパ原産の外来種です。識別ポイントとしては、頭花はブロッコリーのような形で淡い茶色から黄褐色、頭花の柄は長く茎の上方で分枝することが多いです。葉は両面に綿毛があり、線形に近いスプーン状で先端がやや尖り斜上します。草丈は最大60cm程度に達します。