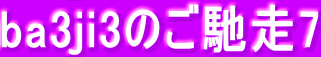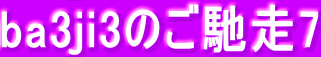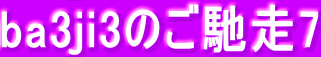


 くりこま高原温泉郷は、国定公園栗駒山の宮城県側登山口にあり、世界遺産「平泉」の観光にも便利な所に位置しています。塩化物泉の「ハイルザーム栗駒」と、江戸時代(1720年)に開湯した硫黄泉の「新湯温泉くりこま荘」があります。「ハイルザーム栗駒」には、大小2つの内湯と露天風呂を男女別に設置されています。温泉を引いた流水プールや寝湯、バイブラバス、サウナなどの入浴も楽しめる近代的保養施設です。「新湯温泉くりこま荘」は、檜造りの内湯と露天風呂が男女別に設けられています。檜造りの貸切露天風呂もある癒し系秘湯の宿です。ともに日帰り入浴も受け付けています。
くりこま高原温泉郷は、国定公園栗駒山の宮城県側登山口にあり、世界遺産「平泉」の観光にも便利な所に位置しています。塩化物泉の「ハイルザーム栗駒」と、江戸時代(1720年)に開湯した硫黄泉の「新湯温泉くりこま荘」があります。「ハイルザーム栗駒」には、大小2つの内湯と露天風呂を男女別に設置されています。温泉を引いた流水プールや寝湯、バイブラバス、サウナなどの入浴も楽しめる近代的保養施設です。「新湯温泉くりこま荘」は、檜造りの内湯と露天風呂が男女別に設けられています。檜造りの貸切露天風呂もある癒し系秘湯の宿です。ともに日帰り入浴も受け付けています。


 鬼首は、JR「鳴子温泉駅」から車で約30分、かんけつ泉や地獄谷などブナ自然林に囲まれた太古のカルデラの山々に囲まれた温泉郷です。その昔、当地で朝廷に逆らっていた鬼(蝦夷)討伐を命じられた坂上田村麻呂が首長の首を落としたところ、空を飛び大岩にかじり付いたという伝説から「鬼首」の名がついたといわれています。周囲にそびえる禿岳(かむろだけ)や荒雄岳、須金岳の麓にはテニスコートやキャンプ場、スキー場などのスポーツ施設も充実しています。登山客はもちろん、グループやファミリーにも人気を集めています。大自然の四季が一望でき、目の前にゲレンデが広がる「ホテルオニコウベ」、夕食は自然豊かな環境から地場食材を多く取り入れた和風会席料理が宴を演出しています。
鬼首は、JR「鳴子温泉駅」から車で約30分、かんけつ泉や地獄谷などブナ自然林に囲まれた太古のカルデラの山々に囲まれた温泉郷です。その昔、当地で朝廷に逆らっていた鬼(蝦夷)討伐を命じられた坂上田村麻呂が首長の首を落としたところ、空を飛び大岩にかじり付いたという伝説から「鬼首」の名がついたといわれています。周囲にそびえる禿岳(かむろだけ)や荒雄岳、須金岳の麓にはテニスコートやキャンプ場、スキー場などのスポーツ施設も充実しています。登山客はもちろん、グループやファミリーにも人気を集めています。大自然の四季が一望でき、目の前にゲレンデが広がる「ホテルオニコウベ」、夕食は自然豊かな環境から地場食材を多く取り入れた和風会席料理が宴を演出しています。
 東北の宮城県に位置する鳴子温泉郷の中山平温泉は、環境省指定の国民保養温泉地です。泉質は含重曹硫黄泉、単純泉、重曹泉等種類も豊富で美肌の湯・美人の湯として知られています。アルカリ度の高い、ぬるぬるした感触が得られる湯のためウナギ湯という名称でも親しまれています。紅葉の名所として名高い鳴子峡の南西約1kmほどに位置しています。遊歩道や展望台も整備されており、新緑の美しい春から、紅葉に色鮮やかに彩られる秋までの一年中が見どころです。やすらぎ荘は、JR中山平温泉駅から徒歩14分のところにある天然温泉を併設する庶民的な公共の宿です。白壁のシンプルな外観で、自然光が差し込むナチュラルな雰囲気のロビーがある同宿は、鳴子峡大展望台まで徒歩13分、日本こけし館まで車で約3kmの距離にあります。
東北の宮城県に位置する鳴子温泉郷の中山平温泉は、環境省指定の国民保養温泉地です。泉質は含重曹硫黄泉、単純泉、重曹泉等種類も豊富で美肌の湯・美人の湯として知られています。アルカリ度の高い、ぬるぬるした感触が得られる湯のためウナギ湯という名称でも親しまれています。紅葉の名所として名高い鳴子峡の南西約1kmほどに位置しています。遊歩道や展望台も整備されており、新緑の美しい春から、紅葉に色鮮やかに彩られる秋までの一年中が見どころです。やすらぎ荘は、JR中山平温泉駅から徒歩14分のところにある天然温泉を併設する庶民的な公共の宿です。白壁のシンプルな外観で、自然光が差し込むナチュラルな雰囲気のロビーがある同宿は、鳴子峡大展望台まで徒歩13分、日本こけし館まで車で約3kmの距離にあります。


 鳴子温泉は宮城県の最北端にあり、鳴子温泉郷(鳴子・東鳴子・川渡・中山平・鬼首)の5つの温泉地の中の一つです。温泉の泉質は多彩で、種類の豊富さ・源泉数の多さは日本有数です。歴史は古く、「続日本後記」に承和4年(837年)4月に潟山が大爆発をして温泉が湧き出したとあり、温泉宿の開湯は江戸時代中期頃と伝えられて、湯治場として多くの人々に親しまれました。また、江戸時代後期には木地師たちがろくろを使って作製した「鳴子こけし」をお土産や玩具として広めました。その木地技術と共に発展してきた漆工芸品の「鳴子漆器」も有名です。「ますや」は、四季を彩る鳴子を最上階の大浴場・露天風呂から見下ろすことが出来ます。男性風呂は鳴子の町並み、女性風呂は季節ごとに変わる山々を間近で楽しめる当館自慢の大浴場です。
鳴子温泉は宮城県の最北端にあり、鳴子温泉郷(鳴子・東鳴子・川渡・中山平・鬼首)の5つの温泉地の中の一つです。温泉の泉質は多彩で、種類の豊富さ・源泉数の多さは日本有数です。歴史は古く、「続日本後記」に承和4年(837年)4月に潟山が大爆発をして温泉が湧き出したとあり、温泉宿の開湯は江戸時代中期頃と伝えられて、湯治場として多くの人々に親しまれました。また、江戸時代後期には木地師たちがろくろを使って作製した「鳴子こけし」をお土産や玩具として広めました。その木地技術と共に発展してきた漆工芸品の「鳴子漆器」も有名です。「ますや」は、四季を彩る鳴子を最上階の大浴場・露天風呂から見下ろすことが出来ます。男性風呂は鳴子の町並み、女性風呂は季節ごとに変わる山々を間近で楽しめる当館自慢の大浴場です。
 「鳴子」の名前の由来は潟山の大爆発後、この辺りの土地を「鳴動の湯」と呼んでいましたが、時代を経るに従い「鳴声」、「鳴号」、「鳴子」と読み改めるようになったことという説と、源義経が平泉を目指している道中、生まれた赤ん坊が川底から湧き出る温泉につかると安心し産声を上げたことから、「泣き子の里」、「なきこ」がなるこ(鳴子)の語源という伝説もあります。鳴子温泉郷は環境省の国民保養温泉地に指定され、ゆっくりと安らげる温泉地です。鳴子温泉は駅前に温泉街が広がり、無料の「足湯」「手湯」で気軽に温泉に触れることができます。お宿ごとに泉質が異なり、湯色も感触もいろいろ。湯めぐりをして「鳴子の湯」を堪能するのも魅力です。「幸雲閣」は、温泉は鳴子でも230年の歴史をもつ伝統車湯の「黒湯」と「白湯」の2種類の泉質をお楽しめます。
「鳴子」の名前の由来は潟山の大爆発後、この辺りの土地を「鳴動の湯」と呼んでいましたが、時代を経るに従い「鳴声」、「鳴号」、「鳴子」と読み改めるようになったことという説と、源義経が平泉を目指している道中、生まれた赤ん坊が川底から湧き出る温泉につかると安心し産声を上げたことから、「泣き子の里」、「なきこ」がなるこ(鳴子)の語源という伝説もあります。鳴子温泉郷は環境省の国民保養温泉地に指定され、ゆっくりと安らげる温泉地です。鳴子温泉は駅前に温泉街が広がり、無料の「足湯」「手湯」で気軽に温泉に触れることができます。お宿ごとに泉質が異なり、湯色も感触もいろいろ。湯めぐりをして「鳴子の湯」を堪能するのも魅力です。「幸雲閣」は、温泉は鳴子でも230年の歴史をもつ伝統車湯の「黒湯」と「白湯」の2種類の泉質をお楽しめます。
 古くから仙台の奥座敷として称された作並温泉は、仙台市と山形市を結ぶ国道48号線(関山街道)に位置し、その由来は歴代仙台藩主のかくし湯と伝えられています。寛政八年(1796年)の開湯以来、さまざまな文化人を始め多くの人々が訪れ今なお愛され続けられています。肌にやさしい泉質と豊富なお湯から「美女づくりの湯」とも言われており、露天風呂や岩風呂、立ち湯など各旅館の多彩な湯めぐりが楽しめます。作並温泉に位置するLa楽リゾートホテル グリーングリーンは仙台駅から電車で約30分。広瀬川渓流・雄大な自然に抱かれたくつろぎのリゾートホテルです。ファンタジーホール「ララ・グリーン」でのバイキングでは、新鮮実演マグロのお刺身&お寿司・仙台名物牛タン焼きなどに加え、人気のアイス・ハーゲンダッツもご用意しております。
古くから仙台の奥座敷として称された作並温泉は、仙台市と山形市を結ぶ国道48号線(関山街道)に位置し、その由来は歴代仙台藩主のかくし湯と伝えられています。寛政八年(1796年)の開湯以来、さまざまな文化人を始め多くの人々が訪れ今なお愛され続けられています。肌にやさしい泉質と豊富なお湯から「美女づくりの湯」とも言われており、露天風呂や岩風呂、立ち湯など各旅館の多彩な湯めぐりが楽しめます。作並温泉に位置するLa楽リゾートホテル グリーングリーンは仙台駅から電車で約30分。広瀬川渓流・雄大な自然に抱かれたくつろぎのリゾートホテルです。ファンタジーホール「ララ・グリーン」でのバイキングでは、新鮮実演マグロのお刺身&お寿司・仙台名物牛タン焼きなどに加え、人気のアイス・ハーゲンダッツもご用意しております。
 はるか古墳時代より、「名取の御湯」と称され「日本三御湯」のひとつとして全国的にも知られてきた秋保温泉。秋保温泉の歴史は古く、古墳時代(531〜570年)の頃には、第29第欽明天皇秋保の湯で皮膚病の一種を癒やしたと伝えられ、このとき「名取の御湯」の称号を賜ったとされます。以後、秋保温泉は皇室の御料温泉の一つとして位置づけられ、別所温泉(信濃御湯)、野沢温泉(犬養御湯)と共に「日本三御湯」と称されるようになりました。「名取の御湯」は、「拾遺集」、「大和物語」などにも詠われています。伊達政宗公も秋保の湯を愛し、伊達家の入湯場として代々大切に守られてきました。仙台の奥座敷・秋保温泉 ホテルニュー水戸屋では、四季折々の自然に囲まれ、都会の喧騒から離れて、ゆったりとした時の流れの中でお過ごしいただけます。温泉旅館にきたら、やはり普段食べられないお食事が楽しみかと思います。ホテルニュー水戸屋のお食事は、料理長が厳選した郷土の食材、自然の恵みをご用意いたします。朝食はカップルにもご家族連れにも嬉しい人気のバイキングもお楽しみいただけます。
はるか古墳時代より、「名取の御湯」と称され「日本三御湯」のひとつとして全国的にも知られてきた秋保温泉。秋保温泉の歴史は古く、古墳時代(531〜570年)の頃には、第29第欽明天皇秋保の湯で皮膚病の一種を癒やしたと伝えられ、このとき「名取の御湯」の称号を賜ったとされます。以後、秋保温泉は皇室の御料温泉の一つとして位置づけられ、別所温泉(信濃御湯)、野沢温泉(犬養御湯)と共に「日本三御湯」と称されるようになりました。「名取の御湯」は、「拾遺集」、「大和物語」などにも詠われています。伊達政宗公も秋保の湯を愛し、伊達家の入湯場として代々大切に守られてきました。仙台の奥座敷・秋保温泉 ホテルニュー水戸屋では、四季折々の自然に囲まれ、都会の喧騒から離れて、ゆったりとした時の流れの中でお過ごしいただけます。温泉旅館にきたら、やはり普段食べられないお食事が楽しみかと思います。ホテルニュー水戸屋のお食事は、料理長が厳選した郷土の食材、自然の恵みをご用意いたします。朝食はカップルにもご家族連れにも嬉しい人気のバイキングもお楽しみいただけます。


 気仙沼市は宮城県の最北端に位置するまちです。人口は約5.7万人。世界三大漁場の三陸沖に隣接し、世界中から漁船が集います。沿岸を少し離れると、海を一望できる安波山や美しい田風景が広がり、水と緑に恵まれたまちです。年間平均気温はおよそ11℃。1年を通して晴れの日が多く暮らしやすい気候です。夏は涼しい風が吹き、扇風機1台でも十分過ごせます。冬は雪も降りますが、高く積もることは少ない地域です。地名はアイヌ語のケセモイ、ケセムイからきており、湾内の奥、もしくはアイヌの勢力の及ぶはずれの港の意味とする説があります。気仙沼プラザホテルは気仙沼湾を一望する高台に立つホテルです。アワビ・フカヒレ・メカジキなど気仙沼の旬な海の幸と地下1800mから湧き出る深層天然温泉で、海水と同じくらいの塩分濃度があるため、体をぷかぷか浮かせることができます。
気仙沼市は宮城県の最北端に位置するまちです。人口は約5.7万人。世界三大漁場の三陸沖に隣接し、世界中から漁船が集います。沿岸を少し離れると、海を一望できる安波山や美しい田風景が広がり、水と緑に恵まれたまちです。年間平均気温はおよそ11℃。1年を通して晴れの日が多く暮らしやすい気候です。夏は涼しい風が吹き、扇風機1台でも十分過ごせます。冬は雪も降りますが、高く積もることは少ない地域です。地名はアイヌ語のケセモイ、ケセムイからきており、湾内の奥、もしくはアイヌの勢力の及ぶはずれの港の意味とする説があります。気仙沼プラザホテルは気仙沼湾を一望する高台に立つホテルです。アワビ・フカヒレ・メカジキなど気仙沼の旬な海の幸と地下1800mから湧き出る深層天然温泉で、海水と同じくらいの塩分濃度があるため、体をぷかぷか浮かせることができます。
 日本三景・松島に初めてとなる「太古天泉 松島温泉」が誕生。地下1500mから湧き出した温泉は数億年前の天水が浸透し、地熱により温められ長い年月をかけて、湯として貯留されていたもので、縄文時代の原風景を今もなお残す松島らしい温泉です。松島温泉は、2007年の掘削工事で掘り当てられた新しい温泉地です。地下1000~1500mのところから湧出するこの温泉は、数億年前の古生代、地球太古の天水が地下に浸透し地熱であたためられ、長い年月をかけて貯留されていたものです。2011年の東関東大震災では一部の旅館が被災したものの、被災者の避難先や災害ボランティアなどの基地として利用され、その後、復旧が進み一般客の受け入れが再開されました。一の坊は、七千坪の庭園とその先に続く松島の海を眺めることが出来る宿です。アート・庭園散策・ライブビュッフェ等様々な魅力ある温泉リゾートです。
日本三景・松島に初めてとなる「太古天泉 松島温泉」が誕生。地下1500mから湧き出した温泉は数億年前の天水が浸透し、地熱により温められ長い年月をかけて、湯として貯留されていたもので、縄文時代の原風景を今もなお残す松島らしい温泉です。松島温泉は、2007年の掘削工事で掘り当てられた新しい温泉地です。地下1000~1500mのところから湧出するこの温泉は、数億年前の古生代、地球太古の天水が地下に浸透し地熱であたためられ、長い年月をかけて貯留されていたものです。2011年の東関東大震災では一部の旅館が被災したものの、被災者の避難先や災害ボランティアなどの基地として利用され、その後、復旧が進み一般客の受け入れが再開されました。一の坊は、七千坪の庭園とその先に続く松島の海を眺めることが出来る宿です。アート・庭園散策・ライブビュッフェ等様々な魅力ある温泉リゾートです。
 昔は「湯刈田」ともいわれた遠刈田温泉は標高330mの高原にあり、信仰登山の基地や湯治場として知られてきました。温泉発祥の由来は、岩崎山の金を掘って財を成した金売橘次が霊泉を発見したのが始まりと伝えられています。史料によると、金の採掘は慶長年間(1600年代)であることから、温泉の発見も実際はこの頃と推定されています。また別の伝説によると、不動滝の大うなぎが三階滝の大ガニとの戦いに敗れ、切られた尾がこの地に流れつきました。それにより足腰の病に効くといわれています。今も共同浴場を中心に広がる旅館やこけし工人の家並みは、往時を偲ばせます。旅館
三治郎の大浴場や露天風呂は、他では絶対見ることのできない素晴らしい蔵王連峰の景色を眺めながらの入浴が魅力の一つになっています。特に夕方と朝は見事なパノラマを手にすることができます。
昔は「湯刈田」ともいわれた遠刈田温泉は標高330mの高原にあり、信仰登山の基地や湯治場として知られてきました。温泉発祥の由来は、岩崎山の金を掘って財を成した金売橘次が霊泉を発見したのが始まりと伝えられています。史料によると、金の採掘は慶長年間(1600年代)であることから、温泉の発見も実際はこの頃と推定されています。また別の伝説によると、不動滝の大うなぎが三階滝の大ガニとの戦いに敗れ、切られた尾がこの地に流れつきました。それにより足腰の病に効くといわれています。今も共同浴場を中心に広がる旅館やこけし工人の家並みは、往時を偲ばせます。旅館
三治郎の大浴場や露天風呂は、他では絶対見ることのできない素晴らしい蔵王連峰の景色を眺めながらの入浴が魅力の一つになっています。特に夕方と朝は見事なパノラマを手にすることができます。

 鎌先温泉は、山の谷底に5軒の宿が肩を寄せ合うように建っています。「傷に鎌先」と呼ばれ、昔から切り傷に効能があると評判の「奥羽の薬湯」です。自炊のできる宿もあり、昔ながらの湯治場情緒がたっぷり漂っています。数日間滞在する湯治客を楽しませてきたのが、伝統の「弥治郎こけし」と名物「白石温麺(うーめん)」です。その昔、弥治郎のこけし職人たちは鎌先温泉の部屋を売って回ったとの事です。今も春から秋までは耕作、冬はこけし作りという半農半工の生活が残るという弥治郎。こけしの素朴な表情は、そんな生活の中から生まれています。また、油を一切使わない「白石温麺」は消化が良いことで有名です。400年の歴史を持つ白石の味が、湯治客の回復を支えています。鎌先温泉にある元禄元年から続く老舗宿「にごり湯の宿 湯守木村屋」は2本の源泉で5つのお風呂が楽しめます。源泉100%かけ流し露天風呂、宮城の旬の恵みの食材で作る会席料理を頂けます。
鎌先温泉は、山の谷底に5軒の宿が肩を寄せ合うように建っています。「傷に鎌先」と呼ばれ、昔から切り傷に効能があると評判の「奥羽の薬湯」です。自炊のできる宿もあり、昔ながらの湯治場情緒がたっぷり漂っています。数日間滞在する湯治客を楽しませてきたのが、伝統の「弥治郎こけし」と名物「白石温麺(うーめん)」です。その昔、弥治郎のこけし職人たちは鎌先温泉の部屋を売って回ったとの事です。今も春から秋までは耕作、冬はこけし作りという半農半工の生活が残るという弥治郎。こけしの素朴な表情は、そんな生活の中から生まれています。また、油を一切使わない「白石温麺」は消化が良いことで有名です。400年の歴史を持つ白石の味が、湯治客の回復を支えています。鎌先温泉にある元禄元年から続く老舗宿「にごり湯の宿 湯守木村屋」は2本の源泉で5つのお風呂が楽しめます。源泉100%かけ流し露天風呂、宮城の旬の恵みの食材で作る会席料理を頂けます。