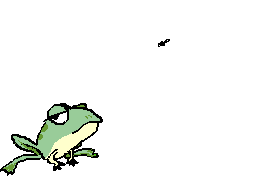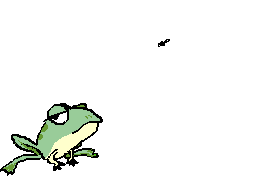
 チチアワタケのカサは直径が5cmほどで形は幼い時は半球形、成長すると平らになっていきます。カサの表面の色に関しては幼菌時は栗褐色で、やがて黄褐色になっていきます。また、湿気が強い環境では表面にはヌメリが見られ、幼い時は粘性が強く、やがて粘性が弱くなるという特徴があります。チチアワタケの肉は貴白色で、味や匂いは特にありません。また、毒の成分がある為、毒キノコとされています。チチアワタケは消化器系の中毒症状を起こす事のある毒キノコです。毒性の強さについては産地や環境に左右される為、一概には言えませんが、毒キノコである事には変わりはないので食用とする事は控えた方がよいでしょう。
チチアワタケのカサは直径が5cmほどで形は幼い時は半球形、成長すると平らになっていきます。カサの表面の色に関しては幼菌時は栗褐色で、やがて黄褐色になっていきます。また、湿気が強い環境では表面にはヌメリが見られ、幼い時は粘性が強く、やがて粘性が弱くなるという特徴があります。チチアワタケの肉は貴白色で、味や匂いは特にありません。また、毒の成分がある為、毒キノコとされています。チチアワタケは消化器系の中毒症状を起こす事のある毒キノコです。毒性の強さについては産地や環境に左右される為、一概には言えませんが、毒キノコである事には変わりはないので食用とする事は控えた方がよいでしょう。
 シロカノシタ(白鹿の舌)は秋に各種林内の地上に発生します。シロカノシタは基本種であるカノシタの白色変種ですが、カノシタよりも多く発生します。食用とすることができ、クセがなくて口当たりがよいため、けんちん汁、みそ汁、炒め物などによく合います。日本だけではなく、ヨーロッパでも食べられているキノコです。シロカノシタはその美味しい味と肉質食感で高く評価される食用キノコです。特に秋のピークシーズン中は料理界で人気があります。この種はさまざまな料理で使用され、独特のナッティーなエッセンスで風味を高めます。食用種として広く収集されていますが、食用ではない類似種と混同しないよう正確に識別する必要があります。消費する前に必ず正しく識別してください。
シロカノシタ(白鹿の舌)は秋に各種林内の地上に発生します。シロカノシタは基本種であるカノシタの白色変種ですが、カノシタよりも多く発生します。食用とすることができ、クセがなくて口当たりがよいため、けんちん汁、みそ汁、炒め物などによく合います。日本だけではなく、ヨーロッパでも食べられているキノコです。シロカノシタはその美味しい味と肉質食感で高く評価される食用キノコです。特に秋のピークシーズン中は料理界で人気があります。この種はさまざまな料理で使用され、独特のナッティーなエッセンスで風味を高めます。食用種として広く収集されていますが、食用ではない類似種と混同しないよう正確に識別する必要があります。消費する前に必ず正しく識別してください。
 ゲンノショウコは、野山の日当たりの良い場所に生える多年草です。日本在来のフウロソウ科植物のなかではもっとも身近でふつうに見られる種類です。ただ環境改変には弱いのか、都市化が進むと姿を消してしまう傾向があります。葉は掌状にギザギザと切れ込み、若葉には黒い斑点が見られます。夏から秋にかけて、白色または紅紫色の花を咲かせます。白花株は東日本に、紅花株は西日本に多いとされますが、必ずしもそうとは限らないようです。1つの花に5個のタネができます。成熟すると、皮ごとめくれあがり、そのときの勢いでタネを遠くまで弾き飛ばそうとします。すべてのタネが弾き飛ばされた後はまるでおみこしの屋根のように見えることから、ミコシグサの別名もあります。
ゲンノショウコは、野山の日当たりの良い場所に生える多年草です。日本在来のフウロソウ科植物のなかではもっとも身近でふつうに見られる種類です。ただ環境改変には弱いのか、都市化が進むと姿を消してしまう傾向があります。葉は掌状にギザギザと切れ込み、若葉には黒い斑点が見られます。夏から秋にかけて、白色または紅紫色の花を咲かせます。白花株は東日本に、紅花株は西日本に多いとされますが、必ずしもそうとは限らないようです。1つの花に5個のタネができます。成熟すると、皮ごとめくれあがり、そのときの勢いでタネを遠くまで弾き飛ばそうとします。すべてのタネが弾き飛ばされた後はまるでおみこしの屋根のように見えることから、ミコシグサの別名もあります。
 ホテイチクは、中国を原産とするマダケの仲間です。棹の下部が七福神の布袋様の腹のように膨れ上がることからホテイチクと命名され、これを観賞するため日本庭園に植栽され、観葉植物的な扱いも多いです。日本での自生はほぼないですが、福島県以西に植栽され、九州南部では帰化したものが野生化しています。節間が奇抜な形になるのは稈の下部にある数節で、節のすぐ下が左右互い違いに膨れ上がることによりますが、その形状には個体差があります。中にはモウソウチクの変種であるキッコウチクと見分けがつかなくなるものもあります。葉は長さ7~12cm、幅1~2cmほどの淡い緑色で、葉脈が格子状になっています。枝は稈の上部から2本ずつ立ち上がりますが、その角度はタケの中でも最も鋭いです。
ホテイチクは、中国を原産とするマダケの仲間です。棹の下部が七福神の布袋様の腹のように膨れ上がることからホテイチクと命名され、これを観賞するため日本庭園に植栽され、観葉植物的な扱いも多いです。日本での自生はほぼないですが、福島県以西に植栽され、九州南部では帰化したものが野生化しています。節間が奇抜な形になるのは稈の下部にある数節で、節のすぐ下が左右互い違いに膨れ上がることによりますが、その形状には個体差があります。中にはモウソウチクの変種であるキッコウチクと見分けがつかなくなるものもあります。葉は長さ7~12cm、幅1~2cmほどの淡い緑色で、葉脈が格子状になっています。枝は稈の上部から2本ずつ立ち上がりますが、その角度はタケの中でも最も鋭いです。
 ハキダメギクは、熱帯アメリカ原産で、世界中に広がっている1年草です。日本には大正時代に渡来したと推定されますが、よく似た仲間のコゴメギクとの混同もあり、あまりはっきりしません。国内ではハキダメギクが圧倒的に多く、市内でもハキダメギクが優勢です。世代交代のサイクルが早く、発芽から1か月ほどで開花・結実できるようになります。また一定の温度が維持されれば、季節に関係なく年じゅう開花・結実が可能で、市街地や温室の中などでは通年発生しています。小さな花が多数集まって一つの大きな花のようになっています。外側に白い舌状花がふつう5個ずつつきますが、数は変動します。果実は綿毛がついており、風であちこち飛ばされていきます。
ハキダメギクは、熱帯アメリカ原産で、世界中に広がっている1年草です。日本には大正時代に渡来したと推定されますが、よく似た仲間のコゴメギクとの混同もあり、あまりはっきりしません。国内ではハキダメギクが圧倒的に多く、市内でもハキダメギクが優勢です。世代交代のサイクルが早く、発芽から1か月ほどで開花・結実できるようになります。また一定の温度が維持されれば、季節に関係なく年じゅう開花・結実が可能で、市街地や温室の中などでは通年発生しています。小さな花が多数集まって一つの大きな花のようになっています。外側に白い舌状花がふつう5個ずつつきますが、数は変動します。果実は綿毛がついており、風であちこち飛ばされていきます。
 日本のひっつき虫を象徴する存在と言えるのは、キク科のオナモミです。果実全体に、先端が鈎状に曲がったトゲを持ち、衣類などにしっかりとひっつきます。しかし、「オナモミ」という種名の在来植物は現在、非常に少なくなっています。秋から冬にかけてセーターなどの衣類にくっつき、とげとげとした実を皆さん一度は目にしたことがあると思いますが、これが生薬になるのをご存じでしたか?それはオナモミという植物の果実で、日干しにすると蒼耳子という生薬になります。オナモミは北海道から沖縄で自生しており、海外では台湾、朝鮮半島、中国、北米に分布しています。稲作文化が日本に入った頃、アジア大陸からの帰化植物として全国に広まったとされています。オナモミは1年草で高さ20
cm~1 mになり、花期は8~10月で、果実を9~10月に採取し乾燥させソウジシとなります。
日本のひっつき虫を象徴する存在と言えるのは、キク科のオナモミです。果実全体に、先端が鈎状に曲がったトゲを持ち、衣類などにしっかりとひっつきます。しかし、「オナモミ」という種名の在来植物は現在、非常に少なくなっています。秋から冬にかけてセーターなどの衣類にくっつき、とげとげとした実を皆さん一度は目にしたことがあると思いますが、これが生薬になるのをご存じでしたか?それはオナモミという植物の果実で、日干しにすると蒼耳子という生薬になります。オナモミは北海道から沖縄で自生しており、海外では台湾、朝鮮半島、中国、北米に分布しています。稲作文化が日本に入った頃、アジア大陸からの帰化植物として全国に広まったとされています。オナモミは1年草で高さ20
cm~1 mになり、花期は8~10月で、果実を9~10月に採取し乾燥させソウジシとなります。
 ヒメジソは、日本を含む東アジア原産の一年草で、山や林や道端でよく見られます。花は淡い紫色から白色で節ごとに2個ずつ咲きます。ヒメジソという和名は、姿や香りがシソに似て、小ぶりであることから名づけられました。茎や葉に白い毛が生えます。原産地は東アジア、南アジア、東南アジアです。アジア大陸のさまざまな気候と地域に広がっており、さまざまな生息地で繁栄しています。自然な生息地を超えて、異なる環境にも適応できるため、ヒメジソは栽培もされています。この拡張は、この植物が原産地と管理された生態系の両方での汎用性を示しています。ヒメジソは葉の鋸歯が粗く数が少なく、萼の上唇の尖りは緩やかで、花軸の毛は少なく、白~淡紫色の花をつける傾向があります。
ヒメジソは、日本を含む東アジア原産の一年草で、山や林や道端でよく見られます。花は淡い紫色から白色で節ごとに2個ずつ咲きます。ヒメジソという和名は、姿や香りがシソに似て、小ぶりであることから名づけられました。茎や葉に白い毛が生えます。原産地は東アジア、南アジア、東南アジアです。アジア大陸のさまざまな気候と地域に広がっており、さまざまな生息地で繁栄しています。自然な生息地を超えて、異なる環境にも適応できるため、ヒメジソは栽培もされています。この拡張は、この植物が原産地と管理された生態系の両方での汎用性を示しています。ヒメジソは葉の鋸歯が粗く数が少なく、萼の上唇の尖りは緩やかで、花軸の毛は少なく、白~淡紫色の花をつける傾向があります。
 ヤナギタデは、水田や湿地、河川敷などの水辺環境に普通に生えるタデの仲間です。稲刈り後の水田周辺で特に見つけやすい傾向があります。湧水のある場所では、水中で流れにたなびきながらまるで水草のように育つこともあります。ことわざ「蓼(タデ)食う虫も好き好き」の蓼は、このヤナギタデのことです。ヤナギタデの葉はかじると強い辛みがあります。こんな辛い葉でも好んで食べる虫がいるのと同様に、人の好みはさまざまだという意味合いがあります。早いものでは7月頃から穂を出しはじめますが、本格的な花期は秋になってからです。花は茎の先だけではなく、葉のつけ根にも、鞘の中に包まれるようにして何個かつきます。
ヤナギタデは、水田や湿地、河川敷などの水辺環境に普通に生えるタデの仲間です。稲刈り後の水田周辺で特に見つけやすい傾向があります。湧水のある場所では、水中で流れにたなびきながらまるで水草のように育つこともあります。ことわざ「蓼(タデ)食う虫も好き好き」の蓼は、このヤナギタデのことです。ヤナギタデの葉はかじると強い辛みがあります。こんな辛い葉でも好んで食べる虫がいるのと同様に、人の好みはさまざまだという意味合いがあります。早いものでは7月頃から穂を出しはじめますが、本格的な花期は秋になってからです。花は茎の先だけではなく、葉のつけ根にも、鞘の中に包まれるようにして何個かつきます。
 ヒロハノレンリソウは、欧州原産で、マメ科ハマエンドウ属の蔓性落葉多年草です。日本には明治初期に渡来し、帰化しています。スイトピーかと思われた方もいらしたことでしょう。お互いにとてもよく似ています。違いは、スイートピーは一年草であり、ヒロハノレンリソウは多年草であり、別名で宿根スイートピーと呼ばれます。蔓長は100~300
cmです。スイートピーと同様、茎や葉柄に翼があります。葉は2出複葉で小葉は披針形をしており、先端にある巻きヒゲが樹木などに絡んでよじ登ります。葉や葉柄には翼があります。夏に、葉腋から花序を伸ばし花を10個程付けます。花はマメ科特有の蝶形で、芳香は無く、花色が少なく白か桃色です。花後に成る果実はスイトピーと同様、有毒です。
ヒロハノレンリソウは、欧州原産で、マメ科ハマエンドウ属の蔓性落葉多年草です。日本には明治初期に渡来し、帰化しています。スイトピーかと思われた方もいらしたことでしょう。お互いにとてもよく似ています。違いは、スイートピーは一年草であり、ヒロハノレンリソウは多年草であり、別名で宿根スイートピーと呼ばれます。蔓長は100~300
cmです。スイートピーと同様、茎や葉柄に翼があります。葉は2出複葉で小葉は披針形をしており、先端にある巻きヒゲが樹木などに絡んでよじ登ります。葉や葉柄には翼があります。夏に、葉腋から花序を伸ばし花を10個程付けます。花はマメ科特有の蝶形で、芳香は無く、花色が少なく白か桃色です。花後に成る果実はスイトピーと同様、有毒です。
 アオゲイトウは一年生植物で、強健な成長習性を持ち、複数の茎を発達させることが多く、高さは約30cm〜2mに達します。葉は一般に幅広く緑色で、やや波状または縮れた質感を持ち、中央の葉脈が目立ちます。花序は密集した小さな緑色の花の集まりとして現れ、通常は夏に咲き、秋にかけても持続します。この植物は深い直根を持ち、枝分かれが少なく、またはより単一で頑丈な茎で成長することができます。アオゲイトウの葉は、中央の茎に沿ってサイズが大きく変化し、頂部に向かって小さくなります。各葉には丸みを帯びた基部と、鋭尖、鈍尖、切形、または丸みのある先端があります。上面は滑らかで無毛ですが、下面は葉脈に沿って毛があり、赤みや紫色を帯びることがあります。これらの葉は通常、披針形から卵形で、長さは最大約15
cmです。
アオゲイトウは一年生植物で、強健な成長習性を持ち、複数の茎を発達させることが多く、高さは約30cm〜2mに達します。葉は一般に幅広く緑色で、やや波状または縮れた質感を持ち、中央の葉脈が目立ちます。花序は密集した小さな緑色の花の集まりとして現れ、通常は夏に咲き、秋にかけても持続します。この植物は深い直根を持ち、枝分かれが少なく、またはより単一で頑丈な茎で成長することができます。アオゲイトウの葉は、中央の茎に沿ってサイズが大きく変化し、頂部に向かって小さくなります。各葉には丸みを帯びた基部と、鋭尖、鈍尖、切形、または丸みのある先端があります。上面は滑らかで無毛ですが、下面は葉脈に沿って毛があり、赤みや紫色を帯びることがあります。これらの葉は通常、披針形から卵形で、長さは最大約15
cmです。
 ギョウギシバは匍匐茎(地表を這う茎)を平らに伸ばし、節ごとに葉をつけて広く地表を覆います。河原や海岸、荒れ地や学校の校庭でも見られます。雑草とされる一方、緑化や牧草として利用されることもあります。ギョウギシバは世界中の主要地域に広く分布しています。アフリカ原産であり、ヨーロッパ、アジア、アメリカなどのさまざまな大陸に導入されています。栽培種として、ギョウギシバはその強靭さと適応性で知られています。生息地を超えた特定の地域では、ギョウギシバは時に有益と考えられることもありますが、それが原生の生態系に影響を与え、地元の植生のダイナミクスの変化につながる可能性もあります。それにもかかわらず、ギョウギシバは栽培され続け、世界中のさまざまな生態系ゾーンで見つけることができます。
ギョウギシバは匍匐茎(地表を這う茎)を平らに伸ばし、節ごとに葉をつけて広く地表を覆います。河原や海岸、荒れ地や学校の校庭でも見られます。雑草とされる一方、緑化や牧草として利用されることもあります。ギョウギシバは世界中の主要地域に広く分布しています。アフリカ原産であり、ヨーロッパ、アジア、アメリカなどのさまざまな大陸に導入されています。栽培種として、ギョウギシバはその強靭さと適応性で知られています。生息地を超えた特定の地域では、ギョウギシバは時に有益と考えられることもありますが、それが原生の生態系に影響を与え、地元の植生のダイナミクスの変化につながる可能性もあります。それにもかかわらず、ギョウギシバは栽培され続け、世界中のさまざまな生態系ゾーンで見つけることができます。
 ナツヅタ(夏蔦)はブドウ科ツタ属の落葉性のつる植物で、吸盤のついた巻きひげや気根で壁などに吸着して伸びます。日本の山野にも自生し、秋の鮮やかな紅葉が美しく、壁面緑化などにも利用されます。夏の緑陰や冬の落葉後の姿も趣があり、育てやすい植物です。秋には葉が赤く紅葉し、冬には落葉して幹だけになります。若枝の巻きひげの先に吸盤があり、また茎から気根を出して壁や岩肌などにしっかりと吸着して成長します。春の新葉、夏の緑葉、秋の紅葉、そして冬の落葉後の姿と、一年を通してさまざまな表情を楽しめます。甲子園球場の壁面を覆うことで有名で、その生命力と旺盛な成長が特徴です。ナツヅタの代表的な花言葉は「永遠の愛」「結婚」「友情」「団結」「絆」「誠実」などです。ツタが他のものに力強く絡みつき、離れない性質から、人間関係の強い繋がりや、永遠に愛し続ける様子が連想され、これらの花言葉が生まれたとされています。
ナツヅタ(夏蔦)はブドウ科ツタ属の落葉性のつる植物で、吸盤のついた巻きひげや気根で壁などに吸着して伸びます。日本の山野にも自生し、秋の鮮やかな紅葉が美しく、壁面緑化などにも利用されます。夏の緑陰や冬の落葉後の姿も趣があり、育てやすい植物です。秋には葉が赤く紅葉し、冬には落葉して幹だけになります。若枝の巻きひげの先に吸盤があり、また茎から気根を出して壁や岩肌などにしっかりと吸着して成長します。春の新葉、夏の緑葉、秋の紅葉、そして冬の落葉後の姿と、一年を通してさまざまな表情を楽しめます。甲子園球場の壁面を覆うことで有名で、その生命力と旺盛な成長が特徴です。ナツヅタの代表的な花言葉は「永遠の愛」「結婚」「友情」「団結」「絆」「誠実」などです。ツタが他のものに力強く絡みつき、離れない性質から、人間関係の強い繋がりや、永遠に愛し続ける様子が連想され、これらの花言葉が生まれたとされています。
 イネ科の植物メリケンカルカヤは、北アメリカと中央アメリカを広く分布しています。また、東ヨーロッパ、東アジア、オーストララシアの一部に移入されています。太平洋の特定の島々やインド洋の一部など、一部領土ではメリケンカルカヤが侵入種と見なされることがあり、地元の生態系に影響を与える可能性があります。いくつかの国では侵略的な植物と記録されています。アロロパシー特性を持ち、在来植物の成長を抑制することがあります。特にハワイでは希少種に影響を与える問題となっています。必要に応じて、除草剤のような化学的な手段で新しい生育を抑制し、さらなる広がりを防ぐことができます。イネ科の植物であり、近くにいると、鼻水、目のかゆみ、くしゃみ、頭痛といった花粉症の症状を引き起こすことがあります。野生の草原、湿地、道路脇や手が入っていない畑などの廃棄物地域に見られます。
イネ科の植物メリケンカルカヤは、北アメリカと中央アメリカを広く分布しています。また、東ヨーロッパ、東アジア、オーストララシアの一部に移入されています。太平洋の特定の島々やインド洋の一部など、一部領土ではメリケンカルカヤが侵入種と見なされることがあり、地元の生態系に影響を与える可能性があります。いくつかの国では侵略的な植物と記録されています。アロロパシー特性を持ち、在来植物の成長を抑制することがあります。特にハワイでは希少種に影響を与える問題となっています。必要に応じて、除草剤のような化学的な手段で新しい生育を抑制し、さらなる広がりを防ぐことができます。イネ科の植物であり、近くにいると、鼻水、目のかゆみ、くしゃみ、頭痛といった花粉症の症状を引き起こすことがあります。野生の草原、湿地、道路脇や手が入っていない畑などの廃棄物地域に見られます。
 ギンネムはギンゴウカン(銀合歓)の名前も持っています。合歓はネムノキのことですから、おなじ意味です。ネムノキとギンネムの主な違いは、「花の色」「原産地・分布」「葉の様子」です。ネムノキはピンク色の花を咲かせる日本の在来種であるのに対し、ギンネムは白い花を咲かせ、熱帯アメリカ原産の外来種です。また、ギンネムの葉は銀白色を帯びることが名前の由来の一つとされています。果実はまさにマメであり、薄くてペラペラしている様子はネムノキとそっくりです。ネムノキなどはマメを稔らせることからマメ科とされてきましたが、近年は花の形などに着目してネムノキ科に属するのが適切であるとしている図鑑もあります。ギンネムにはミネラル(カルシウム、カリウム、マグネシウムなど)やミネラル、タンニンなどが豊富に含まれるため、健康茶として注目されています。
ギンネムはギンゴウカン(銀合歓)の名前も持っています。合歓はネムノキのことですから、おなじ意味です。ネムノキとギンネムの主な違いは、「花の色」「原産地・分布」「葉の様子」です。ネムノキはピンク色の花を咲かせる日本の在来種であるのに対し、ギンネムは白い花を咲かせ、熱帯アメリカ原産の外来種です。また、ギンネムの葉は銀白色を帯びることが名前の由来の一つとされています。果実はまさにマメであり、薄くてペラペラしている様子はネムノキとそっくりです。ネムノキなどはマメを稔らせることからマメ科とされてきましたが、近年は花の形などに着目してネムノキ科に属するのが適切であるとしている図鑑もあります。ギンネムにはミネラル(カルシウム、カリウム、マグネシウムなど)やミネラル、タンニンなどが豊富に含まれるため、健康茶として注目されています。
 メタケ(女竹)は、イネ科のササ類で、細くしなやかで粘り強く、川岸や海岸などに群生する植物です。大きさは最大で高さ8m、直径3cmほどになり、タケノコは食用にはならず苦味があるため「ニガタケ」とも呼ばれます。その柔軟性から、生活用具(籠、簾、うちわ)や園芸用支柱、笛の材料などに幅広く利用されています。イネ科メダケ属の多年生常緑笹で、関東以西の本州、四国、九州、琉球に分布し、川岸や海岸の丘陵などに群生します。細くてしなやかで粘り強く、成長した稈の表皮(稈鞘)が剥がれ落ちず、薄茶色に残るため、稈の緑色とストライプ模様ができるのが特徴です。葉は長さ10~25cm程度で硬く薄いですが、葉の先に尖って垂れ下がるのが特徴です。「女竹(メダケ)」という名前は、マダケを「男竹」と呼ぶことに対し、本種が小さく細いことから「雌竹」という意味で名付けられたとされています。
メタケ(女竹)は、イネ科のササ類で、細くしなやかで粘り強く、川岸や海岸などに群生する植物です。大きさは最大で高さ8m、直径3cmほどになり、タケノコは食用にはならず苦味があるため「ニガタケ」とも呼ばれます。その柔軟性から、生活用具(籠、簾、うちわ)や園芸用支柱、笛の材料などに幅広く利用されています。イネ科メダケ属の多年生常緑笹で、関東以西の本州、四国、九州、琉球に分布し、川岸や海岸の丘陵などに群生します。細くてしなやかで粘り強く、成長した稈の表皮(稈鞘)が剥がれ落ちず、薄茶色に残るため、稈の緑色とストライプ模様ができるのが特徴です。葉は長さ10~25cm程度で硬く薄いですが、葉の先に尖って垂れ下がるのが特徴です。「女竹(メダケ)」という名前は、マダケを「男竹」と呼ぶことに対し、本種が小さく細いことから「雌竹」という意味で名付けられたとされています。
 シロシラガゴケ は部分的な日光条件下で栄え、その生息地である斑点のあるまたは間接的な光を受けることができます。完全な日光にさらすと、乾燥と成長の抑制が起こる可能性があります。逆に、シロシラガゴケ は完全な日陰に耐える特筆すべき特性を示しますが、光の不足が長引くと、栄養価の低下とまばらな成長につながる可能性があります。このコケは、様々な光への適応遺伝子を持ち、明るい光の中では、余分な光を反映させる色合いを移行することで順応し、水分を保存しクロロフィルを保護します。一般的に屋外で見つかる シロシラガゴケ は、森の地面、木の根元、または日陰の岩の隙間に最適な状態で繁栄し、成長と健康のためにこれらの小さな生息地を利用しています。
シロシラガゴケ は部分的な日光条件下で栄え、その生息地である斑点のあるまたは間接的な光を受けることができます。完全な日光にさらすと、乾燥と成長の抑制が起こる可能性があります。逆に、シロシラガゴケ は完全な日陰に耐える特筆すべき特性を示しますが、光の不足が長引くと、栄養価の低下とまばらな成長につながる可能性があります。このコケは、様々な光への適応遺伝子を持ち、明るい光の中では、余分な光を反映させる色合いを移行することで順応し、水分を保存しクロロフィルを保護します。一般的に屋外で見つかる シロシラガゴケ は、森の地面、木の根元、または日陰の岩の隙間に最適な状態で繁栄し、成長と健康のためにこれらの小さな生息地を利用しています。
 ホナガイヌビユは、南アメリカ原産の雑草で、畑地や道端などで見られる帰化植物です。別名「アオビユ」とも呼ばれ、名前の由来は「穂が長く伸びる」ことにあります。ヒユ科の植物で、葉先がわずかに凹んでいること、花期に長い穂状の花序をつけ、果実には深いしわがあるのが特徴です。葉は三角状卵形で長柄があり、先端は円頭でわずかに凹みます。
茎や葉には毛がほとんど見られません。 花は上部の葉腋から伸びた長い穂状に付き、先が芒状に尖りません。 本種をアオビユと呼ぶこともありますが、アオゲイトウも同名で呼ばれることがあります。繁殖力が高いため、農耕地などでは雑草として扱われます。葉は食用にされ、ジャマイカでは「カラルー」、モルディブでは「マッサグー」と呼ばれ料理に使われます。インドでも伝統的なアーユルヴェーダのハーブとして利用されています。
ホナガイヌビユは、南アメリカ原産の雑草で、畑地や道端などで見られる帰化植物です。別名「アオビユ」とも呼ばれ、名前の由来は「穂が長く伸びる」ことにあります。ヒユ科の植物で、葉先がわずかに凹んでいること、花期に長い穂状の花序をつけ、果実には深いしわがあるのが特徴です。葉は三角状卵形で長柄があり、先端は円頭でわずかに凹みます。
茎や葉には毛がほとんど見られません。 花は上部の葉腋から伸びた長い穂状に付き、先が芒状に尖りません。 本種をアオビユと呼ぶこともありますが、アオゲイトウも同名で呼ばれることがあります。繁殖力が高いため、農耕地などでは雑草として扱われます。葉は食用にされ、ジャマイカでは「カラルー」、モルディブでは「マッサグー」と呼ばれ料理に使われます。インドでも伝統的なアーユルヴェーダのハーブとして利用されています。
 エゾギクは、日本、朝鮮半島、中国原産で、キク科エゾギク属の半耐寒性一年草です。園芸品種が多数育種されています。草丈は15~100cmです。葉はヘラ形~長楕円形で、葉縁に鋸歯があり、互生して付きます。夏に花茎を伸ばし、花径が3~15cmの頭花を咲かせます。花色には白、赤、ピンク、紫色があり、花の咲き方は一重、八重、七分咲き、ポンポン咲きがあります。別名で、サツマギク(薩摩菊)、チャイナアスターとも呼ばれます。以前はシオン属に属していましたが、今はエゾギク属とされ、1属1種のみです。従って、孔雀アスター、アルペンアスターは、シオン(アスター)属なので異属となります。エゾギクゅ(蝦夷菊)は和名ですが、北海道産ではありません。一説には「江戸菊」の転訛から蝦夷菊となったものと推測されます。
エゾギクは、日本、朝鮮半島、中国原産で、キク科エゾギク属の半耐寒性一年草です。園芸品種が多数育種されています。草丈は15~100cmです。葉はヘラ形~長楕円形で、葉縁に鋸歯があり、互生して付きます。夏に花茎を伸ばし、花径が3~15cmの頭花を咲かせます。花色には白、赤、ピンク、紫色があり、花の咲き方は一重、八重、七分咲き、ポンポン咲きがあります。別名で、サツマギク(薩摩菊)、チャイナアスターとも呼ばれます。以前はシオン属に属していましたが、今はエゾギク属とされ、1属1種のみです。従って、孔雀アスター、アルペンアスターは、シオン(アスター)属なので異属となります。エゾギクゅ(蝦夷菊)は和名ですが、北海道産ではありません。一説には「江戸菊」の転訛から蝦夷菊となったものと推測されます。
 ナミキソウは、北海道~九州の各地に分布するシソ科の多年草です。園芸的に人気のあるタツナミソウの仲間ですが、波(浪)が来るような海岸の砂地に自生するため、ナミキソウと名付けられました。日本に育つナミキソウは在来種ですが、日本以外でも東アジアの温帯に広く見られます。葉は長さ8~20mmの先端が丸まった長楕円形で、縁には不明瞭なギザギザがあり、茎から対になって生じています。茎は柔らかですが断面は四角形で、地中に走出枝と呼ばれる小枝を出して繁茂します。ナミキソウの開花は6~9月で、上方にある葉の脇に、青紫色をした唇形の花を2輪ずつ咲かせます。花は筒状の部分が長く、その基部は急に曲がって立ち上がっています。下唇部分は白いですが斑紋(模様)はなく、一方向を向いて横向きに咲きます。
ナミキソウは、北海道~九州の各地に分布するシソ科の多年草です。園芸的に人気のあるタツナミソウの仲間ですが、波(浪)が来るような海岸の砂地に自生するため、ナミキソウと名付けられました。日本に育つナミキソウは在来種ですが、日本以外でも東アジアの温帯に広く見られます。葉は長さ8~20mmの先端が丸まった長楕円形で、縁には不明瞭なギザギザがあり、茎から対になって生じています。茎は柔らかですが断面は四角形で、地中に走出枝と呼ばれる小枝を出して繁茂します。ナミキソウの開花は6~9月で、上方にある葉の脇に、青紫色をした唇形の花を2輪ずつ咲かせます。花は筒状の部分が長く、その基部は急に曲がって立ち上がっています。下唇部分は白いですが斑紋(模様)はなく、一方向を向いて横向きに咲きます。
 アップルミントは、ヨーロッパ東部,イギリス,トルコ,アルジェリア,モロッコ,チュニジアなどに自生し,世界各地で栽培されています。多年草で、草丈30~80cm茎はまばらに有毛し葉は有毛しわがあり,長さ3.0~4.5cm,幅2~4cmで、鋸歯があります。花は茎頂の花序に付き薄桃色~白色です。甘いりんごの香りがするミントです。葉の色は明るい緑色で、料理やハーブティー、デザートなどに幅広く使えます。丸い形の葉から、和名で「丸葉薄荷(マルバハッカ)」とも呼ばれます。また、葉の表面が密生した細かい毛で覆われていることから「綿毛のような」を意味する「ウーリーミント」の呼び名もあります。
アップルミントは、ヨーロッパ東部,イギリス,トルコ,アルジェリア,モロッコ,チュニジアなどに自生し,世界各地で栽培されています。多年草で、草丈30~80cm茎はまばらに有毛し葉は有毛しわがあり,長さ3.0~4.5cm,幅2~4cmで、鋸歯があります。花は茎頂の花序に付き薄桃色~白色です。甘いりんごの香りがするミントです。葉の色は明るい緑色で、料理やハーブティー、デザートなどに幅広く使えます。丸い形の葉から、和名で「丸葉薄荷(マルバハッカ)」とも呼ばれます。また、葉の表面が密生した細かい毛で覆われていることから「綿毛のような」を意味する「ウーリーミント」の呼び名もあります。
 コウゼンギクは、シオンの仲間で、アメリカ原産の菊の仲間がヨーロッパで品種改良され、明治時代に日本に渡来した多年草です。原野、空地、道端などに生え、茎の高さが30~70cmになる北アメリカ原産帰化植物です。よく分枝し、枝先に直径2.5cmほどの青紫色の頭花を散房状に多数つけます。頭花の中心部は両性の筒状花で黄色です。その周辺に雌性の青紫色の舌状花が並びます。舌状花は20個以上、総苞片は披針形で、先が尖っています。そう果には長い冠毛があります。葉は互生し、狭披針形で、柄がなく、なかば茎を抱き全縁か低い鋸歯があります。ユウゼンギクの花言葉は「老いても元気で」「後知恵」「若者に負けぬ元気」です。これらの花言葉は、ユウゼンギクが暑さや寒さに強く、晩夏から秋まで長く咲き続ける生命力に由来します。また、友禅染のように美しい花を次々に咲かせることからつけられたとされています。
コウゼンギクは、シオンの仲間で、アメリカ原産の菊の仲間がヨーロッパで品種改良され、明治時代に日本に渡来した多年草です。原野、空地、道端などに生え、茎の高さが30~70cmになる北アメリカ原産帰化植物です。よく分枝し、枝先に直径2.5cmほどの青紫色の頭花を散房状に多数つけます。頭花の中心部は両性の筒状花で黄色です。その周辺に雌性の青紫色の舌状花が並びます。舌状花は20個以上、総苞片は披針形で、先が尖っています。そう果には長い冠毛があります。葉は互生し、狭披針形で、柄がなく、なかば茎を抱き全縁か低い鋸歯があります。ユウゼンギクの花言葉は「老いても元気で」「後知恵」「若者に負けぬ元気」です。これらの花言葉は、ユウゼンギクが暑さや寒さに強く、晩夏から秋まで長く咲き続ける生命力に由来します。また、友禅染のように美しい花を次々に咲かせることからつけられたとされています。
 ノウタケは、梅雨の時期から秋に掛けて、林の中の地上に発生するきのこで、日本各地やヨーロッパ、北米、南米などに広く分布しています。大きさは、7㎝~15㎝と子どもから大人の握りこぶしくらいの大きさがあります。成長したノウタケは茶褐色の外皮に覆われ、この外皮には、ビロードを思わせるような細毛がうっすらと生え、脳を思わせる「しわ」があります。また内部には「グレバ」と呼ばれる“胞子をつくる組織”があり、こちらはスポンジ状で弾力をもつという特徴があります。ノウタケは、発生当初は白色をしていますが、成熟するにつれ茶色、褐色に変化していきます。そして最終的には、黄褐色の独特な匂いを持つ液汁を出し、徐々に自分自身を分解していきます。分解が進み個体が乾燥すると、外皮が剥がれ内部の胞子がむき出しに。この胞子が風や虫たちによって飛散する事で、種を繁栄させます。様々な特徴を持つきのこの中でも、ノウタケの変化は非常にドラマチックだなと感じます。
ノウタケは、梅雨の時期から秋に掛けて、林の中の地上に発生するきのこで、日本各地やヨーロッパ、北米、南米などに広く分布しています。大きさは、7㎝~15㎝と子どもから大人の握りこぶしくらいの大きさがあります。成長したノウタケは茶褐色の外皮に覆われ、この外皮には、ビロードを思わせるような細毛がうっすらと生え、脳を思わせる「しわ」があります。また内部には「グレバ」と呼ばれる“胞子をつくる組織”があり、こちらはスポンジ状で弾力をもつという特徴があります。ノウタケは、発生当初は白色をしていますが、成熟するにつれ茶色、褐色に変化していきます。そして最終的には、黄褐色の独特な匂いを持つ液汁を出し、徐々に自分自身を分解していきます。分解が進み個体が乾燥すると、外皮が剥がれ内部の胞子がむき出しに。この胞子が風や虫たちによって飛散する事で、種を繁栄させます。様々な特徴を持つきのこの中でも、ノウタケの変化は非常にドラマチックだなと感じます。
 ミゾソバは、北海道から九州にかけての水辺や湿地など、湿った場所に生育する高さ30~100cmほどの一年草です。田のあぜや用水路の泥が溜まっているような場所、ため池の岸など常に湿っている場所であれば、ごくふつうにみられる植物です。ただ、定期的な攪乱がある生育に適しているようで、長期間、攪乱がない状況では徐々に生育量が減少します。花は7~10月頃とされますが、秋の訪れとともに花が目立つようになります。花は茎の先端あるいは上部の葉腋から出た枝の先に、10数花が密集して付き、花序の柄の上部には多数の腺毛が生えています。一つの花は直径6~8mm程度で、花被は5裂して長さ4~7mm、花被片の下部は白色、先端はふつう紅紫色を帯びていますが、集団や個体によって花被片の色いは濃淡があり、紅色と言ってよいほど濃いものもあれば、ほぼ白色のものもあります。
ミゾソバは、北海道から九州にかけての水辺や湿地など、湿った場所に生育する高さ30~100cmほどの一年草です。田のあぜや用水路の泥が溜まっているような場所、ため池の岸など常に湿っている場所であれば、ごくふつうにみられる植物です。ただ、定期的な攪乱がある生育に適しているようで、長期間、攪乱がない状況では徐々に生育量が減少します。花は7~10月頃とされますが、秋の訪れとともに花が目立つようになります。花は茎の先端あるいは上部の葉腋から出た枝の先に、10数花が密集して付き、花序の柄の上部には多数の腺毛が生えています。一つの花は直径6~8mm程度で、花被は5裂して長さ4~7mm、花被片の下部は白色、先端はふつう紅紫色を帯びていますが、集団や個体によって花被片の色いは濃淡があり、紅色と言ってよいほど濃いものもあれば、ほぼ白色のものもあります。
 マグワは、朝鮮半島から中国にかけての地域に分布し,栽培されている夏緑広葉樹です。雌雄異株。樹高は10mくらいになります。養蚕用に多くの品種が育種されていますが,栽培する場合は地上50cmくらいのところで一度幹を切断し,側芽を生長させて葉を収穫する株立ち栽培が一般的です。葉は卵形から広卵形で,しばしば浅く3裂します。雄花,雌花ともに尾状に多数つき,春から初夏に咲きます。果実は集合果といい,成熟すると黒紫色に肥大し多汁質になるためまるで一個の果実のように見えます。近縁種のヤマグワは各地の山野に自生し,一般的にはマグワ同様,雌雄異株ですが,稀に雌雄同株のことがあります。また葉が厚めのマグワと比較しヤマグワは薄く,養蚕用にはマグワより育成された栽培品種を栽培することが多いようです。
マグワは、朝鮮半島から中国にかけての地域に分布し,栽培されている夏緑広葉樹です。雌雄異株。樹高は10mくらいになります。養蚕用に多くの品種が育種されていますが,栽培する場合は地上50cmくらいのところで一度幹を切断し,側芽を生長させて葉を収穫する株立ち栽培が一般的です。葉は卵形から広卵形で,しばしば浅く3裂します。雄花,雌花ともに尾状に多数つき,春から初夏に咲きます。果実は集合果といい,成熟すると黒紫色に肥大し多汁質になるためまるで一個の果実のように見えます。近縁種のヤマグワは各地の山野に自生し,一般的にはマグワ同様,雌雄異株ですが,稀に雌雄同株のことがあります。また葉が厚めのマグワと比較しヤマグワは薄く,養蚕用にはマグワより育成された栽培品種を栽培することが多いようです。
 タラノキは、林縁や明るい林の中などに生える落葉低木です。森林伐採後や土砂崩れの跡地などで、植生が回復していく際にいち早く育つ「パイオニア植物」としての性質を持っています。幹や葉に鋭い刺が多く、うかつにさわると痛い思いをします。枝先につく新芽は「たらの芽」と呼ばれ、春の味覚として人気があります。8月から9月にかけて枝先に花の穂を出し、小さな白い花を多数咲かせます。花にはハチやチョウなどの訪花昆虫がたくさんやってきます。花の後、小さな丸い球形の果実がたくさんでき、熟すと黒く色づきます。タラノキの効能は、主に樹皮や根皮が持つ糖尿病、高血圧、健胃、利尿作用で、民間薬として広く利用されてきました。また、若い芽(タラの芽)は山菜として食べられ、滋養強壮、抗酸化作用、ビタミンやミネラル補給に役立ちます。タラの芽に含まれる抗腫瘍作用を持つ成分については、癌治療への応用も期待されています。
タラノキは、林縁や明るい林の中などに生える落葉低木です。森林伐採後や土砂崩れの跡地などで、植生が回復していく際にいち早く育つ「パイオニア植物」としての性質を持っています。幹や葉に鋭い刺が多く、うかつにさわると痛い思いをします。枝先につく新芽は「たらの芽」と呼ばれ、春の味覚として人気があります。8月から9月にかけて枝先に花の穂を出し、小さな白い花を多数咲かせます。花にはハチやチョウなどの訪花昆虫がたくさんやってきます。花の後、小さな丸い球形の果実がたくさんでき、熟すと黒く色づきます。タラノキの効能は、主に樹皮や根皮が持つ糖尿病、高血圧、健胃、利尿作用で、民間薬として広く利用されてきました。また、若い芽(タラの芽)は山菜として食べられ、滋養強壮、抗酸化作用、ビタミンやミネラル補給に役立ちます。タラの芽に含まれる抗腫瘍作用を持つ成分については、癌治療への応用も期待されています。